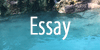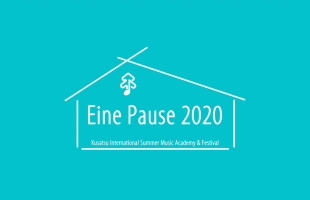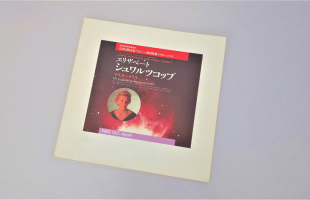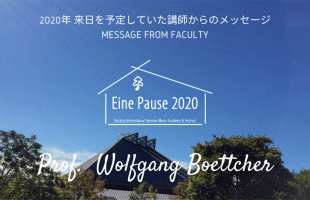文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:小宮正安
第38回プログラムより(2017年発行)
最初にはっきりさせておこう。それは、今日私たちがよく知っている公開演奏会のあり方は、歴史的に見ればかなり最近になってから形作られたものだ、ということだ。音楽を聴くために入場券を買うという現象からして、中央ヨーロッパにおいては18世紀半ばから少しずつ現れ始め、18世紀も最後の四半世紀に至ってようやく一般化した。イギリスではもう少し早い時期からこのような動きが見られたものの、それでも大昔からではなかった。
また、演奏会を主催する専門家というものも存在しなかった。芸術家―つまり作曲家や演奏家―自身が演奏会の主催者であって、純益はそのまま彼らの懐に入った。あるいは慈善演奏会というものも存在し、その場合は社会的な目的のために収益が用いられたが、こうした演奏会における主催者=芸術家のメリットとしては、会場を埋め尽くした人々に自らの芸術を披露できるという喜びがあった。
にもかかわらず、公開演奏会はけっして日常的な催しではなかった。音楽の多くは、私的な集まりの中で生産あるいは消費され、特定の目的、あるいはそれを聴きに来ている限られた人々のみが念頭に置かれていた。自分で音楽を演奏しなかったり、私的な音楽の集いに呼ばれない人は、劇場で劇伴音楽を聴いたり、オペラへ行ったり、教会でおこなわれる大掛かりな礼拝に足を運んだり、はたまた舞踏会やダンスの催し、あるいは民族音楽の演奏といった場で音楽を耳にした。さらには年に2回、クリスマスとイースターの前には演奏会シーズンがあり、夏には野外演奏会も開かれていた。
*
モーツァルトの父レオポルト・モーツァルトが自分の子供たちを引き連れてヨーロッパ中を旅し、各都市で演奏をさせた話は有名だ。ただしそうした演奏の場も、今日のような意味での「演奏会」でなかったことには注意しておきたい。というのもそこに集った人々は、先ずモーツァルト姉弟に驚きを覚えることを何よりも重要視し、次に演奏を聴く、という姿勢だったからである。
こうした旅の途上、レオポルトは広間=ホールを借り、神童が登場する旨を大急ぎで告知し、それに興味を持った人々が来場する、というスタイルが普通だった。もしもそうした広間=ホールが存在しない場合は、ヴォルフガングに教会のオルガンで演奏させる場合もあった。そしてチケットの収益や聴衆のカンパを元手に、彼らは旅を続けた。それゆえ皇后マリア・テレジアは、モーツァルト一家が物乞いのようにしてヨーロッパを旅している、と批判したのである。
子供たちが貴族や領主の館に登場する際も、それは公開の演奏会ではなく、限られた聴衆のための私的な音楽の集いであり、せいぜい家庭演奏会だった。もちろんいくつかの街には演奏会用ホールが既に存在していたが、他の街にはそうした施設はなかった。モーツァルトが若者になってからパリに赴いた際、彼の地では公開演奏会がしっかりと確立されていることを経験したいっぽう、ウィーンにおいては、パリのような演奏会をウィーンでもおこなおうと目論むも結局うまく事を運べない演奏会の主催者のおかげで、期待したほどの成功を得られない場合もあった。
となると原則的には、作曲家や演奏家が演奏会の主催者になるしかなく、またそれが当然という状況に対し、モーツァルト自身もまったく疑問に思っていなかったことになる。モーツァルトの器楽曲の大半が、家庭音楽や家庭演奏会の場において、私的なあるいは半ば公開の形で演奏される音楽のために書かれている所以であり、これは彼にとって自明だった。いや、それでも当時の作曲家の中でモーツァルトほど、新たな公開演奏会の誕生と発展の様子を、旅路で、そして本拠地において個人的に体験した者はいなかったかもしれない。子供時代の最初の経験から成人になってウィーンでの演奏会に登場するまでの長い発展の道のりを、彼は身をもって経験し、時にはみずから積極的に形作っていったのだから。
以下の部分では、まったく異なる2種類の演奏会について述べることとなるが、その際ぜひ頭に留めていただきたいことがある。つまり、これらの演奏会はモーツァルトにとっては重要なものだったが、今日の一般的な演奏会のあり方とはそもそも比較不可能な催しだった、という点だ。
*
モーツァルトの時代、ウィーンにはザルツブルクと同様、演奏会ホールというもの自体が存在しなかった。ザルツブルクにおける器楽の演奏は、どのような編成であろうと、私的あるいは半公開の状態でおこなわれたのである。(ここでいう半公開とは、大勢の招待客が音楽を聴く、つまり家族や友人たちだけが音楽を楽しむ状況ではない、ということだ。)ウィーンでは、劇場や多目的ホールが空いている日には演奏会がおこなわれていた。ちなみに、ウィーンで初の演奏会ホールはといえばウィーン楽友協会の中に作られたもので、オープンしたのは1831年。以上のことを知っておくと、以下のテーマをよりよく理解し、納得していただけるだろう。
*
モーツァルトの時代、公開演奏会のレパートリーはというと、まず目に付くのが管弦楽伴奏つきの声楽曲、つまりはオラトリオ、カンタータ、合唱曲、アリアといったものだった。次いで管弦楽曲を中心とした器楽曲で、室内楽が演奏されることはごく稀だった。
なお室内楽曲(Kammermusik)とは、文字通り室内(Kammer)のための音楽であり、室内(Kammer)とは「部屋」を指す古い言葉である。つまり室内楽曲は、家庭音楽や家庭演奏会を念頭に書かれていた。もちろん公開演奏会で、部屋用の曲を演奏するのは理論上可能なのだが、上のような経緯から室内楽曲が公開演奏会で演奏されることはきわめて稀であり、プログラムに新味を与えたり楽器奏者の多様な才能を示したい場合のみ取り上げられた。その一例が、モーツァルトがピアノとオーケストラのための協奏曲を演奏すべく登場した際の公開演奏会で、彼はそこで自ら、ピアノ独奏曲も演奏している。あるいは1784年、ヴァイオリニストのレギーナ・ストリナザッキの主催する演奏会においても、モーツァルトは当演奏会で彼女とともに初演するために作ったヴァイオリンとピアノのためのソナタを、他の曲目とともに上演している。
いずれにせよ、このように当時の室内楽の地位を知れば、室内楽曲の目指すところや作曲の目的を理解することができるだろう。この両者の要素については、また後ほど説明しよう。
*
数年前、ウィーン楽友協会アーカイブの同僚であるイングリート・フックスが、貴重な発見をおこなった。発見されたのは、上部ハンガリー(現在のスロヴァキア)在住のさる地方貴族が、ウィーンに住む友人であり腹心でもあった人物と交わした記録。これはやがて、出版されることとなった。
このウィーンに住んでいた人物だが、音楽に非常に関心があり、ウィーンの音楽生活についての最新情報を逐一報告することに熱心だった。その中に1786年、モーツァルトが「音楽クラブ」を設立したという記事が載っていたのである。もちろんクラブといっても、今日とは異なる意味合いであって、ある特定の意図や目的のため―この場合は音楽を聴いたり演奏したりするため―に、複数の人々が集まる協会のことを指している。
ちなみに、この手紙に記されている当該の報告を抜粋すると次の通り。「新しい音楽の催しについてですが、開催時間について異論はありません。毎週11時から1時まで、私はモーツァルト氏の音楽クラブへ出かけます。そこには、ヘルツフェルト伯爵夫人、ツォイス男爵夫人、ジャカンのご子息、そして多くの人々が集まり、オペラから抜粋してきたアリアや、オペラ全曲を歌っています。」もちろん新しい音楽として、室内楽作品も演奏された。またアリアも取り上げられたが、それがピアノ伴奏で歌われたのか、あるいは器楽アンサンブルによる伴奏だったのかは分からない。なお手紙の中に出てくる人々は職業音楽家ではなかったが、それについてはまったく問題なかった。彼らはいずれも完璧な音楽的素養と腕前を具えているいっぽうで、あえて音楽活動を生業とせず、人生の楽しみのために音楽を愛していたからである。
ところでこの記録が発見されるまで、私たちは、マイケル・ケリーという歌手―ロンドン出身で長い間ウィーンで活躍していた人物である―の回想録中、以下のような短い文章からしか、当時の状況を伺い知れなかった。曰く、「モーツァルトは日曜日に演奏会をおこない、私はそれに欠かさず出かけた」というもので、そこからこれらの演奏会がモーツァルトの住まいでおこなわれたことは分かっていたのである。なおモーツァルトは、現在モーツァルト・ハウスとして一般公開されているシューラー通りの建物に居を構えていた(現在のモーツァルト・ハウスの入り口はドーム通りとなっている)。そして自らの住まいで催すこれらの演奏会にあたって、モーツァルトは紛うことなく主催者だった。ただし演奏会に際し、やはりモーツァルトが自宅で主催した舞踏会のように、入場料をとったのかどうかについては不明だが。
この「音楽クラブ」と呼ばれる演奏会だが、それとはまったく別個にモーツァルト家でおこなわれていた家庭音楽と混同してはならない。彼は、自身の音楽家仲間とも自宅で音楽を演奏していた。さらに1784年、モーツァルトの生徒たち(いずれも女性)が、彼の命名日の祝いを、自分たちがいつもレッスンを受けている彼の住まいでおこなって驚かせたという記録もある。ただしそれが、この年だけの出来事だったのか、あるいは毎年のようにおこなわれたのかについても分かっていない。
*
モーツァルトによる音楽クラブは、自分の住まいにおける音楽活動の特別な形だった。自身の住居で私的に演奏をおこなったり、家族や友人がそれに耳を傾けたりすることのほうがしばしばで、こちらが一般的には普通だった。
なお、「家庭演奏会」と「家庭音楽」は区別して用いられるべき概念だが、家庭音楽のほうは単なる自分自身の楽しみのためのものであって、聴き手の存在を想定していない。また、モーツァルトの時代にも家庭演奏会という言葉はよく用いられたが、それよりもしばしば用いられたのが「音楽サロン」という表現である。「音楽サロンを構える」とは、「家庭演奏会を開く」というのと同義語だったのだ。言葉の意味合いからすれば、住まいや家の中で一番大きく美しい空間がサロンであり、そこで家庭演奏会を催すということだったのである。そして元々空間を指していたサロンという言葉が、聴衆とともに音楽行為をおこなうことも意味するようになった結果、半公開の音楽サロンと家庭演奏会は同義語として用いられるようになったのである。もちろん聴衆がサロンだけに入りきれない場合は、それに隣接する部屋に集まり、扉を開け放して音楽に聴き入った。
家庭音楽、および音楽サロン/家庭演奏会のためには、ピアノ曲や室内楽曲、歌曲や多声声楽作品が作曲された。またオペラのアリアやオペラの一部分、さらには管弦楽曲のピアノ編曲版も演奏された。ピアノ編曲版というものが生まれた理由も、まさにこうした状況が存在したためである。
例えば新作オペラが初演されると、ピアノ伴奏つきでその抜粋を家庭でも歌えるよう、ただちに楽譜が出版された。このようにしてオペラ作品は有名になっていったのであり、単にオペラハウスで演奏されたから有名になったというわけではなかった。またこうした家庭演奏会のために、管弦楽曲の編曲物や、管弦楽伴奏付きの協奏曲の編曲物も作られた。
なおこれらの編曲物は、モーツァルトの同時代には既に生まれており、彼自身が実際目を通したものもあるが、彼が世を去ってから久しい19世紀半ばまでさかんに作られた。その場合、協奏曲においては、ピアノパートは決まってオリジナルのままに、伴奏部分の編成が縮小されて、というケースがお決まりだった。例えばモーツァルトのピアノ協奏曲が、公開演奏会の場でオリジナルの管弦楽伴奏によって上演されるよりも、室内楽伴奏版を通じ、音楽サロンや家庭演奏会で演奏される機会のほうがよほど多かったのである。
*
家庭演奏会や音楽サロンは多くの家庭で、しかも特に冬の時期に催された。というのも夏は野外で演奏したり、屋外で別の楽しみがあったり、そもそも田舎に滞在したりということが普通だったからである。
家庭演奏会は、毎週あるいはある決まった日にちごとにおこなわれるのが通例で、それによって、いつどこで家庭演奏会がおこなわれるのかを知ることができた。家族の友人であれば、予定されている日時に出かけるだけで(たとえ特別な招待や予約を入れなくても)、演奏会に入れてもらえるという具合だった。また、自分の友人を連れて行ってもよかった(こうした制限の緩さゆえ、先ほどから家庭演奏会のことを半公開の催しと呼んでいるのである)。
もちろん、このように定期的な家庭演奏会が行われる場においては、聴衆が何人やってくるかは分からなかった。それでも問題とならなかったのは、何も演奏がおこなわれているサロンに聴衆が座ったり立ったりしている必要はなく、それに隣接する部屋にいてもよかったからである。狭く感じるのは、それだけ人々の関心が高いという証拠だった。また演奏の合間や終了後には、気分転換のために飲み物や食べ物が提供された。演奏の輪に職業音楽家が入るのは例外的だったが、職業音楽家でなくてもきわめてレヴェルの高い演奏者たちであり、彼らは音楽をすることに喜びを見出すがゆえに、それを生業にはしていない人々だった。
こうした家庭演奏会で曲が決定されるのは、いつもぎりぎりになってからだった。演奏される曲に関するプログラム冊子もメモも存在せず、それゆえ現在の私たちにとって、そこで何が演奏されていたのかを細部まで把握するのは不可能である。というわけで、家庭演奏会で何が取り上げられたかについては、日記や回想録や手紙に頼るしかない。なおモーツァルトは、既に先ほど述べた音楽クラブ……つまり家庭演奏会をさらに高度な形で組織した催し……を自らの住まいで主催しただけでなく、貴族や市民の家庭での家庭演奏会にも出演した。しかもウィーンから父親に宛てて書いた手紙の中で、彼はこのことを幾度となく述べているが、それを特別視していた節はなく、自分が音楽家として自立してゆくための1つの手段と見なしていたことが分かる。
*
このような家庭演奏会は、ウィーンでは特段珍しいものではなかった。もちろんこの街を訪れた多くの旅行者にとってみれば、ここで多くの家庭演奏会が開かれていること自体に目を見張る思いだったろうが……。作曲家や歌手や楽器演奏者が主催する公開演奏会の数も、他の都市に比べると非常に多かった。音楽都市ウィーンにおいては、多くの人々がそうした方法で演奏会を催し、またそれに興味を抱く聴衆も多数存在したのである。というわけでここからは、モーツァルトの時代におけるこうした演奏会の一場面を覗いてみることとしよう。
モーツァルトは、しばしばこのような演奏会を主催し、また同僚が主催した演奏会にもよく登場した。そうした演奏会を主催する時、彼は劇場や広間を借りて、告知や宣伝をおこない、チケットを売って(なお前売り券は常に主催者の住まいで手に入れることができた)、オーケストラを手配し、さらに共演してくれる演奏家の確保に励んだ。1回限りの演奏会ではなく、3回4回と続くチクルス形式の演奏会を企画する際には予約制とし、予約会員を募った。
こうした作業において、モーツァルトを手助けしてくれる人物がいたのかどうかは分からない。ただし覚えておくべきは、必要な経費を彼が全て支払い、そこから差し引いて生まれる純益を手にしていたということである。演奏会の企画がうまくゆかず、それ故にあるいは別の理由ゆえに来場者が少ないと、赤字を負わなければならなかった。
またモーツァルトは、自分で主催する演奏会において、自作の曲だけを演奏するのではなく、ただしあくまでプログラムの中心には、自身を作曲家ならびにピアニストとして示せるような作品を置いていた。またこうした演奏会用に新作のピアノ協奏曲を作った場合、彼はその直後にそれを印刷、あるいは―こちらのほうが一般的だったのだが―写譜をさせて公開した。するとすぐさま、管弦楽パートが室内楽編成に編曲され、家庭演奏会(音楽サロン)で取り上げられていったのである。往々にして2台ピアノ用に編曲がなされたが、その場合、1台目はオリジナルのピアノパートを、2台目がピアノ用に編曲された管弦楽パートを担当するのが常だった。
いずれにせよ、このような公開演奏会を催すにもっとも適した時期は、クリスマスとイースターの前だった。それには宗教的な理由がある。これらの時期は両方とも禁欲期間であり、人々は娯楽を我慢し、クリスマスやイースターの祝日に向けて心を整えなければならなかった。
そうした状況の中、オペラや演劇は娯楽と見なされていたのだが、演奏会はその限りではなかったのである。そのため、劇場やオペラハウスはこれらの期間は閉鎖されていたにもかかわらず、演奏会のために貸し出すことは可能だった。しかも、劇場の閉鎖期間が長いという理由から、クリスマスの前よりもイースターの前のほうがより多くの演奏会が開催された。それどころか、イースターの前におこなわれる演奏会は「禁欲演奏会」とも呼ばれたのである。こうして、クリスマスやイースター直前の期間が演奏会シーズンだった。夏には野外演奏会が通例で、それゆえ夏を本当の意味での演奏会シーズンと見なすことはできない。
モーツァルトは、クリスマスとイースター前のこれらの時期に1回物の演奏会を開き、場所についても宮廷劇場であるブルク劇場を借りる場合もあった。また演奏会チクルスの場合は、別のホールを借りた。彼は父親に宛てて、予約客のリストを誇らしげに送ったことがあるが、そこにはウィーンのVIP級の貴族の名前が記されている。もちろん市民もモーツァルトにとっては大切な得意先だったのだが、自ら主催する演奏会の客として、父親には貴族の名前を出したほうが印象深いと判断したのだろう。
またこうした演奏会用に、モーツァルトは交響曲とピアノ協奏曲も作曲している。例えば1786年のクリスマス前に催された演奏会のためには、今日「プラハ交響曲」の名前で親しまれているニ長調の交響曲を書いた。あるいは1785年の禁欲演奏会チクルスのためには、「ピアノ協奏曲ニ短調」KV.466と「ピアノ協奏曲ハ長調」KV.467を作った。彼は聴衆を常に新しさで驚かせようと考えており、それゆえにこの2つの協奏曲はまったく異なる内容となっている。実際このようなチクルスにおいては、ある曲が別の曲に似通ったものとなってはダメだった。
しかも「ピアノ協奏曲ニ短調」を演奏する際、モーツァルトはペダル・ピアノ―つまりはオルガンのように足で音階の弾けるペダルが付いたピアノ―を演奏して、聴衆の度肝を抜いたのである。ペダルを使って何をどのように演奏するかということについては、ウィーン楽友協会アーカイブが保存しているこの曲の直筆譜を見ればよく分かる。いずれにしても、これら2つの協奏曲も室内楽伴奏版に編曲された。しかもペダル・ピアノをこの協奏曲で用いることは、モーツァルト以外もはや誰もおこなわなくなってしまった。
1780年も後半になると、モーツァルトは自身で演奏会を主催しなくなった。というのもそれまで何年にもわたって、彼はあまりにも演奏会を開きすぎ、そうでなくても様々な演奏会で他の音楽家と共演するということをしすぎたのである。結果、彼が登場してもセンセーションを巻き起こせず、彼をいつでも聴ける状態に人々が慣れっこになってしまった。これが切符の売り上げに響かないわけがない。何しろ音楽家であれば誰もが……当時から今日にいたるまで……、希少価値という要素を大事にするもの。ところがモーツァルトは、人前で自己プロデュースできることこそが嬉しかったのだ。
またこのような公開演奏会、そして演奏会チクルスには、プログラム誌が存在しなかった。あるいは例えばポスターのように、モーツァルトが演奏会を宣伝するためのものが保存されることはまれだった。それゆえ私たちにとって、モーツァルトが主催した演奏会のプログラムの詳細は分からない。手紙や日記や回想録が、それぞれの演奏会で取り上げられた曲を窺い知れる唯一のよすがである。ただし多くの作品について、それらが完成された日付に関しては、「禁欲演奏会」のために作曲されたということも推測可能なのである。
*
このように当時の公開演奏会は、今日のそれとほとんど全てにわたって異なっていた。そして、歴史的な意味における家庭演奏会(あるいは音楽サロン)に至っては、現在もはや存在しない。ただし、モーツァルトが作曲家でありピアニストであっただけでなく、演奏会の主催者であったことに思いを巡らせてみるのは楽しく、また重要だ。モーツァルト自身そうした存在として、これらの目的のために、新作を作曲することをもっぱらとしたのだから。