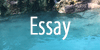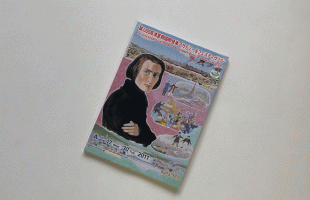文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:小宮正安
第33回プログラムより(2012年発行)
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、生涯に3度パリを訪ねている。最初の訪問は1763年11月から64年4月にかけての計5ヵ月間。当時モーツァルトはわずか8歳だったが、神童という触れ込みで姉のナンネルルと一緒に演奏会に出演したり、生まれて初めて自分の作品を出版したりといった体験に恵まれた。
またこうした活躍を受けて、一枚の銅版画も作られた。天才姉弟のヴォルフガングとナンネルルが一緒に音楽をしている情景を描いたもので、彼らの父親であるレオポルトの姿も見える。この銅版画はその後幾度となく複製され、モーツァルトの姿を伝える正統的な一枚として、今日に至るまでよく知られている。
このような具合に、最初のパリ滞在は大成功を収めた。しかも1764年4月10日にモーツァルト父子はロンドンに出発することとなるのだが、荷物の多くをパリに置いていったのである。そしてロンドンからの帰途、1766年4月10日に再びパリを訪れ、ヴェルサイユでフランス王夫妻を前に幾度となく演奏をおこない、2ヵ月後にこの街を後にすることとなった。
この2回に渡るパリ滞在を通じ、幼いモーツァルトは大成功を手にするだけでなく、きわめて重要な体験を積むこととなった。神童時代の彼が訪れたウィーン、パリ、ロンドンといった大都市は、単にヨーロッパを代表する重要な首都というだけでなく、それぞれ独自の音楽文化を育む音楽の中心地だったからだ。というわけでモーツァルトはパリに滞在することで、フランス音楽の伝統はもちろん、当時の最先端のフランス音楽を吸収し、彼ならではの様式を作り上げてゆくことができた。
1778年3月23日、22歳のモーツァルトは3度目となるパリ訪問を実現した。今回彼に付き添ったのは母親。姉のナンネルルは、もはや神童という触れ込みで演奏会を開くには成長しすぎており、父親は勤め先のザルツブルクの宮廷から休暇の許しを得ることができなかった、というのがその理由である。
ところでほぼ半年にわたったこのパリ滞在、多くのモーツァルト伝ではまるで散々なものであったかのように描かれている。だがそれは、かなり的外れなものであるといわざるをえない。
たしかに3度目のパリ滞在は、重苦しい運命の影に覆われていた。6月3日には、旅に付き添ってきた母親が57歳で死去。モーツァルトはこの出来事に耐え、悲嘆にくれる父親を慰め、芸術的な目的を遂行すべく母の死に影響を受けまいと懸命になった。じっさいこの数週間の出来事を通じ、モーツァルトが成熟を余儀なくされたのはたしかである。彼は、思慮深く、地に足のついた、現実的で、人生経験豊かな人間へと成長を遂げた。もちろんその後のモーツァルトがいつでもこのような人物だったわけではないが、母の死後彼が見せた態度は、たしかにそうだった。
いっぽう多くのモーツァルト伝によれば、この3度目のパリ旅行はモーツァルト父子の相克が根底にあるという見方が圧倒的である。たしかにモーツァルト自身、パリ滞在中に父親に対して全ての事柄を逐一報告しているわけではなく、父親の側としても、ヴォルフガングが神童としてパリで再び持てはやされるのではないかという誤った想像に陥り続けた。
もちろん幼い日のモーツァルトは、神童として唯一無二であり、さらにいえば神童という枠組すら超越していた。彼は音楽界の日常に組み入れられるような存在ではなく、また自らをそうした日常生活から遠ざけておく必要性さえ感じていなかった。だが3度目のパリ滞在にあたって、モーツァルトは既に成長した若者に育っていた。活発な多種多様の音楽シーンが展開されており、ヨーロッパ全土からの音楽家を惹きつけてやまないパリ。そこでは、目覚ましい活動で人々の注目を浴び、成功を手に入れられる可能性がいくらでも存在したのである。
いっぽうそのような都市において、モーツァルトの母は息子に対し、何の助けにもならなかった。父親はザルツブルクからアドヴァイスの手紙をあれこれ出したものの、いかんせんパリ音楽界での実体験が欠けているために、非現実的なものに終始した。というわけで息子のヴォルフガングとしては、自分自身で道を切り開かなければならなかった。そして彼は、驚くべき器用さと成果を引っさげ、往々にして父親が望むのとは明らかに別の方法でそれを成し遂げていったのである。
具体的には、モーツァルトは様々な注文主から作曲の依頼を受けたのだが、これは当時の音楽商法の世界でも最新鋭の、きわめて斬新なやり方だった。だからこそ、彼は自分のおこなっていることを父親に逐一報告しなかったのである。逆に言えばそうした態度が誤解を招き、後に余計な噂を生む原因となったのだろう。
いずれにせよ、パリ滞在中のモーツァルトが依頼を受けて書いた作品のいくつかは、残念ながら散逸するか、未完のままで残されることとなった。現存する完成作品としては、「フルートとハープのための協奏曲」、あるいは今日「パリ交響曲」と呼ばれている交響曲がモーツァルト・ファンにとっては代表格だろうが、数から言えばあまりにも少ないというのが現実である。
では、消失あるいは未完に終わった作品はといえば、グランドオペラ用のバレエ作品2つ、協奏交響曲1曲、ピアノ曲、室内楽曲、演奏会用の宗教曲が挙げられる。中でも、例えば協奏交響曲と宗教曲は失われ、バレエ音楽の2つ目についてはスケッチのまま放置されてしまった。また現存しているバレエ音楽(「レ・プティ・リアン」)については、筋書が散逸したためバレエとして上演できず、さりとて演奏会でも滅多に取り上げられることはない。
だがモーツァルトがパリに滞在していた半年の間で、「レ・プティ・リアン」は7度にわたって上演され、「パリ交響曲」もさほど間をおかずに2度も上演されているという事実は頭にとめておきたい。つまり彼はこの街で熱心に働き、巧みなプレゼンテーションをおこない、たしかな成功を収めたのである。
パリ時代のモーツァルトは、音楽家や同業者の仲間からも一目置かれた存在だった。例えば彼は高名なカストラート歌手の一人、フェルナンド・テンドゥッチとともに、10日間にわたってパリ近郊にある ルイ・ドゥ・ノアイユ公の館に滞在した。あるいは王家の軍楽隊のトランペット奏者だったフランソワ・エーナは、モーツァルトが母を亡くした後何くれとなく彼に寄り添い、埋葬にも立ち会った。この2つの例を見ただけでも、巷間伝えられる状況とはまったく異なり、モーツァルトがパリで人々からいかに厚遇され、活動を展開していたかがよく分かる。
モーツァルトは自分の将来についても賢明な考えを巡らし、自分の名声を保つための方策を色々と考えた。そこで彼は音楽家仲間だけではなく、名だたる音楽愛好家や音楽通、あるいは音楽支援者とも付き合いを深めていったのである。
このことについても、モーツァルトは父親にさほど多くを報告していない。報告したところで無意味だと考えたわけであって、たとえ私たちでさえそのような人々の名前を列挙した手紙を見せられれば、うんざりしてしまうのが落ちだろう。父親にとっても同じこと。彼もまた、そうした人々の名前を知っているはずがなく、また彼らがどのような地位にあるかも皆目見当つかなかったにちがいない。
いっぽうフリードリヒ・メルヒオール男爵のように、父親自身が非常に買っており、是非付き合うようにと息子に勧めたにもかかわらず、結局当の父親が想像したほどの影響力もなく助けにもならなかった人物が存在したことも、原因の一つといえる。じっさいモーツァルトは、自分自身を失望させたという理由から、その後男爵と絶交してしまったほどなのだ。
いずれにしても、モーツァルトはパリで芸術的に様々に重要な体験をした。既に8歳と10歳の折りにこの街を訪れた際も多くの影響や印象を受け、それらを吸収したわけだが、3度目の滞在ではより意識的にパリの音楽様式を学び、自家薬籠中のものとしていった。
いわゆる「パリ交響曲」K. 297もその1つで、当時のフランスで流行っていた最新の嗜好を見事取り入れた、紛うことなきフランス風交響曲となっている。しかも単に表面的な効果にとどまらず、それまでモーツァルトが書いてきた交響曲と比べ、作曲技法上様々な点で大きく異なっている点が特徴だ。彼はこの作品を通じて、フランス風の音楽語法が使えるだけでなく、それを完璧に自分のものとし、フランス風に作曲できるのだという事実をパリの聴衆に示したのだった。
また「協奏交響曲」に関してだが、これは当時パリとロンドンでしか人気がなかったジャンルだった。それゆえ、パリで作られたこのジャンルのための作品が失われてしまったのは、かえすがえすも残念である。なお「フルートとハープのための協奏曲」も、いわばパリ限定の一曲だった。これら2つの楽器が一番愛されていた街こそパリであって、パリの聴衆しかこの組み合わせには興味を持ちえなかったというのがその理由。モーツァルトにとって幸運だったのは、彼がこのような協奏曲に関しても作曲の才能があることを証明できたということだろう。結果、パリの人々はモーツァルトのことを、ヨーロッパ中からこの街に流れてきた音楽家の一人ではなく、フランス風の嗜好に見事合致した曲を書ける重要人物として受け止めたのだった。
ところでモーツァルトにとって3度目となるパリ滞在に関し、伝記的な事実を2つ記しておこう。まったくといってよいほど知られていないが、充分驚くべき内容である。
1つ目は、パリの音楽出版業界におけるモーツァルトの受容について。1778年当時のパリは、ヨーロッパの他の都市がおよそ太刀打ちできないほどたくさんの音楽出版社が存在した。しかもモーツァルトがパリを出発してから程なくして、彼の作品が次々と出版され始め、1780年代には驚くほど多くの数に達したのである。何しろこの頃モーツァルトの作品が継続的に出版されている二大都市はといえばウィーンとパリであり、出版数を見れば双方は互角か、場合によってはパリがウィーンを凌ぐ場合もあったほどだった。
じっさい1780年代、他のヨーロッパの都市では(ウィーン近郊の都市でさえ)モーツァルト作品がそこまでは出版されていなかった。そのことを顧みるに、パリの音楽出版社にとってモーツァルトがいかに重要な作曲家であり、自社のレパートリー充実のために欠くべからざる存在であったかがよく分かるだろう。それにしてもなぜそのような状況に至ったかと言えば、1778年にパリに滞在したモーツァルトが、この街の楽譜出版社と積極的にコンタクトをとり、その関係をさらに発展させた結果、出版社の側も彼の作品を認めるようになったからに他ならない。
しかもモーツァルトは、ザルツブルクで出版した自作の版権をパリの出版社に売ろうと画策し、一部の作品については実際に売り渡しさえした。もちろんそうした作品の全てがパリっ子の好みに合うものではなかったが、そこまでモーツァルトと出版社の関係は密であり、まただからこそ両者の関係は長続きしたのだろう。
ただし、モーツァルトと出版社との間に交わされた手紙のやり取りは、いくつかの例外を除いてすべて失われてしまっている。モーツァルトと家族との手紙は多くが現存している状況に比べると、たしかにその数はごくわずかだ。
だからといって、モーツァルトがパリの楽譜出版社に一切手紙を書かなかったかのように考えるのは早計というもの。むしろパリの出版社から多くのモーツァルト作品が出されたという事実を顧みるに、両者の間で手紙のやりとりが交わされたのは火を見るより明らかだ。さらに言えば、こうした仕事上の関係が育まれるにあたっては、双方が個人的に知り合い、交流を深めることが大前提であり、それを可能にしたのは唯一1778年のパリ滞在に他ならなかった。
2つ目の事実は、いわゆる「パリ交響曲」K. 297とパリ滞在に関するものである。モーツァルトはこの交響曲を、いわゆる「コンセール・スピリテュエル」なる演奏会シリーズのために作った。コンセール・スピリテュエルとは、パリ中心部のテュイルリー王宮内部の演奏会用広間で開催されていた公開演奏会のことで、当時この街におけるもっとも重要な音楽的催しといっても過言ではなかった。
1778年パリに滞在した際、モーツァルトはこのコンセール・スピリテュエルの「作曲家」という称号とポストを得、やがてザルツブルクへと帰って行った。そして帰郷後も、彼はこの称号を得た者の務めとして、コンセール・スピリテュエルのために新作を書き続けていったのである。
ちなみに彼がコンセール・スピリテュエルの作曲家だったのは、1783年あるいは84年まで。1784年には、コンセール・スピリテュエル自体がこのポストを廃止したのが理由である。それまでは演奏会の内容を多彩なものにすべく、コンセール・スピリテュエルは様々な作曲家を専属作曲家として抱えていたのだが、1785年以降はあらゆる作曲家が新作を発表できるよう方針を変更したためだった。
いずれにせよモーツァルトはパリからザルツブルクに戻った後も、ザルツブルクの人々の好みや期待に必ずしも合致しないような作品を書いた。たとえば、パリ旅行から帰った直後に書かれた交響曲第32番ト長調K. 318の場合。なぜここまで「非ザルツブルク的」で、あえてパリの伝統を汲んだ作品をモーツァルトは書いたのだろう?彼はパリで学んだ成果を、ザルツブルクの人々に披露したかったのか?
いや、けっしてそうではあるまい。そもそもザルツブルクの宮廷では、誰一人としてパリの伝統に興味がなかった。また親しい友人たちですら、3楽章からなる伝統的なフランス風の序曲形式の交響曲を前に、首を横に振るのが落ちだったろう。実際のところは、ザルツブルクに帰ってきてから後もモーツァルトがパリのコンセール・スピリテュエルのために作曲をしなければならなかったというのが事の真相であり、そう考えればなるほど合点が行く。
1つ交響曲第32番に限らない。1782年にモーツァルトは自作の「ハフナー・セレナード」を交響曲第35番ニ長調K. 385(いわゆる「ハフナー交響曲」)に改作しているが、これはモーツァルトとパリの関係を考える時、きわめて重要な出来事に他ならない。当交響曲の初演こそウィーンでおこなわれたのだが、初版の楽譜はウィーンとパリでほぼ同時に出版されたからである。ということは、この作品がコンセール・スピリテュエルの演奏会でも取り上げられたことは間違いない。さらにいえば、いくつもの楽章から成るセレナーデを4楽章形式の交響曲にまとめ直すという独自のアイディアは、おそらくコンセール・スピリテュエルの演奏会に新曲を書くという義務を果たすために生まれたものなのだろう。
たしかに元々パリで流行っていた交響曲は3楽章形式のものだったが、この頃になると徐々に4楽章形式のものも浸透しつつあった。ヨゼフ・ハイドンが作った4楽章形式の交響曲が、この街で受け容れられていったのがその理由である。
いずれにせよ「ハフナー交響曲」もまた、1778年におこなわれたパリ旅行の賜物なのであり、この旅行なしに生まれることはなかった。少なくとも現在モーツァルト研究者の中で、この考え方に異論を唱える者は誰もいるまい。
モーツァルトは1778年のパリ滞在を通じ、「パリ風」に作曲することを学んだ。「パリ交響曲」K. 297はもちろんのこと、彼はパリの旅から戻った後もパリっ子の嗜好を念頭に曲を作り続けた。しかも表面的にパリ風を気取るのではなく、パリでの経験を深化させ、作曲活動の糧にしていった点こそが重要である。
その一例がピアノのための変奏曲。このジャンルにはフランスで学んだ変奏技術の影響が至る所に現れており、メロディーを様々に変奏させてゆくという方法そのものがフランス滞在の成果を物語っている。じっさい1778年にモーツァルトがパリに行かなければ、このような形の作品が生まれることもなかっただろう。
モーツァルトとパリ。この小文を締めくくるにあたり、彼が世を去ってから後の時代のパリについても触れておこう。というのもモーツァルトが亡くなってからしばらくの間、彼が愛され、その名声が語り伝えられた大都市といえば、この街の存在を忘れるわけにはゆかないからである。
それが証拠にパリの少なからぬ出版社が、モーツァルトの作品を数多く出版し、オペラのスコアのいくつかについては初版の楽譜を発売しさえした。またパリっ子の好みに合わなそうな作品、もしくはフランスで理解されにくそうな作品(たとえば「魔笛」)については、編曲がおこなわれ世に出された。
こうしてモーツァルト作品に関する知識は、その人の教養を図る物差しとなっていった。さらにはフランスの作曲家たちにとって、モーツァルトを手本としようとする風潮さえ生まれた。もちろんそれは、モーツァルトの様式で作曲する云々という次元のはなしではなく、彼の音楽に具わった根本的な要素……明朗さ、明晰さ、音楽的な語法、楽器の用い方……を絶対的な理想として仰ぎ見ようというものだった。
じっさい後世のフランスの作曲家たちは、モーツァルトに対し様々な賛美の声を寄せている。そのうちの一人こそ、クロード・ドビュッシー。彼はモーツァルトを、自分にとっての音楽上の偉大な祖先であるとした上で、次のように述べた。「モーツァルトはあらゆる音楽家の中でももっとも純粋な存在だ。つまり彼は、音楽そのものなのである。」