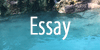文・池内 紀
第14回プログラムより(1993年8月発行)
ウィーン歌劇場から歩いて十分ばかりのところ、買い物客でにぎわうヴィーナー・ツァインの市場前の入口のところに奇妙な建物がある。
神殿のような白い四角いつくりで、正面に飾り文字、その上に金色の大きな球のようなものがのっている。ほぼ百年前に建てられた。出来た当時はその奇妙な形から「金のキャベツ館」などとからかわれた。
ウィーン分離派会館である。通称セツェシォーン。老朽化して、灰色にすすけていた。1986年、建築家アドルフ・クリシャニッツの指導のもとに全面的に修復されて、いまみるとおりの姿で甦った。世紀末ウィーンの生んだ美しい記念物にちがいない。
先に分離派の機関誌「ヴェル・サクルム」のことを述べておこう。
1898年1月に第1号が出た。
上にラテン語のタイトルがあって、鉢植えの若木が表紙絵。その木が青々と繁って木鉢のタガをはじきとばし、木片のあいだから根っこがのびている。右にアール・ヌーボー風の飾り文字で「オーストリア造型家連盟機関誌」とある。
若い画家たちが中心になり、身銭をきって出したものだった。ほんの数年で終ったあと、永らく忘れられていた。復刻版を出そうとして出版社がウィーンの図書館をさがしたところ、全冊そろっているところは一つもなかったという。
ほぼ七十年後に立派な本となったとき、あらためて人々はおどろいた。表紙絵、グラフィック・デザインにわたり、まるきり時代色を感じさせない。どれといわず、拭ったように新しいのだ。つい昨日生まれたばかりの雑誌のように、ういういしい感覚がみなぎっている。
ラテン語のタイトル「ヴェル・サクルム」は「聖なる春」といった意味。その名前、それにタガをはじきとばしてのびようとする若木の表紙からも、この雑誌が若い世代の手になることは推測がつく。前年の1897年、ウィーン分離派が誕生した。旧来の美術家集団はキュンストラーハウスを拠点にしていた。そこから分かれてグループをつくったので分離派とよばれた。「ヴェル・サクルム」は、その分離派の機関誌として創刊された。
グループのなかで比較的年長の画家グスタフ・クリムトを会長に選んだ。旧来の団体をとび出したからには、これまでのキュンストラーハウスは使えない。自分たちの展覧会場をもたなくてはならない。同年はやくもメンバーの一人ヨーゼフ・オルブリッヒの設計による分離派会館が完成した。ローマの神殿のような白々とした外観で、屋上は大きな金色の球がのっている。その球が「金のキャベツ」などとからかわれたのは、先に述べたとおり。
貧乏な画家集団に、こんなに手ぎわよく拠点ができたのは援助者がいたからだ。オーストリア帝国でも指おりの大富豪カール・ヴィトゲンシュタインが資金を出した。のちの哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの父親である。
ローマの神殿風のつくりにせよ、ラテン語の名前にせよ、理由あってのことだった。古代ローマの昔、退廃した皇帝都市に見切りをつけ、城壁の外に出て、自分たちの「永遠のローマ」を建てようとした「分離派市民」にちなんでいる。そういえば、こちらの分離派会館もまたウィーンの旧城壁のリング通りから「外へ出た」フリートリヒ通りに立っている。
誰が「聖なる春」と名付けたのか、いまとなってはわからない。メンバーの理論的支柱となった美術評論家ルートヴィヒ・ヘヴェジーによると、ウーラントの詩「聖春」から思いついたのだろうという。詩の一節に、つぎのようなくだりがある。
「君たちは新しい世界にまかれた種」であり、
「いま聖なる春を待っている……」
分離派会館の企画はヘヴェジーの選んだモットーがかかげられた。
「時代に、その芸術を
芸術に、その自由を」
分離派展の準備中のひとこまだろう。1枚の写真がのこっている。右手にクリムトがいる。古代ローマ人が身につけていたような、白いゆったりとしたガウンを着て椅子にすわっている。まわりの面々はめいめい勝手な姿勢をとっている。笑っている、横を向いている、片肘ついている、大きな腹を突き出して寝そべっている。そんなところからも、グループの性格がみてとれる。
分離派はいまも述べたように、古い流派に対抗した新しい運動をはじめたグループだった。しかし、彼らは何らかのイディオロギーを旗じるしにして、声高に新思想を言いだしたわけではない。これみよがしに旧世代を断罪したりもしなかった。「時代に、その芸術を。芸術に、その自由を」をモットーにしても、すこぶるおおらかな主張といっていい。そもそも、半ば旧世代に属するクリムトを会長にしたり、帝国きっての大富豪をパトロンにもつなどのこと自体、新しい運動にはいたって異質のことである。
ウィーン分離派のめざしたものをひとことにしていえば、―これはウィーン世紀末に共通した特徴だろうが―新しさよりもむしろ「綜合」の試みだった。創刊号の表紙の若木には、上の茂みの中に三つの空欄がみえる。そこにはあとから、絵画、彫刻、工芸をあらわす三つの紋章が入れられた。ちがったジャンルが重なり合って新しい芸術をつくり出すこと。そのためにも分離派展では、絵だけではなく、彫刻や工芸が同じ場所に展示された。会場設計そのものが、もう一つの芸術であり、そこには目にみえない空間デザイナーの強い意志が働いていた。
ウィーンの夕方。
カフェにやわらかい灯がともる。オペラ座の窓からシャンデリアの光が洩れ落ち、プログラム売りが制服に着かえるころ、酒場のテーブルにコップが並べられ、アコーデオン弾きがハンチングをかぶって出勤してくる。
そんな時刻、リンク通りからそれてフリートリヒ通りに入り、散策するとおもしろい。えんえんと長い市場のおおかたが店を閉めた。明りがついているのは安ビールを飲ませる居酒屋。中ほどの右手、アン・デア・ウィーン劇場の少し先に壁面いっぱい桃色の装飾をもった建物がみえる。となり合って黄金の飾りのあるもう一つの建物。世紀末ウィーンの代表的な建築家オトー・ヴァグナーの作ったものだ。ヴァグナーの青写真では界隈一体を同じような新建築が埋めるはずだったが、ウィーンによくあるとおり、「未完成」で終った。
分離派会館が白い照明のなかで、白亜の船のように浮いてみえる。上の黄金の玉は人工の月だろう。たいていの人は気づかないが、横手に小さな入口があって、「カフェ・ゼツェシオン」の標識。建築家のクリシャニッツが修復の際につくったもので、白で統一したブロック式の壁と白い丸いテーブル。壁面に口をあいて、まっ赤な窓や、まっ黒な飾り棚。その前衛的な色と形は、あきらかにこの世紀の産物であり、現代という「もう一つの世紀末」の申し子にちがいない。顔をくっつけるようにして話しこんでいる仲間がいる。一人ポツンと本を読んでいる女性。なにやらしきりに書きものをしている老紳士。
ウィーンの世紀末は時代とともに消え失せたわけではない。「聖なる春」はスタイルを変え、色どりを取り代えて、何度でも甦る。それは文化モード的ではなく、むしろ文化の質と関係している。
これは軽くて重い文化だ。その重さは多民族のるつぼであった千年の歴史のかさなりに根をもっている。軽さは享楽のかたちをとって、四分の三拍子のリズムにあわせて歌いならされてきた。ここでは哲学者が詩人のような散文で書き、ノラクラ者が意味深い観察の記録をのこし、町の歯医者にチェロを奏かせるとプロ以上にうまいのだ。
いつも「聖なる春」であって、夏の盛りや、秋の実りに立ちいたらない。この軽さは、実をいうと、タダものではないのである。
池内 紀(1940~2019)
1965年東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。神戸大学助教授、東京都立大学教授を経て、85年東京大学文学部教授、96年退官。以後、文筆業、翻訳家として幅広く活躍しており、当音楽祭のプログラム冊子へは、第12回「ロマン派音楽・こぼればなし」、第23回「ウィーン昔ばなし」、第24回「影絵の世界」など多数寄稿。