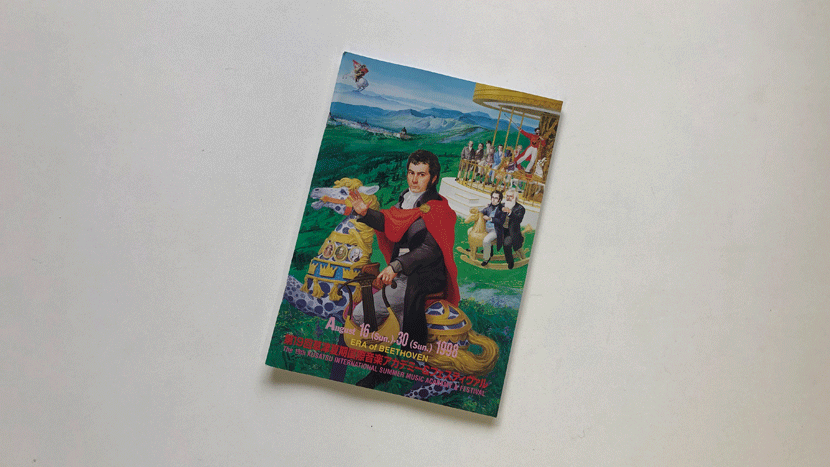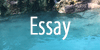文・西原 稔
第19回プログラムより(1998年発行)
ベートーヴェンの生まれた1770年は様々な意味でまさにヨーロッパ社会の変革期であった。ここではとくに音楽面での出来事を中心に論じながら、ベートーヴェンがどのような時代に生きたのかを取り上げてみることにしたい。
1770年前後は、音楽活動を支える社会環境が大きく変貌しつつあった時代であった。啓蒙主義の浸透によって、これまでのバロック時代の精神構造が急変していった。すでに1730年代から始まっていた啓蒙主義の運動は、単に精神的な運動だけではなく、同時に経済構造の変革とも呼応していた。宮廷社会を軸とした社会から次第に都市を軸とした社会に変化するにつれて、やがて宮廷そのものも変貌を余儀なくされる。
とくにドイツ語圏では宮廷文化に占める音楽の比重は高かった。宮廷楽団の他にオペラ劇場と歌手を抱え、歳入の限られていた宮廷にあってはその財政的な負担は想像以上のものであった。すでに18世紀前半には財政的に逼迫して来ていたが、ドイツ語圏の宮廷では宮廷としてのステイタスの確立と財政の二重の課題に直面せざるを得なくなっていた。さらに国際政治状況の緊張は軍事費の増大をも余儀なくし、ますます宮廷経済は逼迫の度合いを強くしていく。ウィーンの宮廷を例にとると、1730年では11万フロリンを音楽のために費やしていたが、しかしこのハプスブルク家の宮廷は極端な財政逼迫と、その後頻発する継承戦争や領士を巡る戦争、そしてあのナポレオン戦争によってもはや音楽に資金を投入できる状況にはなかった。その結果としてマリア・テレジア、さらにヨーゼフ二世の代になると予算の削減のために宮廷劇場を国民劇場の名前でその運営を民間に委ねるほか、宮廷楽団の年金捻出のために、「貧民と孤児のための演奏会」など楽団活動のいわゆる民営化を推し進め、さらに他の諸都市に先駆けて民間の劇場の建設を推奨して、音楽活動を維持するための宮廷の負担を軽減していった。ハプスブルク家のウィーンはさらに、ナポレオン戦争によってさらに戦費の捻出を迫られていく。ナポレオンのウィーン侵攻は、厳密にいえばフランスとオーストリアの戦争ではなくて、ハプスブルク家との戦争であった。この侵攻に対抗するためにハブスブルク家は戦費の調達のために、ハンガリーを含む有力貴族に領地を提供する代わりに、そこから資金を調達したのである。その結果、ウィーンには奇妙な現象が起こる。つまり、先の貧民と孤児の演奏会はウィーンの公開演奏会の先駆けとなり、劇場の民営化は劇場都市ウィーンを現出せしめ、モーツァルトの「魔笛」の初演の舞台ともなった庶民のための劇場活動が促進された。さらにナポレオン戦争によって領地を得た有力貴族たちは、ハプスブルク家の窮乏を横目に豊かな財力を蓄え、その結果としてベートーヴェンやシューベルトらの芸術家のパトロンとして音楽文化の促進に貢献することになったのである。
このような宮廷文化の変貌は各地で起こり、それぞれの事情で宮廷は音楽活動の主役の地位を降りなければならなくなっていった。たとえばシュトゥットガルトの宮廷では、カール・オイゲンは、ヴェルサイユ宮殿の栄華を夢見て、音楽に金に糸目を付けない支出を行った。当時、楽長クラスでも年収が500、600ターラー程度であったところに、1754年にニコロ・ヨメッリを3000ターラーで迎え、1767年には給料を倍の6000ターラーに増額している。マンハイムの宮廷も同様で、超一流の楽団を構えることを夢見たカール・テオドールも破格の給料で楽団員を募ったのである。モーツァルトもその高給ぶりに羨望を隠さず、ここでの就職を強く希望したことはよく知られている。彼は手紙にこのように書いている。「まったく話にならないひどい歌手やずぶの初心者でも600グルデン(フロリン)はもらえるのです。オーケストラの楽団もいい給料がもらえ、指揮者のカンビヒさんは1800、コンサート・マスターのフレンツルさんは1400、楽長のホルツバウアーさんは3000グルデンももらうのです。」ちなみにモーツァルトがザルツブルクの大司教のもとでもらっていた給料は、彼がそこを辞める時で450グルデンであった。こうした宮廷楽団への支出はそのほかの宮廷でも同様であった。しかし、その結果は目に見えていた。社会が大きく変貌しつつある時代にあって音楽にのみこれほどの資金をつぎ込むことはもはや許されるものではなかった。シュトゥットガルトではオイゲンは、彼の統治するヴュルテンブルク公国の予算の10分の1を音楽につぎ込んだ結果、国家財産は極端に逼迫して、オペラの解散と宮廷楽団員の解雇をせざるを得なくなる。イギリスの音楽史で、資料収集のためにこの地を訪れたチャールズ・バーニーは、「音楽はこの国にとっては有害である」と日記にしたためており、この国の半分は俳優とヴァイオリン弾きと兵隊で、残りの半分は乞食であると述べている。そのほか、ドレスデンの宮廷やハイドンの勤務したエステルハージの宮廷も、ディッタースドルフの務めたヨハニスベルクでも、楽団の解散が相次ぐ。
ベートーヴェンがボンで音楽活動を始めた時はまさに宮廷文化が最後の華を咲かせていた時期であった。ボンの宮廷でも、モーツァルトを楽長に迎えて、ヨーロッパ一の宮廷楽団にすべくさまざまな団員をスカウトして小都市にもかかわらず、きわめて質の高い楽団を維持していた。少年ベートーヴェンもその団員に名前をつらねていた。しかし、ほどなく財政的な理由で楽団を維持することは困難になる。1792年、ベートーヴェンがウィーンに出た時期のヨーロッパはフランス革命に象徴される大きな歴史の節目を迎えていたのである。その当時のウィーンは、上にも述べたようにハプスブルク家の宮廷は音楽的なパトロンの役割を担うことはできなかった。それに代わって、裕福な都市貴族がパトロンとして芸術を擁護していたのである。
ベートーヴェンの生きた1770年から1827年は歴史における大きな変換期を体験していた。1770年代は宮廷文化が最後の華を咲かせていた時代であると同時に、いくつかの出来事が同時に進行していた。バッハの再評価の運動が起こったのもこのころで、フォルケルがバッハの作品収集に乗り出した。また今日のピアノに連なる楽器の技術革新がさかんになるのもこのころからである。ベートーヴェンはこれらふたつの運動と密接な関連をもっていた。1801年より現在のペータース社よりバッハの鍵盤音楽集が刊行されるが、ベートーヴェンは真っ先に全巻予約を行っただけではなく、その後の創作でバッハから強い影響を受けるのである。ピアノについては、ベートーヴェンのとくにピアノ・ソナタの創作の歩みは、ピアノの改良の歴史であったと言ってもよいほどに、ピアノの技術革新にベートーヴェンは大いに貢献したのである。
この時期のヨーロッパの諸都市はどうであったのであろうか。ロンドンは音楽の消費都市として大衆文化が開花していたが、重要なのはピアノの技術革新がこの都市を中心に始まったことであった。ブロードウッド社他によってウィーン・アクションとは異なるイギリス・アクションという機構が確立され、それはやがてベートーヴェンの創作にも変革をもたらした。そしてイギリス・アクションは19世紀後半になるとウィーン・アクションを圧倒していくのである。一方、パリではフランス革命の影響で、革命式典音楽のための巨大編成の合唱付きの吹奏楽がさかんになり、ゴセックやメユールといった作曲家が1000名以上の編成の作品を作曲した。さらにケルビーニやグレトリー、ボワエルデューらのフランス・オペラが新しい伝統を形成していた。ウィーンではフランスおよび革命を連想させるものは厳しく検視されていたはずであるが、実際にはこれまでのジングシュピールに飽きて、もっと劇構成のしっかりとしたオペラを求めていたウィーンでは、フランスのオペラの翻訳物が舞台の主役をしめていた。ベートーヴェンがブーイ原作のフランス語の戯曲にオペラを作曲したのもその影響であり、今日、彼の交響曲にもメユールなどのフランスの作曲家の影響が指摘されている。
ベートーヴェンがウィーンに移り住んだ1792年からウィーン会議が始まった1815年頃までが彼の創作活動の大きな時期になるが、これはほぼ、フランス革命からナポレオン戦争終結までの時期に当たっている。この時期のベートーヴェンの作品はほとんどすべて貴族に献呈されているが、これは芸術を擁護する貴族が金銭的な援助を行ったことと関連がある。この時期はロッシーニがウィーンでも人気を博したのみならず、イギリスで活躍した作曲家でピアノ製造業や出版業などを手掛ける実業家でもあったクレメンティが、事業の拡大をねらってベートーヴェンと面識をもち、イギリスでの彼の作品の出版交渉を行い、イギリス・アクションのメーカーのエラールやプロードウッドなどが、ベートーヴェンに楽器を献呈して自社の楽器の拡販を図るなど、とくに経済面で活況を呈していた。
しかし1815年以降になると、ウィーンの経済は非常なインフレに見舞われ、すべてが一変するのである。ウィーンは経済不振によって、度重なる通貨切り下げを余儀なくされ、かつてパトロンとして名を連ねた貴族はたちまち零落していった。ベートーヴェンの年金の出資者のキンスキーやロプコヴィッツもまた同様であった。ベートーヴェンが作品出版の交渉相手をマインツのショットなどウィーン外の出版社に求めたのもそういう理由によっていた。ベートーヴェンが孤高の後期様式に入っていったのはこのような時代背景をもっていたのである。
西原 稔(1952年~)
東京藝術大学大学院博士課程満期修了。現在、桐朋学園大学音楽学部教授。18,19世紀を主対象に音楽社会史や音楽思想史を専攻。「音楽家の社会史」(音楽之友社)、「ピアノの誕生」(講談社)、「ブラームス」(音楽の友社)などの著書のほかに、共著・共編では「ベートーヴェン事典」(東京書籍)などもある。作曲家+ピアノ作品演奏法などの講演会も多数行っている。