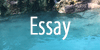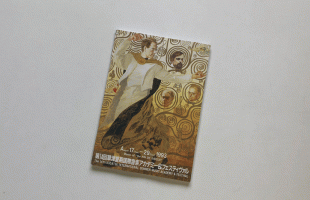文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:小宮正安
第39回プログラムより(2018年発行)
500年来というもの、自然は作曲家に様々な霊感を与えてきた。だが、自然から生じる要素をどのように音楽に当てはめればよいのか?まず思い浮かぶのは、自然の音や響きそのものであって、動物の鳴き声、鳥のさえずり、風や波の音、小川のせせらぎ、雷の轟きといったところ。そこから時代が徐々に下って来ると、自然から喚起される雰囲気、例えば寒さに震えたり、暑さで消耗したりといった状態が描写されるようになってゆく。日の出、日の入り、夜の静けさといったものもまた然り。いわゆる、音による絵画に他ならない。
こうした音による絵画の中で、今日もっとも有名なのが、アントニオ・ヴィヴァルディによる4つのヴァイオリン協奏曲「四季」である。ちなみにこの作品は、たしかにヴェネツィア出身のヴィヴァルディによって作曲されてはいるものの、とあるオーストリアの人間が曲を依頼したことから生まれたという経緯がある。ヴィヴァルディは当作品を、ヴェンツェル・モルツィン伯爵と彼の宮廷楽団に捧げているのだが、この伯爵はウィーンの皇帝カール6世に仕える人物だった。またこの協奏曲の直接的後継といえるのが、ヨーゼフ・ハイドンのオラトリオ『四季』である。じっさいこのオラトリオでは、テキストに自然現象(例えば雷)や自然の音(例えば動物の鳴き声)が出てくる箇所で、音楽がそれらを模倣しているのだ。「雷雨」は、モーツァルトもコントルダンス KV.534に取り入れている。また動物の鳴き声という点では、やはりハイドンによるオラトリオ『天地創造』が、『四季』以上の模倣を聴かせてくれる。それどころかわざわざこの箇所にだけ、ハイドンはオーケストラの楽器の1つとして、コントラファゴットを用いているのだ。ちなみにコントラファゴットは、古典派のオーケストラではほとんど用いられなかった楽器である。
また、音楽に特にしばしばとり入れられたのが自然からの挨拶であり、とりわけ鳥の鳴き声である。たとえばすぐに思い浮かぶところでは、ハイドンの弦楽四重奏曲「ひばり」(Hob. III:63) やオルガン小曲「うずらの鳴き声」(Hob. XIX:8)、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ作品79の第1楽章におけるかっこうの鳴き声、モーツァルトのミサ曲「雀」KV. 220 のベネディクトゥスにおける雀のさえずりといったところ。特に最後の例の場合、神を讃えるテキストの箇所で鳥の鳴き声が模倣されるのは古くからの伝統であり、鳥たちも神を讃えるという旧約聖書の詩篇の記述に拠る。他の動物を用いて自然が描写されているケースについても、4つの例を挙げるにとどめておこう。まずは、ハイドンの弦楽四重奏曲「蛙」(Hob. III:49)と、シューベルトのピアノ五重奏曲「ます」D 667である。シューベルトはこの曲の第4楽章に自らの歌曲「ます」の旋律を引用し、ハイドンは蛙特有の鳴き声を彷彿させる主題を用いていることから、こうした呼び名が付けられた。ハイドンの交響曲「めんどり」(Hob. I:83) の第1楽章や、交響曲「熊」(Hob. I:82)の最終楽章にも同様のことが当てはまり、後者では聴き手が熊の踊りを想像できるという次第。
ただしここでは、話題をもう一度四季に戻そう。四季というものは、作曲家たちにしばしば霊感を与え……少なくとも彼らの多くの作品が四季と関係している。例えばモーツァルトのピアノ・ソナタKV.331 やベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ作品24がそうで、それらは後に「春」と呼ばれるようになった。対照的に作曲者本人が名付けた例が、ローベルト・シューマンによる交響曲第1番で、文字通り「春の交響曲」と命名されている。あるいはヨハン・シュトラウス2世はワルツ「春の声」、彼の父親であるヨハン・シュトラウス1世はワルツ「真夏の夜」、弟のヨーゼフ・シュトラウスはポルカ・シュネル「冬の喜び」を作曲している。
田舎における生活、つまり自然の中における生活も、音楽によって模倣された。もっとも有名で秀逸な例を2つ挙げるならば、ハイドンの「四季」、ベートーヴェンの交響曲第6番となるだろう。それらに耳を傾ければ、自然の中における、あるいは自然を相手にした、田舎の人々の労働や喜びや気苦労を共に体験できる。しかも単なる雰囲気の描写ではなく、まるでそこに居合わせているかのような、ほとんどルポルタージュといってもよいような特徴がそれらには具わっている。田舎の生活の雰囲気を描いたダンス音楽としては、ヨーゼフ・シュトラウスの「オーストリアの村つばめ」を挙げておこう。
多くの作曲家が、自然の中で何を体験できるかを聴き手に思い起こさせてくれる。例えばフランツ・シューベルトの「さすらいびと幻想曲」では彼の歌曲「さすらいびと」が引用されているが、幻想曲を聴くと歌曲のテキストが頭に浮かぶという仕掛けだ。モーツァルトのドイツ舞曲「そり遊び」KV.605が描くのは、冬の楽しみ。馬が引くそりに乗って、様々な風景の中を走ってゆくのだが、普通は馬の頭に鈴が付けられており、その澄んだ響きが乗っている人々を幸せにし、逆にそりの前を横切ったり、橇の真正面から来たりするものに対しては警告音となるという次第である。(音楽による「そり遊び」は、モーツァルトの父親のレオポルトも作曲している)。このように自然の体験を音楽に拠って表現しようという行為を、多くの作曲家がおこなっている。狩の体験を音楽で描く際に、狩猟ホルンを関連付けるのもそのひとつだ。モーツァルトの弦楽四重奏「狩」KV.458、ハイドンの交響曲「狩」(Hob. I:73)はその一例であり、あるいはやはりハイドンの交響曲(Hob. I:31)は「狩人の見張り小屋」とか「ホルン信号」などと呼ばれている。
自然の雰囲気を克明に描写するという特別な形式のひとつとしては、一日の移り変わりを音楽で表現するという方法がある。それが特に成功しているのが、ハイドンの交響曲 (Hob. I:6, 7 ,8)の三部作であって、それぞれに「朝」「昼」「晩」と呼ばれている。他にもこのように、一日の推移に寄せる感情を表現した作品は多数存在しているが、必ずしも一日のうちに何が起きたかという具体的な事例を描いている訳ではない。そうした意味では、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ「月光」も、こうした自然の雰囲気の描写のひとつに属している。また、ヨハネス・ブラームスのヴァイオリン・ソナタ作品78も、雰囲気を描写した形式の典型といえよう。というのも当作品の最終楽章に、彼は自作の「雨の歌」作品 53-3を引用しているからだ。雨は、太陽や霧や嵐や雷のように自然現象である。ただしブラームスはそれを、音による絵画のように表現するのではなく、雨の気分と関連付けており、それはそもそも彼の歌曲のテキストに記されているものなのである。となると、シューベルトやブラームスをはじめ、数えきれないほどの歌曲も、自然そのものや自然に関係する事柄に捧げられていることが分かる。ただしその数はあまりにも多いため、ここではその例を挙げる余裕すらないほどだ。
クリスマスを迎えると、キリスト教の教会では、イエス・キリストがベツレヘムの馬小屋で生まれた際、焚火を囲んで羊の群れの番をしていた羊飼いたちが天使からキリストの降誕を知らされた、という聖書の記事が取り上げられる。またそれを人々の脳裏に刻んでもらうべく、様々な工夫が重ねられてきた。そのひとつが、音楽でこの出来事を分かり易くかつ深く、人々に伝えるというもの。それが、いわゆるパストラール音楽(パストラーレ)を生み出すこととなった。パストラールとは、ラテン語のパストール、つまり上で説明したような、聖書で重要な役割を果たしている羊飼に由来する。そこから転じて羊飼の音楽ということになり、羊飼いの音楽のメロディが、羊飼いの楽器(とりわけ様々な種類の角笛)さらには田舎の民俗音楽に登場する楽器を用いて演奏される、ということが一般化していった。またこうした『自然楽器』は限られた音しか出せず、そのため非常に特殊な旋律しか奏でられないという事情を抱えていることから、パストラール音楽の旋律も非常に特徴的なものとなった。しかも、ベツレヘムの馬小屋に眠る生まれたばかりのキリストを前に、羊飼が音楽を奏でている情景を模倣しようと思うと、いきおい子守唄のリズムが用いられることとなり、それが独特の旋律と相まって、パストラール音楽が形作られていった。
なおこうしたパストラール音楽は、古典派の時代に絶頂を迎える。とりわけ、ヨーゼフ・ハイドンおよびミヒャエル・ハイドンの兄弟のパストラール音楽は見逃せない。モーツァルトもパストラール音楽をしばしば用い、またベートーヴェンは交響曲第6番(『田園交響曲』というタイトルが与えられている)の最終楽章「牧人の歌」に、パストラール音楽の要素を反映させている。
逆に言えばパストラール音楽は、単にクリスマスの出来事を思い出す行為とのみ結びついているわけではなく、ほぼ田舎の生活の象徴という意味合いで発展を遂げた。つまり、この手の旋律やハーモニーを聴けば、自然の中の生活に立ち会ったような気分に浸れるようになったのである。そこでは羊飼や農民が、自然音列しか出せない楽器を演奏しているわけだが、作曲家たちはそんな単純かつ特徴的なメロディに手を加えて行ったのだった。またパストラール音楽の響きとしては、民俗音楽の楽器の典型ともいえるバグパイプが往々にしてイメージされており、そこでは完全五度のみで低音の伴奏が付けられた。
ところでパストラール音楽に関して、もう少し細かだが、重要な情報も付け加えておこう。イタリアにもパストラール音楽は存在したのだが、そこでは子守唄のような3拍子とは異なる別のリズム、つまり6/8拍子に基づく付点リズムが用いられている。なぜか?それはイタリアの民俗音楽における子守唄がこのリズムに則っているためであり、そうしたリズムに基づいて馬小屋のイエスを前にした羊飼いたちの音楽を人々が想像したためである。まさにイタリアの民俗音楽が生んだ独特のパストラール音楽というわけで、バッハやヘンデルも―ドイツやオーストリアではなく―イタリアのパストラール音楽を引き継いだのだった。
田舎の楽器や、それらによって奏でられる典型的な旋律を取り入れるのは、何もパストラール音楽に限られた手法ではない。既に述べたように、例えば自然の中での狩を思い起こさせる曲においても、狩猟ホルンが典型的な旋律を奏でる。モーツァルトの「ポストホルン・セレナード」も、郵便馬車の御者がポストホルンを独特の旋律で吹いて、馬車が村に着いたことを知らせるという、自然豊かな風景を思い起こさせてくれる。コントルダンスKV.611のトリオでは、モーツァルトはライアーの音を真似ている。ライアーは民俗音楽で用いられる楽器の1つであり、その軋むような音色ゆえ、戸外でのみ、つまり自然の中でのみ用いられるのが特徴だ。田園的なテーマを選んだ例と言えば、カール・チェルニーのピアノ曲「ロンド・パストラーレ」もそうで、そこでもいかにも田舎の楽器が奏でそうな旋律が基となっている。
田舎のダンス音楽、つまり器楽による民俗音楽は、弦楽器によって演奏される場合が多かった。なお弦楽器は、自然音での演奏になる管楽器に比べて音域が広く、それゆえダンス音楽も音域が広い。それでも、田舎の人々のダンス音楽には、特定の伝統というものが具わっており、主題の型や、また当然のことながらダンスの形式によって、様々に異なる特徴的なリズムが聴かれる。そしてこのような田舎のダンス音楽は、いわゆるウィーン古典派の夥しい作品の中に現れることとなった。
ただし今日の我々にとっては、どの部分が実際のダンス音楽から引用され、どの部分に作曲者自身のアレンジが加えられているのかを聴き分けることは難しい。というのも、それらは様式化されている場合が多く、元々のダンス音楽よりも少しだけ洗練され、工夫が施されているいっぽうで、きわめて単純かつ粗野である場合も少なくないからだ。とまれこれらの田舎のダンス音楽は―オリジナルのままか、あるいは作曲者のアイディアが加えられたり様式化されたりしているかということを別にして―、聴き手を自然の中へと誘ってくれる。田舎でおこなわれる屋外のダンス、あるいは悪天候や冬には屋内で踊られるダンス。つまるところ、田舎の生活は、自然の中での生活そのものなのだ。
これとよく似ているのが、民謡である。田舎のダンス音楽と同様、民謡もまた既にバロック時代から芸術音楽に引用されていた。ただしバロック音楽において、こうした手法は珍しかったのだが、古典派音楽では非常にしばしば用いられるようになってゆく。結果、やはりどこまでがオリジナルの引用で、どこからが作曲家のアイディアを反映したメロディなのかを判断するのが難しくなってしまったのも事実である。もちろん交響曲、弦楽四重奏、ピアノ曲で民謡が登場するケースの全てではないにせよ、 それがオリジナルか、そうでないのかを判別できる可能性もまたきわめてまれなのだ。だがここでも、引用がおこなわれたのか、あるいは民謡風に曲が作られたのかという問題を一旦棚上げするならば、これらのメロディが私たちを田舎の生活や自然に誘ってくれることもたしかなのである。
ハプスブルク家は、様々な国々を支配下に置いて巨大な帝国を形作っていた。それゆえ、ウィーン古典派の芸術音楽に登場する民俗舞踊や民謡には、ドイツ語圏にかぎらず、ハンガリー、ボヘミア、クロアチア等々で生まれたものが数多く存在する。そのことに注意して作品を聴けば、なるほど、その違いが分かって来るだろう。特に「他と違う」のがハンガリーの民俗音楽。理由としては、ハンガリーの風景が他の地域と特に異なっており、それがこの地域における音楽に新たな形式を与える理由になったから…、と説明できよう。山岳地域では、平地におけるのとはまた異なる音楽が奏でられ、それがまったく異なる民族の個性を育むものだが、ハンガリーではそれが特にはっきりと現れている。たしかに「ハンガリー風」と題されたハイドンの弦楽四重奏曲の最終楽章に耳を傾ければ、ハンガリーの風景が思い起こされる。ブラームスのハンガリー舞曲や、彼の盟友ヨーゼフ・ヨアヒムのヴァイオリン協奏曲「ハンガリー風」もまた然りである。
数えきれないほどの作品が、自然に囲まれた場所や地域を特定して書かれている。そうした例が豊富に見られるのが、シュトラウス・ファミリーのダンス音楽の場合。「ウィーンの森の物語」や「クラプフェンの森で」だけを例に挙げても、そこにはウィーン近郊の森や、ウィーンの森にある特別の場所の雰囲気が、ダンスの形式を通じて、音楽による輝かしい記念碑のように立ち現われている。温泉や山や湖や河川も、音楽の中に取り入れられた。じっさい、ヨハン・シュトラウス2世のワルツ「美しく青きドナウ」が、ベドルジヒ・スメタナの交響詩「モルダウ」ほど具体的に自然を描写していないとしても、もしもドナウ河なかりせばこのワルツも存在しなかったにちがいない。またドナウ河を具体的にイメージして作られた曲には、当時のハンガリー、現在のルーマニアのティミショアラに生まれたヨシフ・イヴァノヴィチのワルツ「ドナウ河のさざなみ」もある。
様々な種類の花々を幾つものピアノ曲に顕現させたのが、イグナーツ・アスマイアー。彼はシューベルトのサークルの一員であり、後にウィーンの宮廷楽団楽長に就任した人物だ。例えば彼の作品は、ローベルト・シューマンが「ミルテの花」作品25で表現したような手法を用いている。そして多種多様な花々を、それらの名前や特徴によって描こうとする姿勢は、たとえばヨハン・シュトラウス2世が作ったワルツ「南国のばら」や「レモンの花咲くところ」、ポルカ・マズルカ「ひまわり」や、ヨーゼフ・シュトラウスによるワルツ「秋のばら」、さらにはヨハン・シュトラウス1世のワルツ「野の花々」「刺のないばら」「ばらの葉」に現れている。
自然を描くにあたっての別の方法は、オペラの世界に存在する。モーツァルトの「魔笛」1つをとっただけでも、そこには小鳥売りが登場し、危険な大蛇が殺され、太陽が歌い、夜の女王が主役を務め、さらなる別の主人公2人が火の試練と水の試練を受けて自分たちの決意を証明する、といった次第。小鳥売りが他にも登場するのは、カール・ツェラーが作った、その名も『小鳥売り』という題名のオペレッタで、その中のもっとも有名なナンバーではバラが扱われ、オーストリアのティロルの風景が歌われる(『ティロルのバラを贈る時』)。そうでなくてもオペレッタには、この小文のテーマと関係する作品がたくさんある。ヨハン・シュトラウス2世の「くるまば草」では、全ての場面が森の中だけで展開するようになっている。森というものが自然の風景として重要だったからという理由だが、だからといってそれがどこの森か、ということが具体的に示されることはない。いっぽう筋書きの中で、上部オーストリアのヴォルフガング湖が具体的な舞台として用いられているのが、ラルフ・ベナツキーのオペレッタ『白馬亭にて』。これを観れば、例えば雨が降る様子ひとつをとっても、この湖特有の自然現象が分かるというものだ。何しろ当作品のもっとも有名なナンバーのひとつは、ヴォルフガング湖の自然や人々や風景を歌い上げたものなのだから(『ザルツカンマーグートでは、みんな愉しくすごせるね』)。
以上、自然が音楽の中にどのように現れたのかについて、そうした音楽に関する選りすぐりの例を取り上げながら、ごく手短に概説してみた。だがこの小文が読者の皆様の中に、そうした作品に親しみたいという好奇心を喚起し、あるいは既に曲そのものをご存じの場合でも、自然に対する親近感という視点から、それらの作品により親しみを持っていただける機会となれば幸いである。もちろん今回扱ったのは、有名な作曲家の例がほとんどだった。もしも、今日あまり顧みられる機会のない彼らの同時代人のことを話題にできたのであれば、取り上げた例の数がさらに増えたことは、火を見るより明らかである。