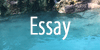文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:小宮正安
第35回プログラムより(2014年発行)
リヒャルト・シュトラウスは、様々な場所で活躍した人物である。ざっと眺めただけでも、まずは21歳の折、マイニンゲンの公爵の宮廷音楽監督に就任した。マイニンゲンはドイツ中部のチューリンゲン地方の小さな街で、当時は公爵が居城を構えた上、宮廷楽団が設けられていた。それは例えば、モーツァルトの時代におけるザルツブルクや、ハイドンの時代におけるエステルハーザやウィーンやアイゼンシュタットのような光景であり、前者においては大司教が、後者においてはエステルハージ侯爵家が支配していたのである。(なおマイニンゲンに次いで、シュトラウスはミュンヒェン、ワイマール、ベルリンでこれも宮廷管弦楽団を指揮するようになる。宮廷管弦楽団とは、その土地々々の君主の宮廷によって組織運営され、宮廷の名声を高める重要任務を負ったオーケストラのことだ。)
マイニンゲン時代、シュトラウスはきわめて幸福な環境にあったが、およそ1年以上そこに留まった後、ミュンヒェン宮廷管弦楽団の第3楽長として彼の地へと赴いた。地位的に見ればワイマールよりもおよそ格下のポストだが、ミュンヒェンは彼の故郷だったこともあり、このような決断をしたのだろう。またそうした事情も手伝って、3年後にワイマールから宮廷楽長として招聘を受けると、それを受諾。1894年には再びミュンヒェンへ、今度は宮廷楽長として返り咲くも、1898年にはベルリンの宮廷楽長となり、10年後には音楽総監督の地位にまで登り詰め、ベルリンのオペラに責任を負う立場となった。しかも音楽総監督となった1908年、シュトラウスはバイエルン南部のガルミッシュに新築になったばかりの邸宅へと引っ越す。というのも彼はベルリンを仕事の中心としてはいたものの、到底この街に住む気にはなれなかったからだ。実際1917年にはベルリン芸術大学の作曲科の教授となるも、3年後にこの職を辞することとなった。何しろ1918年から19年にかけて、シュトラウスはベルリンでの仕事を少しずつ減らしていったほどなのだから。
1918年、シュトラウスは妻とともにウィーンへ引っ越し、1919年にはフランツ・シャルクとともにウィーン国立歌劇場の監督を務めはじめる。そして1924年にこのポストを辞めた後、彼が何か決まった地位に就くことはもはやなくなった。
当時シュトラウスは60歳。無理に専任のポストを手に入れなくても、そこかしこから客演要請の声がかかり、さらに彼自身作曲活動に充分な時間を割きたいと望むようになっていた。逆に言えば驚くべきことに、彼はこの年齢に至るまで、指揮活動を十二分におこなうだけでなく、管理職も兼ねた地位で仕事をし続けていたのである。というのもシュトラウス曰く、豊かな市民にふさわしい生活を送るためには、作曲活動だけでは金銭的に足りず、そのため生活の多くを指揮活動に割かなければならなかった。またそれゆえに、作曲活動に少しでも専念できる時間を確保すべく、日常業務のかたわら充分な休暇がとれるよう気を付け、とりわけベルリン時代にはこれまで以上の充分な休暇を取得できるよう努めたのだった。
1922年、シュトラウスはウィーンに大邸宅を建て始め、1924年そこへ引っ越した。それはガルミッシュの邸宅よりも大きく、一家の本拠地となるはずだった。ところがこれが完成したまさにその年、シュトラウスはウィーン国立歌劇場の監督を辞めてしまう。それでも彼としては新築になったウィーンの邸宅に住みたいと願い、家族ともども1年の大半はここに、そして夏だけガルミッシュに行くというスタイルがとられることとなった。「ガルミッシュは元々、夏の住まいでした」とシュトラウスの孫も語っているほどである。
ところが第二次世界大戦が勃発し、ウィーンでも空爆の危機が迫り始めた1944年から45年にかけて、シュトラウス一家はガルミッシュに引き上げ、この地で敗戦を知ることとなる。そして敗戦後間もなくシュトラウスはスイスへ赴くが、敗戦処理で進駐してきた連合国側の命令により、ドイツやオーストリアに入国することができなくなってしまった。1947年、度重なる働きかけの結果、オーストリアに進駐している4ヵ国による許可を得ることが必要という条件付きで、シュトラウスにオーストリアの国籍が与えられた。当時のウィーンは激しい空爆に晒された直後であり、食糧や日用品もほとんど手に入らないような状況だったにもかかわらず、シュトラウスはそこまでしてこの街へ戻りたかったのである。ところがウィーンの邸宅は進駐軍によって召し上げられ、他の人間が住んでいた。しかもそれをシュトラウスに返却するというような話は、ついぞ出なかった。
1949年、シュトラウスに対し、スイスを出てドイツのガルミッシュへ入国してもよいとの許可が出された。そしてこの年の6月11日、85歳の誕生日を迎えた彼は、ウィーン楽友協会から祝福のメッセージをもらった返礼として、ウィーンで「敬愛する会員の皆様に、間もなくお目にかかり直接ご挨拶したい」としたためている。だがその機会は、もはや巡って来なかった。1949年9月8日、シュトラウスはガルミッシュで息を引き取った。
*
シュトラウスとウィーンとの関係は、彼が1924年にこの街に邸宅を完成させる遥か以前の青年時代にまで遡り、しかもそれはきわめて緊密で多岐にわたっていた。以下、ウィーンにおける彼の多彩な芸術活動を眺めて行こう。
1882年12月、18歳のシュトラウスは初めてウィーンへとやって来た。彼は街を観光し、宮廷歌劇場(国立歌劇場の前身)やブルク劇場を訪ねた。さらにウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(以下「ウィーン・フィル」と略)の演奏会にも足を運び、オーケストラの素晴らしさに感嘆して次のように述べた。「僕たちのところでもこのように素晴らしい演奏ができるのならば、演奏会もより優れたものとなるだろうに。」つまり彼はウィーンへやって来ることで、ウィーン・フィルと、地元のミュンヒェンの宮廷管弦楽団とを比較できるようになったのである。
なお比較ということでいえば、シュトラウスは当初、こと管楽器に関してはウィーンの音色を気に入らなかった。というのも彼の父親はミュンヒェンの宮廷楽団のホルン奏者だったこともあり、シュトラウス自身、ミュンヒェンの管楽器の音色に慣れ親しんでいたからである。その点ウィーンでは、ホルンやトランペットの楽器そのものからして異なっており、それが大きな違和感を覚える原因となったのだろう。逆に後年になると、シュトラウスはこのウィーン独特の響きをきわめて高く評価するようになったのだが。
1892年、ウィーン・フィルはシュトラウスの交響詩『ドン・ファン』を初めて取り上げ、これをきっかけに、折に触れて彼の交響詩を演奏することとなった。ただしオーケストラや聴衆はシュトラウスに好意的だったものの、一部の新聞の批評は否定的だった。そうした状況の中、シュトラウスを積極的に評価したのが、ヨハネス・ブラームスだったのである。ちなみにブラームスは、マイニンゲン時代のシュトラウスと既に個人的に知り合っていた。
1902年、シュトラウスのオペラ『火の消えた街』がウィーン宮廷歌劇場で上演される。これは、この劇場で彼のオペラが取り上げられた最初の出来事だった。
それから4年後の1906年8月17日、シュトラウスは初めてウィーン・フィルを指揮した。これはカール・ムックの代役であり、現在のザルツブルク・フェスティヴァル(通称ザルツブルク音楽祭)の先駆的存在であるザルツブルク音楽フェスティヴァルでの出来事だった。結果、オーケストラは彼の指揮に熱狂し、その後も演奏会を是非指揮してほしいと懇願。それに対し、シュトラウスはすぐに首を縦にふるようなことはせず、まずはギャラに関する条件を出した。ここからも分かるように、彼は常に商売熱心であり、しかも実利的で交渉上手だった。
1906年12月16日、シュトラウスは指揮者として、ウィーン楽友協会大ホールで開催されたウィーン・フィルの定期演奏会にも満を持してデビューする。そしてそれからというもの、ウィーンで、あるいは演奏ツアーで、彼はウィーン・フィルを合計98回も指揮したといわれており、指揮者とオーケストラの間に相思相愛の関係が築かれることとなった。1910年に故郷のミュンヒェンで「リヒャルト・シュトラウス・フェスティヴァル」が開かれた際にも、彼はわざわざウィーン・フィルを呼び寄せているほど。そしてウィーン・フィルはこのフェスティヴァルで主要なプログラムを担当し、シュトラウスの指揮で3回演奏会に出演した他、多くの室内楽の演奏会にも登場した。
なおこの演奏会に際し、シュトラウスはウィーンでリハーサルをおこなったのだが、その間を縫って1910年6月19日、ウィーン宮廷歌劇場でも初めて指揮をしている。そしてその時の演目に選ばれたのが、自作の『エレクトラ』だった。
シュトラウスとウィーン・フィルとの共同作業における更なるハイライトはというと、例えば1923年におこなわれた南アメリカ・ツアーが挙げられるだろう。また1924年にウィーン・フィル主催による記念すべき第1回目の舞踏会のために、彼はオープニング用のファンファーレを作曲し、それ以来、楽友協会大ホールでおこなわれるウィーン・フィル舞踏会では毎年この曲が響いている。
70歳の誕生日には、ウィーン・フィルの名誉会員に指名された。75歳と80歳の誕生日を迎えた1939年と1944年には、家族や親戚の間でおこなわれるような親しい雰囲気の祝賀パーティがウィーン・フィルによって催され、楽友協会大ホールではシュトラウスが指揮をして2度にわたる演奏会が開かれた。なお80歳記念の演奏会では、シュトラウスとウィーン・フィルによる数々の録音の中でも最後となる録音がおこなわれ、これがコンサートホールにおける両者の最後の共演となった。というのもこれに続き、やはりシュトラウスの80歳を祝し、ウィーン国立歌劇場でおこなわれた彼の自作オペラ『ナクソス島のアリアドネ』の上演が、シュトラウスと彼の愛するオーケストラ(同歌劇場のオーケストラ団員が自主運営している演奏会用のオーケストラがウィーン・フィルである)の本当に最後の共演機会となってしまったからである。
いずれにしても、シュトラウスがいかにウィーン・フィルに満足していたかは、彼がオーケストラの創立100周年を祝った手紙にはっきりと記されている。その中で彼は、自分がこのオーケストラの弦楽器の音色に惚れ込んでいると述べた後、次のように書いた。「それに勝るとも劣らず私が評価しているのが、管楽器の弱音、ハープの輝かしさ、常に優雅さを失わない打楽器です。皆さんの芸術的な功績は、世界中の聴衆に熱狂を巻き起こし、称賛の的となっています。皆さんに対する賛辞を、私はごく手短に2つの文章にまとめてみたいと思います。『ウィーン・フィルを指揮した者だけが知っている。あなた方が何者であるかということを!』。しかしこれは、私たちだけの秘密です。何しろ皆さんは私のことをよく分かっていらっしゃるのですから。この祝いの場でも、また譜面台を前に演奏をする時も!」
シュトラウスは、ウィーン・フィルの団員の幾人かとは個人的な友達付き合いもおこなった。名コンサートマスターとして知られるアルノルト・ロゼ、彼よりはるかに若い年代のヴォルフガング・シュナイダーハン、チェリストのフリードリヒ・ブクスバウム、ヴァイオリニストのヴァルター・ヴェラー1世やオットー・シュトラッサー……。
さらにティンパニストのハンス・シュネラーは、シュトラウスの自伝的作品ともいえる「家庭交響曲」で、シュトラウスが楽譜に書いていたのとは異なる演奏を即興的におこなった。しかもシュトラウスはそれをいたく気に入り、この箇所をいつもそのように叩いてくれるようシュネラーに頼んだのである。というわけで、シュトラウスのこのきわめて個人的な作品がウィーンで演奏される場合は、他の場所で演奏される時と異なって、作曲者当人のお墨付きをもらったいわばウィーン・フィル・バージョンを今もなお聴くことができるのである。
*
ブラームスやグスタフ・マーラー同様、シュトラウスも自作をウィーンで初演することには、きわめて慎重だった。そのため、ウィーンをはじめとする重要都市で新作を取り上げる以前に、どこか別の街でいわば試演をおこなうのが常だったのである。
例えばオペラを初演するにあたっては、ドレスデンは理想的な都市だった。そこには優れたオペラハウスがある一方で、音楽の中心地という点ではウィーンとはまったく比べ物にならず、世界中の音楽界に圧倒的な影響力を持つような評論家もいなかったからである。聴衆にしても、ウィーンのように仮借ない批判をする者は少なかった。
というわけで、シュトラウスがウィーンで初演した舞台作品と言えば、オペラ『影のない女』とバレエ『泡立ちクリーム』の2曲だけだった(前者は1919年、後者は1924年)。『ナクソス島のアリアドネ』については、1912年にシュトゥットガルトで初演がおこなわれた後、シュトラウスは改訂の必要性を痛感し、1916年に第2稿にあたる改訂版のウィーン初演を敢行した。さらにウィーン国立歌劇場のためのベートーヴェンとモーツァルト作品の編曲版(『アテネの廃墟』と『イドメネオ』)の初演も、ここでおこなっている。
シュトラウスにとってもっとも重要なオペラの台本作家も、ウィーンの人間だった。具体的には、フーゴー・フォン・ホーフマンスタール、シュテファン・ツヴァイク、ヨーゼフ・グレゴールであり、彼らはウィーン人ならではの人生観を台本の中に織り込んだ。またそれゆえに、シュトラウス自身、芸術的にも人間的にも、彼らへの理解を深めることができたのである。
同じことは、やはりウィーン人だった演出家のマックス・ラインハルトやロタール・ヴァラーシュタイン、天才的な舞台美術家のアルフレード・ロラーにも当てはまる。ウィーン出身だったり、ウィーン在住だったりした音楽家ともシュトラウスは親しく交際し、彼らを高く評価していた。マーラー、エミール・ニコラウス・フォン・レズニチェク、ヴィルヘルム・キーンツル、フェーリクス・ワインガルトナー。フランツ・シャルク(ただし彼とは後に仲違いすることとなる)、クレメンス・クラウス、ルドルフ・モラール、カール・ベーム、イゾルデ・アールグリム。またここでは名前を記すスペースがないが、男性女性を問わず数々の歌手たち……。
シュトラウスが、若き日のアルノルト・シェーンベルクを賛美し、支援したことも忘れてはならない。もっとも後年、シェーンベルクがさらなる進歩を遂げ新たな道を歩んでゆくにおよび、シュトラウスは彼に対して失望するようになったのだが。
シュトラウスはウィーンで、文学者のサークルとも親しく付き合い、何人もの文学者と友達になった。その中には、ホーフマンスタール、ツヴァイク、グレゴールのように、直接彼のオペラのために台本を書いた者もいたが、それ以外にもアルトゥール・シュニッツラー、リヒャルト・ベーア・ホフマン、アントン・ヴィルドガンスといった著名人も含まれていた。またルートヴィヒ・カルパート、マックス・グラーフ、ハインリヒ・クラリックといった音楽評論家と交友を結んだのも注目に値する。なおこのように評論家と音楽家が親しく交際した例といえば、カルパートとマーラー、あるいはエドゥアルト・ハンスリックとブラームスを思い出される向きも多いだろう。
さらにウィーンでの交友関係は、芸術家以外にも、例えば大工場経営者として有名だったマンフレード・フォン・マウトナー=マルクホーフにまでおよんでいる。シュトラウスはマウトナー=マルクホーフを心から理解しており、また非常に信頼していた。実際1947年、マウトナー=マルクホーフはシュトラウスがオーストリア国籍を獲得したいと願った際、それが迅速に滞りなくゆくよう取り計らったのである。
なおマウトナー=マルクホーフの妻は、ウィーンの画家として名高いレオポルト・クーペルヴィーザーの子孫に当たる。クーペルヴィーザーといえば、1826年に彼が結婚式を挙げるに当たって、フランツ・シューベルトがピアノのためのワルツを贈った人物だ。ちなみにこのワルツ、未出版のままマウトナー=マルクホーフ家に保存されていた。それをシュトラウスはマウトナー=マルクホーフ夫妻の家で演奏し、1943年にはこの作品が失われることのないよう、またあらゆる人が目にすることができるよう、楽譜を書き写す作業までおこなったのである。これぞウィーンの音楽的な伝統における素晴らしい一例であって、シュトラウスがシューベルトの作品のプロモーターとしても活躍したことを物語るエピソードといえよう。
ウィーンの音楽的な伝統は、作曲家としてのシュトラウスにもインスピレーションを与え続けた。「もしも何かよいメロディが欲しくなった時には、よくシューベルトの歌曲を1ダースほど弾いてみることにしている。」このようにシュトラウスは述べている。
もちろんシュトラウスの場合、シューベルト作品のメロディをそのまま引っ張って来るのではなく、シューベルトがメロディを考えつくにあたっての秘密を丹念に追い、シューベルトが用いたのと同じ技術の上に、独自のメロディを創造してゆくのだった。これもシュトラウス曰く、彼はどこか遠くからシューベルトのことを考えるのではなく、シューベルトをひたすら「慕い、演奏し、口ずさみ、感嘆」していたのである。
シュトラウスはモーツァルトについても、その「劇場に関する偉大な本能」について感嘆の念を隠さなかった。当然のことながらシュトラウス自身、オペラを書くにあたっては台本作家と協議を重ね、どのようにして道を切り拓いてゆけばよいかを探り、そのための努力を惜しまなかった人物である。その彼が、モーツァルトこそ「人間が生きてゆく上での感情をあらゆる角度から描きつくし」「人間の感情の表現をあますところなく」音楽的に表現できた究極の存在である、と述べているのだ。
ベートーヴェンに関しても、彼がオペラ『フィデリオ』を作曲する際、台本の成立に積極的に関わったという経緯を、シュトラウスは積極的に参考にした。そしてモーツァルトやベートーヴェンがおこなったように、ホーフマンスタールやツヴァイクやグレゴールが台本を作製してゆく過程において、シュトラウス自身、熱心にそれに関与していったのである。
有名な『〈ばらの騎士〉のワルツ』がヨーゼフ・シュトラウスのワルツを下敷にしているのも、けっして偶然ではない。シュトラウスが述べているように、それは意図的におこなわれたものだった。何しろ彼は、ヨーゼフの兄であるヨハン・シュトラウス2世と「個人的に会い、言葉を交わした」ことを生涯自慢にしていたほどなのである。またシュトラウス兄弟をそこまで尊敬するようになったのも、ウィーンの伝統の中に彼が身を置くようになったからこそだったからともいえる。「目にするもの耳にするもの、何でも複雑に難しく考えようとする時代のただなかにあって、ヨハン・シュトラウスの天賦の才能は、森羅万象を汲み上げて創造できる能力に満ちていた。彼はまさに、原初的な閃きに溢れた最後の人物の1人なのだ。原初的で、根源的で、メロディ以前のもの……まさに彼はそれらを具えていた。」
*
シュトラウスはウィーンで、この街に住む友人たちのホーフマンスタール、ラインハルト、バールらとともに、長年温めてきた構想についての議論を重ね、ついにそれを実現させた。これぞ先述したザルツブルク・フェスティヴァルの創設であり、同フェスティヴァルの事務所は当初はザルツブルクではなく、ウィーンの楽友協会会館の中に置かれていた。しかもフェスティヴァルの組織作りに当たっては、楽友協会の組織がモデルにされた。
この事実もまた、ウィーンにおけるシュトラウスを語る際には見逃せないものである。シュトラウスは生涯にわたってザルツブルク・フェスティヴァルのことを気にかけていたが、それもこれも楽友協会というウィーンに生まれ育った組織が手本になっていたのだから。
もちろんシュトラウスは、他にもウィーンの様々な音楽団体と密接な関係を持っていた。1914年にウィーン・コンツェルトハウスがオープンした際には、オルガンと管弦楽のための『祝典前奏曲』を作曲している。楽友協会会館も彼の指揮活動にとって、いわばホームグラウンドであり、生前からその作品が幾度となく上演された。また彼にとっては楽友協会資料館も重要な存在であった他、1916年には協会から名誉会員の称号を受けている。さらに1924年にはウィーン名誉市民の称号を得た他、晩年にオーストリア国籍を与えられたことは、ウィーンに根差し活動してきたことへの褒美ともいえる出来事だった。
実際シュトラウスは国籍授与の通知を前に、次のように述べている。「これは私にとって、魂の故郷であるオーストリアと愛すべきウィーンに長年携わってこられたことの特別な象徴なのだ。」