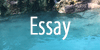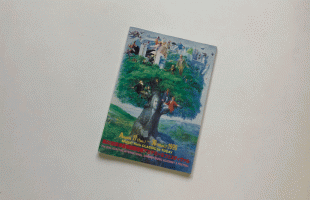文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:武石みどり
第27回プログラムより(2006年発行)
モーツァルトが生まれた1756年は、ちょうど18世紀の半ば、変転と変革の時代であった。バロック音楽の時代は過ぎ去ったが、われわれが「古典派音楽」と呼ぶ様式はまだ無かった。モーツァルトが子供の頃に接し、模倣し、さらに発展させた音楽は、今日暫定的に「前古典派」と呼ばれている。彼はこれを出発点として、古典派音楽への大きな一歩を踏み出した。モーツァルトは啓蒙主義を体験した。この精神史上の現象は、世界を初めて合理的に理解しようと努め、貴族と市民の差異を縮め、民主主義の原則を想起させ、教会や個人生活の中で宗教色を抑制し、新しい主観的な自意識へと人々を鼓舞するものであった。
モーツァルトは芸術家としても人間としても、まさに18世紀の申し子であった。同時代の人々のように感じたり考えたりし、同時代の芸術的、哲学的、政治的変化を特徴とし、それらを知識として受動的に取り入れたのではなく、彼にふさわしくまたその能力に応じて自らその形成に加わった。現代とはまったく異なる社会的、技術的、衛生的条件の下で、同時代の人々と同じように生活し、仕事をした。しかしそれでも彼は、我々にとって今なお非常に新しく生き生きとした存在なのである。
「モーツァルトと18世紀」というテーマについては、さまざまな側面から語ることができよう。しかしここでは、音楽だけに的を絞ることとする。モーツァルトを独立した現象として見ず、彼が生きた時代と同時代人の中に当てはめて見るのでなければ、我々は彼を理解することはできない。
モーツァルトは、バロック期のオーストリアの重要な作曲家ヨハン・ヨーゼフ・フックスが著した『グラドゥス・アド・パルナッスム』という音楽理論書で勉強した。彼は生涯にわたって、ヨハン・ゼバスティアン・バッハとゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルを偉大な先輩および啓発的な模範とみなしていた。彼は芸術が常に変化するものでなければならないこと、芸術家は常に新しいものを生み出すべきこと、そして聴衆が―少なくとも当時―常に新しいものを知りたがっていることを知っていた。しかし、新しいものにはすべて根源があるのであり、それは秘密にすべきでなく明らかにされるべきである。彼自身の新しい音楽の根源はバロック音楽にあった。それで彼はそこに学ぶものがあると考え、生涯にわたってバロック音楽と取り組んだ。バロック音楽の強い影響は、モーツァルトの晩年の作品『魔笛』や『レクイエム』にまで見ることができる。その一方で、モーツァルトは多くの作品の中にロマン主義を先取りするか、あるいはロマン主義のもたらす新しい流れを呼び込む役割を果たした。後世には、彼のヴァイオリン・ソナタに「ロマンティック・ソナタ」という呼び名が付けられたほどである。また、『魔笛』や『レクイエム』、およびそこに含まれるバロック風旋律とほとんど同時期に作曲されたクラリネット協奏曲は、古典的な構想のうちにロマン的な感覚を感じさせる。カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(特に器楽曲の細部において)やヨーゼフ・ハイドン(特に『天地創造』と『四季』の二つのオラトリオにおいて)と並んで、モーツァルトもロマン主義の多くを先取りした作曲家であった。
モーツァルトは同時に、古典派音楽の方向を指し示した人物でもあった。ヨーゼフ・ハイドンは晩年の多くの作品においてモーツァルトの足跡をたどっている。ベートーヴェンは、そのためにボンからウィーンに出てきたにもかかわらず、希望していたモーツァルトの指導を受けることができなかった。母親の命が危うくなったため、モーツァルトと会う前に故郷に帰らざるをえなかったのである。しかし彼はモーツァルトの作品を研究して学び、生涯尊敬し続けた。
モーツァルトはバロック音楽からのみならず、18世紀の他の作曲家たち、すなわち同時代の人々からも多くを学んだ。ヨーゼフ・ハイドンに献呈した6曲の弦楽四重奏曲の序文に、どのようにして(本当に優れた)弦楽四重奏曲を作曲するかを、ハイドンから初めて学んだと公言している。ハイドンとモーツァルトの重要な研究家、H.C.ロビンズ・ランドンは、モーツァルトのピアノ協奏曲ニ短調KV466の細部の多くがハイドンの交響曲第80番ニ短調にヒントを得て作られたことを指摘している。これ以外にも、ヨーゼフ・ハイドンがモーツァルトに影響を与えたことを示す例は多く、ハイドンはしばしばモーツァルトの携範であったと言うことができる。さらに、ヨーゼフ・ハイドンの弟であるミヒャエル・ハイドンに目を向けてみよう。この人物はザルツブルクの宮廷楽団でモーツァルトの同僚であり、親しい友人でもあった。モーツァルトのジュピター交響曲の最終楽章は、その直前に作曲されたミヒャエル・ハイドンの交響曲ハ長調の最終楽章をモデルとして作曲されている。また、モーツァルトの最初の弦楽五重奏曲は、やはり直前に作曲されたミヒャエル・ハイドンの弦楽五重奏曲を手本としていることが明白である。モーツァルトはミヒャエル・ハイドンの教会音楽をよく知り、そこから学ぶために、自らの手で楽譜を書き写した。オラトリオ『救われたベトゥーリア』では、ミヒャエル・ハイドンの合唱を文字通りそのまま用いている。これらすべて(そしてここでは列挙しつくせないその他の類似例すべて)は、決してモーツァルトの才能を否定するものではない。ここでわかるのは、モーツァルトという天才も自分を取り巻く芸術的環境から霊感を得ていたということであり、この環境に属していたのが、ヨーゼフ・ハイドンとミヒャエル・ハイドンという最も重要で優秀な作曲家たちだったのである。残念ながら現在ミヒャエル・ハイドンはあまり注目されていないが、今年は彼の没後200年に当たる。2009年に迎えるヨーゼフ・ハイドンの没後200年に向けては、すでにその名にふさわしい「ハイドン・イヤー」の準備が開始されている。
モーツァルトはまた、18世紀後半の他の作曲家たちからも影響を受けた。例えばハイドン兄弟の師にあたるヨハン・ゲオルク・ロイター、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの息子ヨハン・クリスティアン・バッハ、そして今日まったく名前の知られていない多くの作曲家たちである。「すべてを試し、よいものは残る」というのが、彼のモットーであった。しかし彼の場合、単に残すことが重要だったのではなく、よいものの上に積み上げ、他の作曲家の長所をさらに発展させることが重要なのであった。
モーツァルトには多くの競争相手がいた。彼と同じくらい高い賞賛を受けていた同時代人たちである。今回の草津国際音楽アカデミーでは、その競争相手の何人かの作品もコンサート・プログラムに取り上げられている。競争によって、モーツァルトはすばらしい成果へと駆り立てられた。彼は競争相手から刺激を受け、より優れた音楽を作ろうとした。だから競争があることに感謝し、競争相手は敵ではなかった。競争相手の作品の多くは、モーツァルトの作品よりも人気があった。もちろん同時代の聴衆がモーツァルトの才能を見逃すことはなく、彼は賞賛され有名になった。しかし彼の作品の多く―特に室内楽作品―は、聴衆にとっても演奏者にとっても複雑すぎて、理解しにくかった。これは今日の我々には理解しにくいことである。我々にはわかりにくいが、こうした作品では彼は18世紀の作曲様式と作曲技法をはるかに超越していた。
モーツァルトが生きた時代には、作曲家にまだ著作権もなくまた演奏の印税もなかった。作曲家はまだ職業ではなく、独奏者(ヴィルトゥオーソ)、音楽教師、楽長、歌手、または楽器奏者だった人々が、作曲もしたのであった。彼らは作曲で報酬を受けることを喜んだが、その後作品に対する権利はまったく持たなかった。(著作権と印税は、20世紀になって初めて一緒に導入された。リヒャルト・シュトラウスはこの権利規定のために集中的な努力をした。)このような状況から、なぜ見知らぬ人物がモーツァルトにレクイエムの作曲を注文できたのか、モーツァルトの死という事態が起こらず、ヴァルゼック伯爵がこのレクイエムを自分の作品として出版したとしてもなぜ罰せられないのかという理由を知ることができる。同時代の人々にとって、このような「名前の差し替え」は決して悪質なインチキではなかった。音楽の芸術作品は、品物と同様、買い求めたりプレゼントしたりできるものだったのである。モーツァルトはオラトリオ『救われたベトゥーリア』にミヒャエル・ハイドンの合唱曲を借用し、皆がこの合唱曲をモーツァルトの作品と考えた。その一方で彼は、ミヒャエル・ハイドンが病気で注文された曲を作曲できなかったとき、代わりにヴァイオリンとヴィオラのための二重奏を作曲している。モーツァルトは友の手助けをしたのであり、モーツァルトの作品はミヒャエル・ハイドンの作品として、曲の注文者であるヒエロニムス・コロレード大司教に渡された。これはモーツァルトの友情の証であり、彼は自分に作品への権利があるなどとまったく考えもしなかった。18世紀には(そして19世紀にも)、作曲家たちは芸術作品の創造者として、作品そのものへの賞賛を求め、作品の成功に幸福を感じ、作品が売れれば喜んだ。しかし作品を食べていくための資本とは考えなかったのである。
作品は品物として扱われたため、作曲家は自分の権利を自由に行使することはできず、一度市場に出れば作曲家自身の影響力は及ばなくなり、異なる楽器編成にしたり、短縮したり、異なる歌詞を付けたりという具合に、他の作曲家がいとも簡単に多くの編曲を生み出した。このような状況で、作品が間違って他の作曲家の作品とされることもあった。モーツァルトの名前は他の同時代の作曲家たちより売れ行きがよいため、意図的にモーツァルトの作とされたり、あるいはモーツァルト的な響きの曲だからモーツァルトの作品だろうという理由付けで、間違ってモーツァルトの名が付けられたりした。このようにして、他の作曲家の作品の作者と間違えられた18世紀の第一の作曲家はヨーゼフ・ハイドン、二番目はモーツァルトであった。
ここではモーツァルトの話に留まることにしよう。彼は、同時代の様式で作曲し、自分の周囲でよく用いられている語法で作曲し、そして自ら表現したいように作曲した。これはつまり、時代様式、地域様式、個人様式の組み合わせの中で作曲したということを意味する。これは18世紀において典型的なことであった。19世紀の半ば以降、時代様式がひとつではなくなり、さまざまな様式が横並びとなる。例えばブラームスがある時代様式の代表者である一方で、同時代のワーグナーとブルックナーは別の時代様式を代表しているのである。新しい作曲技法の工夫により時代様式はどんどん増え、今日ではもはや特定の時代様式というものがなくなり、個々の作曲家が多様な様式の中に自分の位置を見出している。聴衆の一人ひとりにとって、時代様式を認識するのは緊張を要する課題である。「これは古典派音楽のように聞こえる」とは言えるだろう。だが、「モーツァルト的な響きがする」と言うのはかなり難しい。もし今年の草津国際音楽アカデミーで演奏される種々の音楽がすべて「モーツァルト的な響きだ」と言うとすれば、それは間違いであろう。今回取り上げられる作品は、18世紀後半または1766年から1800年頃の音楽の響きをもつ。モーツァルトの音楽も同様である。しかし、他の優れた作曲家と同様に、モーツァルトにも個人的な様式的特徴がある。それをつかむことができれば、モーツァルトとそれ以外の作曲家とを簡単に聴き分けることができよう。
しかし、そのような判断は100パーセント確実なものではない。これまで示してきたように、モーツァルトは他の作曲家たちから学び、他の作曲家たちに影響を与え、またさらに発展させたため、そこに交差と混合が起こっているからである。モーツァルトが多く旅行したことも重要である。18世紀のでこぼこ道をがたがた揺れる馬車(夏は非常に暑く、冬は非常に寒い)で旅することは、なんと大変なことであっただろうか。今日の我々の感覚では、旅行のスピードも非常に遅かった。しかしその一方で、音楽家・作曲家のモーツァルトにとって旅行がいかに重要なものであったかを忘れてはならない。彼は異なる地域様式を知る機会を得た。少年モーツァルトはロンドンでピアノ協奏曲を初めて体験し、すぐに自分でも作曲してみた。フルートとハープのための協奏曲は、この二つの楽器の組み合わせが好まれたパリでしか成立しえないものであった。またパリでは、ザルツブルクやウィーン、イタリア等とはまったく異なる様式で交響曲が作曲された。モーツァルトは旅先で、つねにその地で期待されるような作品を作曲し、故郷に戻るとこれらの体験を組み合わせ、ザルツブルクまたはウィーンの聴衆を新しいもので驚かそうと努力した。聴衆も新鮮な驚きを求め、さまざまな地域様式を細部にわたって紹介し、組み合わせ、発展させたモーツァルトを賞賛した。17歳の時にはウィーンを訪問して新しい交響曲のタイプを知った。これはH.C.ロビンズ・ランドンがいみじくも「疾風怒涛交響曲」と名付けたタイプである。ザルツブルクに帰ると、モーツァルトはすぐに同じ様式で交響曲ト短調KV183を作曲し、ザルツブルクの人々を驚かせた。今日の我々には、ザルツブルクで知られていないウィーン特有のものがあり、それを体験するためにウィーンまで旅行しなければならないという状況は、想像もできない事態である。しかし18世紀には、このような地域格差は当然のことであった。おそらくモーツァルトは、数多くの旅行体験をもとに、比較的狭い地域内にも見られた多くの特殊性を乗り越え、より高い次元で統一した18世紀の最初の作曲家であったと言えよう。
18世紀においても、今日と同様、作曲家の間にはいわば専門の細分化がみられた。ある作曲家は歌劇場指揮者であったため主にオペラを作曲し、またある作曲家は教会の指揮者で主に教会音楽を作曲、またさらにピアノ教師をしていたために、主にピアノ曲や室内楽曲を作曲した者もいるという具合であった。宮廷に勤める楽長は、宮廷楽団のために主に管弦楽曲と室内楽を作曲しなければならなかった。このように、専門の細分化の例には枚挙に暇がない。18世紀の作曲家のうち、すべてのジャンルを作曲できた作曲家は数少なく、ましてやすべてのジャンルで成功した作曲家はもっと少なかった。ヨハン・ゼバスティアン・バッハはオペラを作曲しなかった。ヨーゼフ・ハイドンはすべての音楽ジャンルのために作曲したが、交響曲や室内楽の分野での名声に比べて、オペラ作曲家としてはあまり知られていない。ミヒャエル・ハイドンもまた、すべてのジャンルで傑作を作曲したにもかかわらず、主に教会音楽の作曲家として有名だった。ベートーヴェンでさえ(彼はもはや18世紀には属していないが)、オペラ作曲家としては問題があった。唯一のオペラ『フィデリオ』が成功するまで何度も作曲し直し、二曲目のオペラは書こうとしなかった。シューベルト、シューマン、ブラームス、マーラーの場合も、大成功を収められなかったジャンル、あるいはまったく魅力を感じず作曲しなかったジャンルが存在する。このように18世紀において典型的な専門性を、モーツァルトはあざやかに超越した。彼はその世代において、すべてのジャンルの作品を作曲し、すべてのジャンルで成功し有名になった唯一(音楽史全体においては、数少ない作曲家のうちの一人)の作曲家である。オペラと教会音楽、管弦楽曲、協奏曲、ピアノ曲、室内楽曲、オラトリオ、合唱曲、歌曲、カノン… どのジャンルにおいても彼の作品は知られている。およそ6歳年上のアントーニオ・サリエリと比較してみよう。サリエリはピアノ曲と室内楽曲を作曲していない。交響曲と協奏曲はごくわずかで、その作品はほとんど知られていない。しかし18世紀の作曲家たちの中で、作曲ジャンルに穴のあるサリエリが例外なのではなく、包括的な作品群を生み出したモーツァルトの方が例外なのである。
モーツァルトが人間としても芸術家としても18世紀の典型的代表者であったにもかかわらず、その伝記や作品の細部においては18世紀を超越していたことを認識するのは、なんと魅力的なことであろうか。彼はまた、死後も部分的に(またはまったく)忘れ去られてしまうことなく、常に演奏や作曲で取り上げられ、名を知られた最初の作曲家でもあった。18世紀の聴衆は、常に最新の音楽を聴きたがった。作曲家が亡くなると新しい作品は生まれないので、聴衆は多かれ少なかれ興味をもたなくなるのが普通であった。しかしモーツァルトの死以来、聴衆は昔のお気に入りの作品を繰り返し聴くことを好み始めた。モーツァルトに始まったこの展開が、結局今日の状況―未知の新しい音楽よりも、過去の有名なお気に入りの音楽を聴く方を好む―を導いたのである。草津夏期国際音楽アカデミーのプログラムは、有名で人気のあるモーツァルトの音楽と18世紀の知られざる音楽の組み合わせで聴衆に新鮮な驚きを与えている。これによって、聴衆がモーツァルトをもっとよく理解し、音楽の発展の中に彼を位置づけるとともに、モーツァルトの近くに位置しモーツァルトとよく似ている18世紀の知られざる作曲家の作品にも喜びを見出すことができれば、これはまさに大きな成果だと言えよう。