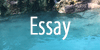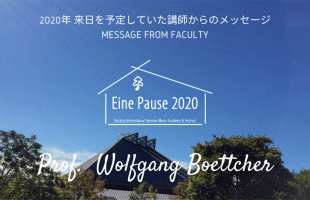文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:武石みどり
第30回プログラムより(2009年発行)
ローベルト・シューマンは、1841年に記したコンサート批評の中で、次のように記している。ハイドンは「いつも喜んで迎え入れる家族ぐるみの親しい友人のようなものだ。だが今の時代では、もはやそれほど関心を呼び起こす存在ではない。」この言葉は、当時の一般的な見解を述べたものである。すなわち、人々はハイドンのオラトリオ「天地創造」「四季」、数曲の後期の弦楽四重奏曲、そしてロンドン交響曲のうちの数曲だけは評価し、尊敬と畏敬の念をもって演奏もしたが、総じてハイドンを時代遅れと感じ、そこから学ぶものは何もないと考えていた。確かに三大巨匠の一人として崇めてはいたが、それは単に伝統だからであって心からの尊敬ではなかった。フーゴー・ヴォルフは40年後に、ハイドンの音楽は心地よいが年金生活者向けだとさえ記している。
もちろん例外もあった。アントン・ブルックナーとリヒャルト・ワーグナーは若い頃からハイドンの音楽に親しみ、ヨハネス・ブラームスは生涯にわたってハイドンを高く評価した。
ウィーン楽友協会アーカイヴはハイドンに関する資料を包括的に所蔵しており、19世紀の後半から、いわばハイドン資料の保護の拠点となって発展してきた。アーカイヴの所長であったカール・フェルディナント・ポール(1819~1887)は、1875年に初の現代的なハイドン伝を著した。この本は、今日に至るまで基本文献として通用している。その後継者オイゼビウス・マンディチェフスキ(1857~1929)は、ポールが下準備していたハイドン作品目録の作成に取り組み、またハイドン全集の出版に尽力した。この全集出版準備には、グスタフ・マーラーも加わっている。(マーラーは、当時ハイドンの重要性を認識していた数少ない人物のうちの一人であった。)だが、全集は数巻しか出版されず、マンディチェフスキの年齢的な限界により、作品目録も下準備の段階のままで終わった。ウィーン楽友協会の事務局長フーゴー・ボートシュティーバー(1845~1971)は、ポールのハイドン伝2巻に第3巻を補って完結させた。
ポールとマンディチェフスキの仕事を基礎として、ほとんど考えられないほどの労力をハイドン研究に注ぎ込んだのがアントニー・ファン・ホーボーケン(1887~1983)である。彼はウィーン楽友協会の理事で、1920年代からハイドン作品目録の作成に取り掛かり、実際にその仕事をやり遂げた。1957年から1978年にかけて出版された3巻の目録は、今日「ホーボーケン目録」として世界中に知られている。ホーボーケンは、本当にハイドンが作曲した作品と誤ってハイドンのものとされていた多くの作品とを初めて区別して示した。その分類にはほとんど間違いがなく、今日まで、新しい資料の発見によってわずかな修正が加えられているのみである。その中で最も重要な修正は、弦楽四重奏曲作品3(有名な「セレナード四重奏曲」を含む)がハイドンの作品ではなくローマン・ホーフシュテッターの作であること、また有名な「聖アントニウスのコラール」を含む6曲の管楽パルティータ[ディヴェルテイメント]が確実にハイドンの作ではないということである。この管楽パルティータは、ポールが友人ヨハネス・ブラームスと意見を交わした際に話題となった作品で、ブラームスは「聖アントニウスのコラール」を有名な「ハイドンの主題による変奏曲」の主題として用いた。しかし今日では、「ハイドンの主題による変奏曲」の主題がハイドンの作でないという事実が認識されている。このように学問の進歩によって幾つかの修正が加えられてはいるものの、総じてホーボーケンの業績は音楽学の発展にとって画期的な意義を有するものであった。
1932年はヨーゼフ・ハイドンの生誕200年であったが、演奏面でハイドンを掘り起こす特別なきっかけとはならず、数少ない演奏レパートリーの中から曲を選んで演奏する状態が続いた。しかし、この記念の年は学問的なきっかけの年となった。デンマークの音楽学者イェンス・ペーター・ラールセン(1902~1988)が、ハイドン作品の真偽の確定のために重要な資料批判研究を開始したのだ。また、ウィーン楽友協会の協力者カール・ガイリンガー(1899~1989)が、ハイドン伝を著した。これは、ハイドンの生涯と作品を初めて総体的に論じた重要な伝記であり、その後第4版まで出版された。さらにガイリンガーは、ハイドンの未出版作品の出版にも取り掛かった。
ナチスの軍隊がオーストリアに侵攻すると、ガイリンガーは1938年に移住した。彼はボストン大学の音楽学の教授となり、そこでH.C.ロビンズ・ランドン(1926~)という弟子を得た。ガイリンガーを通じてハイドン研究に情熱を抱いたランドンは、オーストリアに行ってハイドン研究に生涯を捧げる決心をした。そのような弟子を得たことは、ガイリンガーにとって幸運であった。第二次世界大戦が終わると、再び独立したオーストリアに入国するために、ランドンはアメリカ軍に入隊した。当時アメリカ人として個人では入国できなかったために、アメリカ占領軍の一員としてウィーンに入ったのである。そのような状況でハイドン研究に取り掛かるには、さまざまな苦労があったことであろう。その後、彼は退役してオーストリアに残った。
ランドンの大きな業績は、それまで演奏レパートリーとされていたわずかな作品ばかりでなく、できるだけ多くのハイドン作品をLPレコードに録音し、ラジオ番組のために収録し始めたことである。これによってより多くの作品がたくさんの人の耳に届くようになり、オーケストラや演奏家、コンサート興行主がハイドン作品を多くプログラムに取り上げるようになった。ランドンはレコード録音をウィーンで行い、ラジオの収録はロンドンのBBCで行った。また並行して、ハイドンの未出版作品の楽譜をできる限りすべて出版し、質の悪いエディションでしか出版されていなかった作品(編曲版や歪曲された版)の正確なエディションを出版する仕事に取り掛かった。これは途方も無い取り組みであった。彼はそのために調査すべきすべての図書館と音楽資料館を訪ね歩き、資料を調査・比較し、すでに消失したと考えられていた多くの作品を再発見した。ランドンが校訂した楽譜は、主にウニヴェルザール社とドブリンガー社から出版されている。例えば、今日ハイドンの交響曲を演奏する際、たいがいの場合はランドンが編纂した楽譜が譜面台の上に置かれる。室内楽作品の場合も同様である。
ランドンの編集・出版作業を通して、演奏家たちは初めて、これまでほとんど演奏されなかったハイドンの交響曲もすばらしい音楽であり、ハイドンが協奏曲の分野でも傑作を残していること、また弦楽四重奏曲ばかりでなくピアノ・トリオや種々の編成の室内楽でも優れた作品があることを知った。さらに加えて、ランドンが編纂した楽譜により、ハイドンが偉大なオペラ作曲家であることも初めて明らかとなった。ランドンの楽譜を用いて演奏した初期の著名な演奏家として、1950年頃にハイドンのミサ曲の初録音を指揮したハンス・ギレスベルガー、BBCで多くの初録音を指揮したサー・チャールズ・マッケラス、初めての交響曲全曲LP録音を指揮したエルンスト・メルツェンドルファー、二番目の交響曲全曲録音と初のオペラ全曲LP録音を成し遂げたアンタル・ドラーティが挙げられる。彼らは、まさに先駆的な業績を成し遂げた。またニコラウス・アーノンクールも―当時はコンツェントゥス・ムジクスの結成前で、まだ指揮者ではなかったが―、ランドンに資料の状況について情報を提供し、演奏習慣の問題について討論した。
こうした初期の録音は、多くの困難を伴う冒険的な仕事であったが、ランドンから人々へと伝播した情熱により困難も克服された。例えば特に問題となったのが、非常に高音域のホルンパートである。ロマン派音楽の常套的なホルンの用法に慣れきっていたホルン奏者たちは、ハイドンのホルンパートを演奏不能と考え、演奏に際してはまず新しい奏法を身につけなければならなかった。このようにハイドンを新しく鮮釈・演奏する冒険的事業について、ランドン自身、そして演奏に参加した音楽家たちが多くのエピソードを語っている。それはまさに、ハイドンの音楽を知り、その演奏解釈を学ぶ時代であった。
このパイオニア時代は、今日すでに遠い昔となっている。オリジナル楽器を用いる古楽アンサンブルにとって、ハイドンは今やレパートリーの中心である。しかしこうしたスペシャリストばかりでなく、日常的なコンサートにおいてもハイドンのあらゆる作品が至る所で聴かれるようになった。昨年、東京のサントリーホールにおけるウィーン・フィル・ウィークの演奏会で、リッカルド・ムーティがハイドンの交響曲第67番を指揮した。もちろんランドンの楽譜を用いてである。ムーティのような偉大な指揮者も、すでにロンドン交響曲(およびパリ交響曲)以外のハイドンの交響曲作品に関心を抱いていることを、まさに示した好例である。もちろん、なぜよりによって交響曲第67番なのかと疑問に思う聴衆もいたかもしれない。しかし演奏を聴けば、その理由は明らかである。第67番も傑作だからだ。ハイドンのオペラの声楽パートは信じられないほど難しいが、他とは比べ物にならないほどやりがいがあるため、偉大なスター歌手たちがCD録音に参加している。例えば、チェチーリア・バルトリがニコラウス・アーノンクールの指揮で録音した「アルミーダ」は、ベストセラーCDとなった。
今日、ハイドンの作曲ジャンルの全曲録音はもはや珍しいことではない。コンサートホールで何曲かを聞いた聴衆は、同じジャンルのハイドンの作品を全部知りたくなり、全集CDに手を出すこととなる。オペラ、交響曲、ミサ曲、弦楽四重奏曲の全集CDが幾つも存在する中で、さらにペーター・ヴェヒターの率いるアンサンブルがハイドンの弦楽三重奏曲[ディヴェルティメント]の全曲CDを、またディーター・フルーリーの率いるアンサンブルがフルートを含むピアノ三重奏曲のCDをカメラータからリリースした。さらにアントン・ホルツアプフェルとアンサンブル「ドルチェ・リゾナンツァ」によるハイドンのオルガン協奏曲の全曲CDも忘れてはならない。
誤ってハイドンの作品とされていたが、確実にそうではない楽曲に対しても、今日では以前とは異なる接し方がされている。どのような音楽であったからハイドンの作とされたのか、「偽の」ハイドンと「本物の」ハイドンを容易に聞き分けられる違いは何なのか、すなわち当時の一般様式とハイドンの個人様式がどのように異なっているのかという点に関心が寄せられているのだ。最近、ハイドンの作ではないのに80年近くも誤ってハイドンの名で出版されていたオーボエ協奏曲のCDが、カメラータからリリースされ、さらに同曲の異なる演奏も録音された。これは、音楽の楽しみと推理の楽しみを組み合わせたものである。またハイドン作品を基に同時代人が作った編曲に関しても、今日では新しい関心が寄せられている。例えば、コレギウム・ヴィエニーズは、ゲオルク・ドゥルシェツキが管楽合奏(ハルモニームジーク)用に編曲したハイドンの『天地創造』をCD録音した。この編曲版を聴くと、こうした同時代人の編曲版を通してハイドンのオラトリオの人気が上がったのも当然という気持ちになる。これに対して、ハイドンの様式とまったく合致しない後年の編曲―例えば幾つかの弦楽四重奏曲を無枠にヴァイオリン・ソナタに編曲したもの―は、結局消えていく運命にある。これらは、ハイドンとまじめに向き合わず、「ハイドンが作曲した曲のままではつまらないので、手を加える必要がある」と考えた時代の産物である。
以上は、演奏の世界におけるハイドン再発見を示す例である。ハイドンの没後200年にあたる2009年を重要なきっかけとして、ハイドン再発見の動きはますます拡大していくことであろう。
ハイドンの再発見は、また他の側面でもたどることができる。
H.C.ロビンズ・ランドンは、1976年から1980年にかけて5巻にわたる『ハイドン 記録と作品』を発表した。これはハイドンに関心を持つ人は誰もが参照すべき基本文献である。この著作は、当時の知識をまとめ、かつ多くの新しい研究成果を補ったものである。その後の研究の進展により、細かい部分において我々の知識はさらに前進した。それもまた、ハイドン研究が常に刻々と進んでいる証として、歓迎すべきことであろう。新しい知見は、主に論文の形で発表される。その発表の場を提供しているのが『ハイドン年鑑』と『ハイドン研究』、および多くの論文集である。ヘンレ社から出版されているヨーゼフ・ハイドン研究所編纂のハイドン全集は、100年前にオイゼビウス・マンディチェフスキが取り掛かろうとしていたものであり、2013年に全巻完結の予定である。全集版では、ハイドンの作曲した作品すべてが、特に研究目的のために統一的な判断基準の下に校訂されている。全集版で初めて新しく校訂された作品、特にランドン編纂の実用楽譜も存在しなかった作品の多くについては、演奏用パート譜も作られた。その例となるのがミサ曲、および2曲のオラトリオである。
我々の世代は、ハイドンの全体像の重要性と音楽史的な位置づけという点で、今やまったく新しいハイドンを見出している。ハイドンは同時代の他の作曲家と比較して、誰よりも有名で敬愛されており、その点ではモーツァルトをも凌ぐ存在であった。2回のロンドン旅行の後は、まさにスターとして限りない名声と人気を博した点で、他の作曲家とは比較にならない。また彼はスターとして自分を売り込むことにも長けていた。世の中のことに通じ、人に信頼され、自負心をもちながらも、謙遜で傲慢なところは微塵もなく、また優れたビジネスマンでもあった。彼は自分の価値を知り、それを拡大・確立させながら、自分の作品をヨーロッパ中の出版社に売った。ハイドンの主君エステルハージ侯爵が、侯爵以外の人間のためにハイドンが作曲したり作品を献呈したりすることを禁じた、という伝説がよく記されているが、それはまったくの間違いである。雇用契約には、侯爵のために新しく作曲した作品を、一定期間の後に他に利用してよいと規定されている。これは当時の委嘱作品においては当たり前のことであり、ベートーヴェンやシューベルトにも見られることであった。ハイドンは誰よりも人気があったために、ハイドンの名を付けた偽の作品が出回ることが他の作曲家に増して多かった。音楽の質は別として、ハイドンの名前を付けておけば、本当の作曲家の名前を付けておくよりも楽譜がずっとよく売れたのである。ハイドンの名を付して出版された曲の中には、ハイドンの個人様式には及ばないもののある程度の水準の作品もあったが、よくもハイドンの名を付けて売れたものだと驚くほどいい加減でお粗末な曲もあった。幸運なことに、今日我々は真偽の問題をかなり明確に判断することができ、真偽不明の作品はわずかしか残っていない。もちろん―これは再発見された新しいハイドン像の別の側面であるが―、偽のハードイドン作品から離れることができず、新しい学問的見解を無視する演奏家たちもいる。彼らは偽の、あるいは低レベルの編曲作品をハイドンの曲として演奏し続けている。しかし、このような演奏家の数は次第に少なくなっている。
ハイドンをエステルハージ家の楽長としてだけ見る伝統的な考え方も、すでに以前からら修正すべきものとして指摘されている。彼は生涯のうち30年にわたって、また中断を経てその後死ぬまで(名義だけではあるが)同家の楽長職にあった。しかし、侯爵家の楽長として、彼は取り巻きの中で最も高い職位にあった。芸術的・財政的・組織的な問題について自己責任による判断を許されており、今日でいうならば局長格であった。加えて、ハイドンは仕える身でありながら常に侯爵と個人的接触をもつ数少ない人間の一人であった。今日、多くの記録を検討してみると、ハイドンが侯爵の召使ではなく協力者であったことが明確にわかる。エステルハージ侯爵の宮廷に仕えながら、彼は他の貴学族のためにも作曲し、市民や出版社からの作曲契約にも応じた。その相手はウィーン、ハプスブルク帝国圏内、ドイツばかりでなく、パリ(いわゆる「パリ交響曲」)、スペイン、イギリスにまで及んでいる。
ハイドンの実像として新発見されたもうひとつの側面は、彼が非常に教養人であったということである。彼はラテン語を話すことができ、イタリア語を話し書くことに加えて、イタリア語で詩も創作した。フランス語も理解し、59歳のときに短期間でフランス語をマスターした。ひょっとするともっと多くの言語を話せたのかもしれない。その蔵書は特定の文学的関心を示しており、注目に値する。彼はまた美術収集家でもあった。イギリスの版画、すなわち銅版画とメゾチントを、ロンドンに旅立つずっと以前から収集していた。
場合によっては、報酬をお金ではなく版画で支払ってもらったことさえある。ロンドン滞在中に、コレクションはさらに拡大した。ウィーン郊外のグンペンドルフの自宅にハイドンを訪ねると、彼は、きちんと並べた自らの美術コレクションを喜んで誇らしげに見せたという。
新しく再発見された真のハイドン像は、高い教養と自負心を具えた人物像である。彼は貴族の宮廷に仕える身ではあったが、侯爵家が主君でもあり芸術保護者でもあった。ハイドンが世界的に有名になったことにより、侯爵家は「エステルハージ侯爵家の楽長」と称されることを誇りに思うようになった。ハイドンの名声は侯爵の名声を上げるのに貢献したのである。
さらに今日の我々が知っていることは、ハイドンが先駆者あるいは発明者であったばかりでなく、完成者でもあったということである。確かにモーツァルトの2曲のト短調交響曲はハイドンというお手本なしには成立しなかったであろうし、ハイドンの後期の交響曲がなければベートーヴェンの交響曲も違う形のものとなっていたであろう。しかし、モーツァルトやベートーヴェンについて考えるまでもなく、ハイドンの交響曲自体が傑作なのである。彼は決して誰かの影に隠れることはなく、また誰によっても凌駕されない。彼自身が初期の作品から後期の様式を発展させてきたのであり、ハイドンの後期作品に隠されているアイデアは後世の作曲家によってさらに展開されていった。となると、冒頭に挙げたシューマンの考えは間違っており、ブラームスの考えが正しいということになる。のちの世代がハイドンから学ぶことは、まだ充分にあったのだ。
今日我々は、再発見されたハイドンの全体像をつかみ、それに適応し、すべてのジャンル、すべての時期にわたってできるだけ多くの作品を知らなければならない。そのことをハイドンの没後200年にあたる2009年に決心したならば、今後なすべきことは山のようにある。そして、それに気づくことこそ、ハイドンの記念の年の意義であり課題なのである。