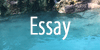「エリザベート・シュヴァルツコップ マスタークラス」について
8月25日~27日の3日間にわたり公開予定の「事務局長のエッセイ集」。その中で語られる、「エリザベート・シュヴァルツコップ女史」を講師に迎え、秋の特別マスタークラスが開催されたことをここでご紹介。40年の歴史の中で、後にも先にも夏期以外にマスタークラスが行われたのはこの時のみになる貴重な機会でした。
日程:1983年10月21日(金)~24日(月)10時~(初日は11時~)、16時~
会場:群馬県 草津町 天狗山レストハウス
主催:財団法人 関信越音楽協会(現 公益財団法人 群馬草津国際音楽協会)
講師:エリザベート・シュヴァルツコップ
アシスタント・通訳:長野羊奈子/アシスタント・ピアニスト:大場俊一、岡田知子
受講生:8名
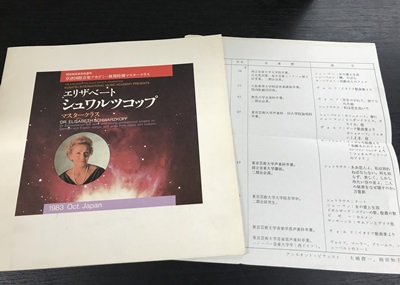
レッスンの内容《当時のプログラムより抜粋》
彼女のマスタークラスは、イギリスやドイツ、オーストリア、さらにはアメリカと世界中で行われて来ましたが、日本で行うに当たって、ヨーロッパ各国で行われているのと同様の方法が取られました。
すなわち、同一受講生による連続した6回ないしは7回のレッスンを公開するもので、それによって歌い手の進歩、あるまとまった受講生の声楽に対する明確な体験をしてもらおうと言うものです。従って、連続してこれを聴かれることによって、より深い女史の歌に対する考え方を理解することができると言うことになります。
今回は特別に草津において少人数で、肉声で聞こえる範囲の連続した公開マスタークラスを計画しました。連続した2日間だけでもそのマスタークラスのあり方が良く理解して頂けるものと思いますが、ここで4日間、女史と一緒にすごせることは、きっと色々なものを我々にもたらしてくれると信じています。
なお、女史のお弟子さんである長野羊奈子さんに通訳とアシスタント、白井光子さんに一晩のコンサートをお願いして、あわせて女史の声楽に対する考え方を知って頂く上で、援助を仰ぎました。
文:井阪 紘
1983年の秋にエリザベート・シュヴァルツコップの草津での特別マスタークラスが開催できた経緯は、遡って私と彼女との出会いから話をしなくてはならない。
私の音楽(レコード)プロデューサーとしてのキャリアは、1963年に日本ビクター株式会社に入社した後、本人の希望もあってのことだろうが、レコード部門に配属されたことから始まっている。
2年の営業経験を経て、本社のレコード部門の上長から、音楽知識があるとの認識があったのだろう、フィリップス・レコード事業部のクラシックのA&R(アーティスト・アンド・レパートリー)部門に転属させられた。
クラシックのA&Rとは、毎月、どのレコードを出すか? どのアーティストをプロモーションして売り上げに繋げるか? といったことをクラシック音楽の部門で考えるセクションである。
当時のフィリップスには、ヴァイオリニストで言えばグリュミオーかヘンリク・シェリング、チェリストではモーリス・ジャンドロンやヤーノシュ・シュタルケル、ピアニストにはイングリッド・ヘブラーやニキタ・マガロフ、クラウディオ・アラウ、アダム・ハラシェヴィッチ、オーケストラはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団で指揮者はオイゲン・ヨッフムとベルナルト・ハイティンクなどが在籍していた。ウィーン交響楽団とはヴォルフガング・サヴァリッシュが指揮者として録音が多くあったため、私は何回かサヴァリッシュ氏がNHK交響楽団に招かれるようになった折に羽田空港まで出迎えに行った。
私とマエストロとの音楽上のつき合いは、恐らくサヴァリッシュがウィーン交響楽団と60年代に入ってステレオで録音したブラームスの4曲の4枚組交響曲全集を、私が2枚のLPにまとめたときからだが、その仕事の私の音楽への取組み方に共鳴し、説明に納得してもらえたようだった。
当時、1960年代は、録音され編集された磁気のマスターテープをラッカーに切る作業、これをマスタリングと言うのだが、LP片面30分がせいぜい標準で、多く収録しても35分がリミットだった。後には、そのマスタリングにヴァリュアブル・ピッチという、テープレコーダーの再生するヘッドの前に、もうひとつ再生ヘッドを付けて、予め入力する音量の大きさを予知して、それによってカッターヘッドのラッカーの溝を広げるという方法が取り込まれるようになって、長時間の収録が可能となるのだが、私はそれ以前にマスタリングエンジニアと組んで、スコアを見ながら大きな音量になる寸前に大音量が来ても良いように溝を拡げる方法を考え出して、それによって、手作業でブラームスの40分ある交響曲をLP片面にカットすることをトライし始めた。
LPレコードは当時も1枚2200円から2400円と高価な値段がしたから、もし通常のLPと同じダイナミックレヴェルを保った、ブラームスの交響曲が2枚のLPに収まれば、それは素晴らしい顧客サービスとなる上、一曲の交響曲を聴くのに一度レコード・プレイヤーを止めて盤を裏返す必要もなくなる訳である。
サヴァリッシュはこの2枚組の自分のブラームスの交響曲全曲のLPを聴いて、フィリップスのオリジナル盤よりも良い音がすると喜んでくださったようで、その苦労話をしたことから、私は大いなる信頼を得、終生マエストロには弟子のように可愛がってもらい、多々アドヴァイスをしてもらった。
「リート(歌曲)を聴く前と聴いた後では、その人の人生は変わっていなくてはなりません。」
これは、畑中良輔先生がシュヴァルツコップのことをお書きになるときに引用されるシュヴァルツコップ自身の言葉だが、私も1968年に彼女のヴォルフとリヒャルト・シュトラウスのリートを二晩聴きに行って、彼女のような音楽家の近くで仕事をしたいものだと思った人間である。シュヴァルツコップの言うとおり、それも彼女自身のリートによって、人生のいくつかの選択肢からこの仕事に一生を託そうと決意し、歩む道を変えた人間の実例と言えるかもしれない。
それほどに彼女のリサイタルには心を揺さぶられた。歌詞の内容を知っている程度なのに、まるで一語一語の意味が心の底まで伝わるようで感動した。それは魔法にかけられたかのような時間であった。いま聴いているのは現実か、別世界なのか、それとも幻影を見ているのだろうか?――コンサートは不思議な瞬間だった。
シュヴァルツコップは言葉と音楽が持つ、すべての世界を表現してみせた歌手である。それには、気品と尊厳に満ちた完璧な声を用いたが、時には卑俗で普通は声楽家が使わないような声も巧みに交えて、あくまでも言葉を伝える手段にそれを使った。だから、あのヴォルフやR.シュトラウスのリートの世界が創れたのではないだろうか。
私がシュヴァルツコップと知り合うことができたのは、指揮者サヴァリッシュの紹介によるものであった。まだ駆け出しのプロデューサーに、その大先輩であるレッグ氏を紹介してやろうというサヴァリッシュからの暖かい支援と激励だったのだ。偶然、N響の指揮者として来日中だったサヴァリッシュが、わざわざ日本ビクターの青山スタジオに電話をくださった。
「君に会わせたい人がいる。今夜、大手町のパレスホテルに6時に来なさい。忘れないように。」と念を押された。
ホテルのロビーで紹介されたのが、エリザベート・シュヴァルツコップと、その夫で当時EMIを辞されていた名プロデューサーのウォルター・レッグの二人であった。
―つづく―