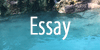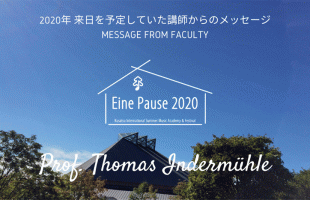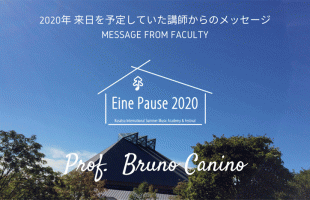文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:小宮正安
第34回プログラムより(2013年発行)
ジュゼッペ・ヴェルディはワーグナーの天賦の才を認め、何の嫉妬もなくそれを受け入れた作曲家のひとりである。ワーグナーの芸術的な方向性については時に付いてゆけない場合もあったものの、それでもワーグナーの作品を研究し、―意識的にせよ無意識的にせよ―彼から多くの影響を受けた。「私だって、音楽とドラマとの融合を試みてきた」、これはヴェルディの言葉の中でもよく引用される一節だ。「オペラ『マクベス』においてもそうしたのだが、ワーグナーがおこなっているように自分で台本を書くことはやはりできなかった。」あるいは今日、ヴェルディのオペラ『ファルスタッフ』に、ワーグナーからの明らかな影響を見て取ろうとする動きもある。
だがそれでも、両者の類似性や影響を逐一探ってゆくことは、さほど重要とは思えない。大事なのは、ヴェルディがワーグナーをライヴァル視したり、芸術上の敵などとはけっして見なしていたりしなかったということ。むしろヴェルディにすれば、ワーグナーは作曲家仲間であって、畏敬すべき存在に他ならなかった。
いっぽうワーグナーの場合は、まったく逆である。彼はヴェルディに近づこうともしなければ、近づくこともなかった。何しろヴェルディに対して、公式には何もコメントを残していないほどである。もちろん裏を返せば、それは彼なりにヴェルディを認めていた証でもあったのだろう。というのもワーグナーの場合、他の作曲家に対して否定的な見解を述べたり書いたりする場合が非常に多かったからだ。1875年11月、ワーグナーはウィーンの宮廷歌劇場でヴェルディの『レクイエム』を聴く機会に恵まれたが、終演後ついにそれについての見解を口にすることはなかった。ウィーン中がかたずを飲んで見守っていたものの、結局は徒労に終わった。
それでもウィーンの聴衆は、この2人の作曲家を同じように受け入れ、称賛し、敬愛した。何しろ当の本人たちがウィーンに足を踏み入れるはるか以前から、彼らの作品はこの街でつとに知られていたのだから。
ジュゼッペ・ヴェルディ
1843年、ヴェルディ29歳の折のこと。彼は人生初となる外国旅行に出かけ、ウィーンへ足を踏み入れる。そして4月4日、5日、1年前にミラノで世界初演されたオペラ『ナブッコ』のウィーン初演を、みずからの指揮でおこなった。彼はこの街の宮廷歌劇場管弦楽団(それに先立つこと数年前、オットー・ニコライの指揮の下、楽団のメンバーが集まってウィーン・フィルハーモニー管弦楽団が創設されていた)に熱狂し、オペラ上演も成功を収めた。人々は家庭でもこのオペラを楽しめるよう、ピアノ独奏用、ピアノ連弾用、さらには弦楽四重奏用等に編曲された楽譜を買い求め、オペラの中に登場する有名なメロディーはすぐさま巷に広まった。
ところで『ナブッコ』には、当時北イタリアを占領していたオーストリアに対する抵抗心が描かれているということが、今日さかんに唱えられている。さらには囚人たちの合唱曲として有名な「行け、わが想いよ、黄金に翼に乗って」が、オーストリアに支配された北イタリアの人々の心情を描いたものだ、ということも。だがそれらははっきり言って間違いだ。そもそも国家政治というものに対し、ヴェルディは常に一定の距離をとっていた。またヴェルディはオペラ『ナブッコ』を、当時のオーストリア皇帝フランツ1世の姪にあたるアーデルハイト大公妃に捧げている。しかも、もしもこのオペラが反オーストリア的なテーマを素材としていたならば、それがウィーンの宮廷歌劇場で上演されることなどなかったろう。というわけで、『ナブッコ』における反オーストリア的要素云々といった話は、後世の人々が考え出したものにすぎない。
いずれにしても『ナブッコ』は成功を収めた。またその後もヴェルディの新作オペラは宮廷歌劇場で上演され、批評家たちは彼がロッシーニやドニゼッティの跡を継いでイタリア・オペラの未来を担う偉大な作曲家になれるか否かを議論し合った。こうしてヴェルディのオペラは、世界初演から程なくして、ウィーンでも定期的に初演されるようになった。またそれを受けて、多くの作曲家がヴェルディのオペラの主題に基づいて変奏曲を作るようになった。
ヨハン・シュトラウス2世も1850年代から60年代にかけて、ヴェルディのオペラに登場するメロディーを用いたダンス音楽を作曲し、ヴェルディの音楽をウィーンだけではなく世界中に広める役割を果たしている。シュトラウスのダンス音楽が世界各地で演奏されていたためで、例えば「『仮面舞踏会』のカドリール」作品271などは典型的な作品といえるだろう。その他にもシュトラウスはウィーンはもとより、パヴロフスクやサンクト・ペテルブルクの夏の演奏会で、ヴェルディの作品そのものをしばしば取り上げた。
1875年6月3日、ヴェルディは妻のジュゼッピーナを連れて、2度目となるウィーン滞在をおこなった。彼らはホテル・ムンシュ(ここには現在、ホテル・アンバッサダーが建っている)に投宿。ヴェルディは新装だった宮廷歌劇場(現在の国立歌劇場)で、『アイーダ』と『レクイエム』の上演を指揮した。いわばそれは世界的に有名になった人物の凱旋公演であって、その将来的な資質に疑問を差し挟む者などもはやひとりもいなかった。ヴェルディはこれらの上演に大変な満足と感動を覚え、ウィーン宮廷歌劇場のために新作オペラを1曲書く約束をおこなった。―ただしそれが実現することは、残念ながらなかったのだが。
いずれにせよヴェルディがウィーンに滞在した出来事は、きわめてセンセーショナルであり、ヨーロッパ中の新聞がそれについて書き立てた。何しろヴェルディ指揮の公演を訪れる人々のために、ウィーンの南部から出発する鉄道には特別列車が仕立てられ、彼らが終演後深夜に無事帰宅できるよう便宜が図られたほど。
ヴェルディはウィーン滞在中、ウィーン楽友協会の資料室と音楽院を訪問している。資料室では、当時の室長だったカール・フェルディナント・ポールの出迎えを受けた。居合わせた人々の証言のおかげで、ヴェルディが資料室でどのような時間を過ごしたかが今でもよく分かる。
ヴェルディは、彼にとって「唯一の偉大な作曲家」であるベートーヴェンの直筆や遺品を見たいと希望した。そこでポールはまず、ベートーヴェンのデスマスクを見せたところ、ヴェルディはそれを感慨深げに長い間眺めていた。また「英雄交響曲」の有名な直筆総譜(表紙にはナポレオンに宛ててしたためられた献呈の辞をベートーヴェンがこすり取った跡が残されている)をポールが持ってきたところ、ヴェルディはその前で帽子をとり、畏敬の念を示した後、およそ半時間もの間それをじっくり研究した。『新自由新聞』の記事によれば、ヴェルディが「この素晴らしい作品のあらゆる音符を知り尽くしている」ことが、その様子からは分かったそうである。あるいは別の新聞に曰く、ヴェルディが「作品の隅から隅まで理解しているのは一目瞭然だった」。さらにジャーナリストで評論家でもあったテオドール・ヘルムの記憶によれば、ヴェルディは総譜を「深い感動を身体一杯に湛えながら研究していた」。
またヴェルディの興味を特に引いたのが、ベートーヴェンがボン時代に作曲し、断片としてしか残されていないヴァイオリン協奏曲ハ長調の直筆譜だった。この曲は当時未出版の状態だったのだが、ヴェルディはその場に一緒にいたウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターであり、楽友協会音楽院のヴァイオリン科教授でもあったヨゼフ・ヘルメスベルガーとあれこれ議論をした結果、その4年後ヘルメスベルガーは当協奏曲を自ら補完し、第1楽章を初出版することとなる。いずれにしてもヴェルディはベートーヴェンのことを「あらゆる時代や国々が生んだ作曲家の中でももっとも偉大な存在」と呼んでおり、そうした人物に対する感動を繰り返し、しかも生き生きと表明した。
その後ヴェルディは楽友協会資料室で、フランツ・シューベルトの手稿や直筆譜を閲覧した。(ただしそれらが何であったのかについては、残念ながら分からない。)さらにはオリジナルの直筆譜だけでなく、作曲家の遺品にも興味を抱いた彼は、例えばモーツァルトの遺髪を目にしている。それでもこの様子を見ていた人々にとってみれば、ヴェルディが偉大な作曲家たちの直筆や遺品に大きな興味を示す一方で、新しいものに対する見聞や経験を大事にしていることは明らかだった。再び『新自由新聞』の記事によれば、「未だかつてベートーヴェンの直筆を見たことがなかったヴェルディは、ウィーンでこのような素晴らしい遺品をたくさん発見できた喜びを、繰り返し口にしていた」。つまり彼は先達たちの直筆譜を、研究用の音楽資料としてだけではなく、遺品としても受け止めていたということだろう。
ところでヴェルディのウィーン楽友協会訪問は、彼のために特別に企画された演奏会で幕を開けた。出演は楽友協会音楽院の生徒たち、会場は協会の小ホール(現在のブラームス・ザール)である。10歳から14歳の男女の生徒からなる音楽院管弦楽団が、ヨゼフ・ヘルメスベルガーの指揮の下、最初にフランソワ・オーベールの序曲を演奏した。ヴェルディは演奏の出来栄えに心底驚き、賛辞の言葉を重ねながら次のように語っている。「このような音楽院のオーケストラが世界的に見てトップの実力を誇っているのだから、ウィーンはすごいですね。他の街にも音楽院はありますが、そもそもここまでのオーケストラを具えている例などありません。」
この後、音楽院の生徒たちが、『椿姫』や『イル・トロヴァトーレ』からアリアやデュエットを披露。彼らの歌唱力にも、ヴェルディは心底感銘を受けた結果、特にソプラノのエテルカ・ゲルストナーをヴェネツィアのフェニーチェ劇場に推薦し、彼女は1875年12月に同劇場で『リゴレット』のジルダ役でデビューした。また彼女は翌年もヴェルディのお蔭で、ジェノヴァの歌劇場と契約することとなった。
ところでヴェルディは楽友協会音楽院で、音楽院のカリキュラムや組織についても質問を重ね、最後に感嘆の言葉を述べている。「今日ここで披露してもらった成果に、私が心底驚いたことをご存知ですか?」次いで、このように続けた。「この組織に備わっている素晴らしい秩序は、生徒たちの成長にとって一番理にかなったものでしょうね。」またヴェルディは―若い頃オルガニストだったこともあり―楽友協会大ホールのオルガンも案内してもらい、大変な感銘を受けている。またそうした事情からヴェルディは1898年、自らの「アヴェ・マリア」をウィーン楽友協会合唱団が世界初演することを許可した。
ウィーン滞在中のヴェルディは、時の皇帝フランツ=ヨーゼフから、個人的な謁見を賜る機会に恵まれた。その際皇帝はヴェルディに対し、外国人が受けられる最高の勲章=「フランツ=ヨーゼフ勲章の星付コムトゥア章」を授与する。これはイタリアの誕生に当たって吹き荒れた反オーストリア的、国家的な動きの中で、ヴェルディが毅然とした態度を貫き、そうした動きに利用されなかったことに対する感謝のしるしに他ならなかった。
リヒャルト・ワーグナー
ワーグナーは19歳のおりはじめてウィーンを訪れ、彼自身の言葉に曰く、この街に我が家のような親しみを覚えた。彼は当時既に作曲家としてそれなりに知られており、ウィーン楽友協会でも認められた存在だった。またヨハン・シュトラウス1世とその楽団に魅了されたのもこの時だった。
ワーグナーが2度目にウィーンへやって来たのは1848年のこと。彼はこの街を足掛かりに、ドイツ語圏の劇場の改革を夢見ていた。この街が若々しい力に満ちているという印象を持った彼は、自らの斬新な理想を他ならぬウィーンから広めてゆけると考えていたのである。
ところがワーグナーは、当時本拠地としていたドレスデンで勃発した革命に加担したかどでスイスに亡命の身となり、恩赦が与えられる1861年まで彼の地にとどまっていなければならなくなった。それでもこの間も、彼はウィーンと度々コンタクトを取り続けた。あるいはヨハン・シュトラウス2世は、自らの演奏会でワーグナーの作品を取り上げ、その中には楽劇『トリスタンとイゾルデ』からの数曲の世界初演も含まれていた。また1857年以降、ワーグナーのオペラはウィーンで上演されて大成功を収め、とりわけ『タンホイザー』『ローエングリン』『さまよえるオランダ人』は人気演目だった。
スイスでの亡命生活を終えたワーグナーは、ウィーンに腰を据えるという計画を抱くようになり、1863年にそれを実行に移す。彼は、シェーンブルン宮殿からさほど遠くない優雅な住宅地に家を構え、その中に豪華な内装を施し、何人もの使用人を雇った結果、すぐさま借金まみれの身となった。結果、ついには債務過剰のかどで逮捕を逃れるべく、ウィーンから逃げ出した。
この事件が起きる前、ウィーンの宮廷歌劇場はワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』の世界初演に向け、ピアノ・リハーサルを開始していた。トリスタン役とイゾルデ役にはそれにふさわしい経験豊かな歌手が起用され、彼らはこの作品に深い感銘を受けながら音楽と一体となってリハーサルを進めていった。
ところがトリスタン役の歌手が突然病気になり、1864年にはそれが原因で死去することとなる。そうした状況の中、彼の力は急激に衰え、声にも支障が出るようになってしまった。同じくイゾルデ役の歌手も、トリスタン役の歌手ほど危険な状態ではなかったものの病気にかかり、体力低下により役を務めることができなくなった。ワーグナーはイゾルデ役の彼女に理解を示し、トリスタン役のテノール歌手にも同情したものの、もはや代わりの歌手を見つけるだけの時間がなかった。そこで、この2人の歌手が再び歌えるようになるか否かがはっきりするまで『トリスタンとイゾルデ』の世界初演を延期しよう、ということになったのである。ワーグナーにとっては、この作品の初演にあたって別の歌劇場など考えられなかった。また当時作曲中だった楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』も、ウィーンで上演する心づもりだった。
いっぽうワーグナーと対立する人々は、『トリスタンとイゾルデ』が上演不可能であり、どのような優れた歌手でもこの作品を歌えないという噂を流した。何しろ主役級の2人の歌手ですらリハーサルで声を失い、それもこれもワーグナーが彼らの声をダメにしたのだと……。それに対しワーグナーの信奉者は、『トリスタンとイゾルデ』の初演ができなくなったのは、この作品に適した歌手を起用できなかった宮廷歌劇場に責任がある、と主張した。ありていに言えば両陣営の言い分とも間違いなのだが、今日にいたるまでワーグナー関係の本を見ると、この間違った主張がいたるところに引用されているというのが現実だ。
じっさいこの時期に書かれたワーグナーの手紙をきちんと読めば、主役の歌手2人が降板し初演が不可能になったことに対し、彼がけっして失望していたのではなかったということはよく分かる。あるいは、他の歌手を用いてウィーンや別の場所での初演の機会を探っていたのではないということも。ワーグナーは当時、ゆくゆくは「指揮のヴィルトゥオーゾ」をして生きてゆこうと思い、作曲家としても指揮者としても称賛されることを望んでいた。ちょうど『ニュルンベルクのマイスタージンガー』を完成させようとした頃だが、作曲家として持てはやされたいとはさほど考えていなかったようである。
ワーグナーは、借金についても気に病んではいなかった。最初のうちは、何週間か経ってほとぼりが冷め、新たにどこからか借りた金で借金の埋め合わせをすればウィーンに戻れ、豪華な屋敷暮らしを再開できると考えていたのである。ところがその間に、彼のもっとも大事な友人(その人の名はヨゼフ・シュタントハルトナーといい、ウィーン楽友協会の執行部も務めていた人物である)が件の屋敷を売り払って借金を帳消しにし、債務超過によって外国でもワーグナーが逮捕されかねない状況を回避してくれたのだった。そこでワーグナーはウィーンに住むことを諦める羽目になったのだが、別段その状況に怒ったわけではなく、ましてウィーンに腹を立てることもなかった。
ワーグナーはウィーンで、後の人生に大きな影響をもたらすような貴重な経験を積んだ。中でも重要なのが、個人的な事柄においても芸術的な事柄においても自らの途方もない要求を可能とするには、金持ちの大支援者が必要だと考えるようになったこと。つまりは、ワーグナーの要求全てを満たせるような生活様式を可能にし、彼のオペラを理想的な形で―それも上演回数を制限して質の高い上演だけをおこなえるような音楽祭の実現をもたらしてくれる人物、ということになる。じっさいこの頃のワーグナーは、自らのオペラを自らの音楽祭で上演できさえすればそれでよく、その後それらが様々な歌劇場で取り上げられてゆくことについてはさほど関心を持たなくなりつつあった。
こうしてワーグナーはウィーンでの経験を通じて、今日私たちにもお馴染みの人生に乗り出してゆく。実際彼は、やがて莫大な額の金を用立ててくれる支援者を見つけた。その人こそ、バイエルン王のルートヴィヒ2世。彼の援助の甲斐あって、ワーグナーはバイロイト音楽祭を創設し、指揮者として演奏旅行を展開してゆけるようになった。
指揮者としての演奏旅行をおこなう際にも、ワーグナーは特に足しげくウィーンを訪れた。そしてウィーンの人々も彼を作曲家としてだけでなく、指揮者として大いに称賛していた。既に1856年、モーツァルトの生誕100周年記念の演奏会を開催するにあたって、ワーグナーを指揮者として招こうという動きもあったほどだ。(ただし、この計画が実現することはなかった。)
あるいはウィーンを本拠地としていた時代、ワーグナーは演奏会を催しては輝かしい成功を収めている。それらの演奏会では、自作のオペラの一部が取り上げられたのだが、オペラ本体から切り離して上演する必要があったため、特に新たに演奏会用に「ウィーン版」が作られた。また後年、ワーグナーはウィーン楽友協会大ホールで演奏会を指揮することがあったが、そこでの収益はバイロイト祝祭劇場の建設資金に充てられた。そしてこの劇場が完成し、バイロイト音楽祭が始まった後は、ウィーンとバイロイトを往復する特別列車にウィーンの人々が乗り込み、彼の地を訪ねていったのである。
ところで他所の場所と同じく、ワーグナーと対立する人々はウィーンにも現れた。彼らはワーグナーの芸術的意図を理解せず、それゆえワーグナー本人からも拒絶されたのだが、興味深いことにワーグナーは彼らに対し怒りを露わにするのではなく、無視するという形をとったのである。つまり彼らは対立する存在ではあっても、敵ではなかったということだ。たとえばこの時、ワーグナーから拒絶された批評(たとえばエドゥアルト・ハンスリックのもの)が今日では当たり前のように取り上げられる場合が多いが、これらはあくまである事象に的を絞った文学作品であって、読者が感心しながら読むことを前提に書かれたものであることを忘れてはならない。
というわけで、巷間言われるワーグナーとブラームスの敵対関係なども実際には存在しなかったのである。何しろ『トリスタンとイゾルデ』がウィーンで世界初演される計画が持ち上がった時、ブラームスは写譜の手助けをおこなっているほどだ。またワーグナーがウィーンに構えた豪華な邸宅をブラームスが訪れ、楽興の一時を愉しんだこともある。ただしこうした機会は、残念ながらけっして数多くなく、長続きもしなかった。というのもワーグナーが債権者から逃れなければならなくなったためである。
逆にワーグナーもブラームスの演奏会を何度か訪れ、もっとも目立つ一番前の席に座ることをもっぱらとした。それによって自分がブラームスに興味を持っており、ブラームスを拒絶しているのではないことを人々に示そうとしたためである。さらにブラームスが直筆譜を集めていることを知ったワーグナーは、自らの直筆譜のいくつかや、『ラインの黄金』の総譜を送ってさえいる。なお当時ウィーンで活躍していた指揮者のハンス・リヒターは、ブラームスともワーグナーとも親交を結んでいた。
計画こそあったものの、結局ワーグナーがウィーンに腰をおろすことはなかった。それでもウィーンはワーグナーにとって重要な街であり、ウィーンにとっても彼は重要な存在であり続けたのである。
興味深いのは、ヴェルディとワーグナーが、ウィーンにいた若い作曲家たちにどのような影響を及ぼしたのかという問題である。実のところ多くの作曲家はワーグナー志向であり、ヴェルディを規範としようとする者はほとんど現れなかった。ヴェルディの衣鉢を継ぐにはイタリア人でなければならないと信じられていたためであって、それはイタリア人がワーグナーのように作曲できないと考えられていたのと同じこと。というわけで若きウィーンの作曲家にワーグナーが及ぼした影響は大きく、ヴェルディのそれは小さいということになるのだが、それでも彼らは両者を同じく称賛していた。その典型的な例こそ、グスタフ・マーラーだったのである。