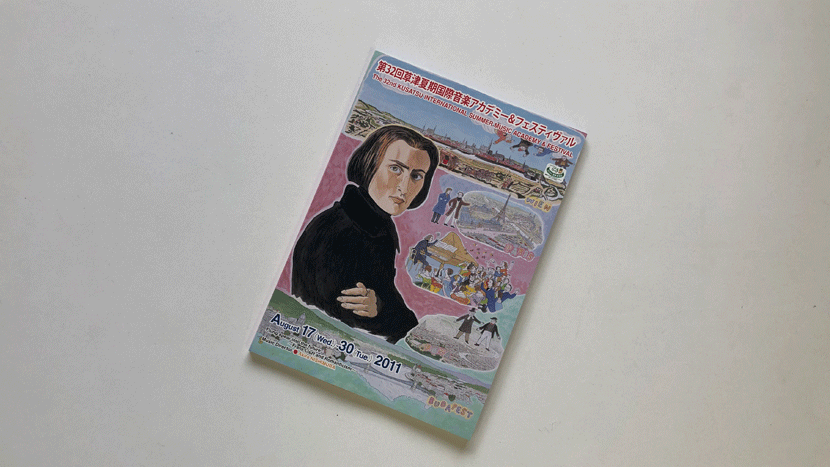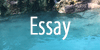文・福田 弥
第32回プログラムより(2011年発行)
フランツ・リスト(1811~86)は、19世紀ロマン主義のヨーロッパを駆け抜け、ヴィルトゥオーゾ・ピアニストとして空前の成功を収めた音楽家です。しかしその一方で、寒村に平民として生まれたこと、一般の高等教育を受けられなかったこと、生涯にわたって永住の地をもたなかったことなど、少なからぬコンプレックスを抱えていたと思われます。彼の生涯を概観すれば、ヨーロッパのさまざまな地域や人物と繋がりがあることがお判りになるでしょう。ヴィルトゥオーゾとして、文字通り、全ヨーロッパに足跡を残し、パリ、ヴァイマル、ローマ、ブダペストなど複数の国に居を構えました。これは別の言い方をすれば、「根無し草」のような人生とも言えるかもしれません。あくまで推測ですが、異邦人であり続けた彼は、自らのアイデンティティを確かめる必要があったのではないでしょうか。だからこそ、彼はことあるごとに自らが「ハンガリー人」であることを強調し、「ハンガリー狂詩曲」を演奏したのでしょう。ただしここでは、ハンガリー以外のリストについて述べてみます。
パリ
19世紀、パリを制すること、それはヨーロッパを制することでした。ロッシーニ、ヴェルディでさえパリ進出を図ったのです。その意味では、シューマンやワーグナーは、生前はあくまでもドイツの作曲家に過ぎませんでした。そのパリで、音楽の中心といえば、宮廷やオペラ座と並んで、サロンを挙げなくてはなりません。音楽家にとって重要なことは、貴族のサロンで名声を掴むことであり、そのためにはまずは紹介状が必要で、リストの場合はウィーンでもらったメッテルニヒからの紹介状が功を奏したことでしょう。サロンは、なんの補償もなかった音楽家たちにとって、人的交流、マネージメント、食事や宿泊場所の提供など、福利厚生、社会保険としての重要な役割を担っていました。反面、バルザックの小説や「椿姫」などにも描かれているように、快楽主義に浮かれた、移り気なこの街で確固たる人気を掴むためには、さまざまなかけひきも必要でした。たとえばショパンが、ポーランド系移民の貴族たちのコミュニティを足場にしていたことはよく知られています。
9歳からピアニストとしてもてはやされ、パリへやってきたリストの精神的土壌はこの地で培われていきました(ちなみにリストの第一言語はフランス語となります)。しかし幼少期のリストにとって、パリでの生活が順調に始まったわけではありませんでした。パリ音楽院からの入学拒否、1827年の父の死(15歳にして母親を養う生活)、そして翌年の貴族令嬢との失恋は、リストの精神に大きな打撃を与えたと考えられます。とくに後者は、階級による差別という社会の現実を強く認識させたことでしょう。
1830年の七月革命以後、ラムネー神父の自由主義カトリシズムやサン=シモニズムの思想からも影響を受けたことで、天才は社会に対して大きな役割を担うべきであるという思想を身につけていったと考えられます。そんななか、パガニーニ、メンデルスゾーン、ショパン、ベルリオーズたちとの接触を通じて、さまざまな刺激を受けました。とくにショパンとは1832年から35年にかけてたびたび共演しています。一方で、オペラ座やイタリア座では、ベッリーニやマイアベーアの華やかなオペラが上演されていました。今にして思えば、なんと贅沢な音楽シーンだったことでしょう。
パリを代表するサロニエール(サロンの経営者)であったマリー・ダグー伯爵夫人との出会いもまた、大きな経験でした。彼女は一時期、ジョルジュ・サンドと共同してサロンを開いていました。この時代のパリでは、先前にも述べたように、喜びや快楽を第一義とする享楽的な風潮があり、結婚後の恋愛はわりと普通であったようです。しかし、遺産相続の問題が生じるために、通常は子供を作りませんでした。それに対して、リストとマリーがとった行動は例外的と言えるでしょう。3人もの子供(そのうちのひとりが、のちにワーグナー夫人となるコジマ)に恵まれたことは、ふたりの愛情の深さを物語っています。しかし、3人の父親はリストですが、ふたりの母親の名は偽名で、ひとりは不明となっています(「母親不明」とはありえない話です)。
しかし、1844年にマリーと別れてからの後半生、リストとパリの関係は疎遠になっていきます。とりわけ1866年3月15日、パリで行われた「グランのミサ・ソレムニス」の演奏は、リストの心に大きな傷を残しました。このミサ曲には少なからぬ自信をもっていただけに、旧友のベルリオーズやドルティグから酷評されたことで、リストは深く傷つき、ますますパリから遠ざかることになってしまったようです。15年以上経った1882年2月27日にマイエンドルフ夫人に宛てた書簡から引用しましょう。「ベルリオーズが『グランのミサ』を攻撃し、「芸術の否定」とまで非難した時、私のふたりの旧友、ベルリオーズとドルティグは、……私との関係を否定しました。……私には才能がなく、ピアニストとしての成功にとどまっていればよいのだから、作曲にかかわるなどまったくもって間違いである、と結論付けたのです」。
ヴィルトゥオーゾ時代
1839年から47年にかけてのツアーは、訪れた地域と、その人気や演奏会の数、レパートリーなどの点で、まさに空前の規模であり、それによってリストはヨーロッパを席巻していきました。鉄道が未発達であったにもかかわらず、北はサンクトペテルブルク、グラスゴー、南はジブラルタル、東はイスタンブール、西はリスボンと、文字通り全ヨーロッパの主要都市に足跡を残しています。こうした華やかな面ばかりが強調されますが、10年近くにわたって、落ち着く暇も場所もなく、演奏会のために移動し続ける生活を送ったリストが、どれほど精神的に充足していたか、それは判りません。というのも、当時の公開演奏会で演奏されていた曲と言えば、オペラや民謡のパラフレーズ、技巧的作品などが中心でした。ベートーヴェンのソナタなどは、リストは折に触れて弾いていましたが、当時、弾いていた人はほとんどいませんでした。イタリアではエチュード(練習曲)をリストが弾いたとき、「勉強しに来たんじゃない」という野次が飛んだとリストは書いています。貴族のようにサーベルを持って舞台に上がり、失笑されたこともありました。ルイ14世をまねて「朕は演奏会なり」と言ってみせたこともありました。一方で、「大衆の喝采が私に何をしてくれるというのか。空虚で他愛のない祝福に自問している」と憂いています。聴衆と音楽家の乖離。これは、当時の(そして現代の)多くの音楽家が抱えている問題です。
ヴァイマル
1848年から宮廷楽長としてヴァイマルに居を構えます。ヴァイマルは小さな街ですが、文化都市として全ヨーロッパに知られた街です。イルム川を渡った高台にあるアルテンブルク荘に、カロリーヌと住んでいました。若き日に、反体制的ともいえる思想を持っていたリストが、なぜに宮廷楽長という体制に従属した職に就いたのでしょうか。宮廷側としては、ゲーテ亡きあと、もう一度、文化的に復興させたいという思惑があり、オーケストレーションの修練を積んだことのないリストにとっては、自由に使える管弦楽団があることは大きな魅力でした。つまり、音楽家としての実利を優先したと考えられます。
この地で、交響詩などの管弦楽作品に取り組むと同時に、教育活動にも力を注ぎました。その結果、ヴァイマルは革新的な新ドイツ派の中心地となり、多くの若い音楽家がリストの取り巻きとなりました。以降、リストは無料で多くの弟子を育てましたが、それは、若き日に身につけた思想、すなわち才能ある者は社会に貢献すべきであるという考えを実践していた結果であると思われます。宮廷楽長を辞めてローマに住んで8年、再びリストは1869年から1年の数ヶ月をヴァイマルで過ごすようになります。その際、宮廷から与えられた家Hofgärtnereiが、現在のリスト博物館です(今年、リニューアル・オープンしました)。同じ通りには、晩年のリストを撮影した写真家ルイス・ヘルトの店舗があります。
ローマ
1837年夏から約2年間、リストとマリーはイタリアに滞在し、各地でさまざまな文学や美術、民謡に接します。ヴィルトゥオーゾ時代にも、イタリア各都市を訪れています。とくに1839年3月、ローマでは史上初となるピアノ・リサイタルを敢行しました。当時の演奏会は、多くの音楽家がさまざまなジャンルを演奏することが当たり前でしたから、一人で演奏会を行うなど考えられない冒険であったはずです(初の公開リサイタルは翌40年6月にロンドンで行われました)。
1861年以後、リストはローマに生活の拠点を置きます。カロリーヌ・ザイン=ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人との婚礼はキャンセルとなりますが、リストはそれほど落胆していたようにはみえません。むしろ、ヴァイマルの宮廷楽長としての煩わしさから解放されたことを喜び、精力的に作曲活動にいそしんでいます。それまでのリストの集大成とも言うべきオラトリオ「キリスト」を書いていた1865年には、聖職者の資格を得ています。そのために、彼は昵懇であった枢機卿のもとで修練を積み、一時期、ヴァチカンにも住んでいました。
1869年からは、1年をヴァイマル、ブダペスト、ローマで住み分けるようになります。とくに亡くなるまでの十数年は、噴水と糸杉で有名なローマ近郊のエステ荘で生活をしていました。「エステ荘の噴水」は、晩年の獄作のなかでもよく知られた作品です。
彼の多彩な活動や思想は、現在でも充分には知られているとは言えません。華麗なヴィルトゥオージティーへの反動だけでなく、リスト自身の矛盾した性格も、誤解を招く一因となっているのかもしれません。たとえば、人間の救済を主張する聖職者でありながら、しばしば女性問題を引き起こしました。また、自由主義の傾向を示しながらも貴族趣味を表に出すこともありました。失言や大仰な言動も少なからずあり、ハンガリーを祖国と主張しつつも、必ずしもハンガリー人から手放しで受け入れられていたわけではありません。国際的活動が、日和見主義や根無し草のような印象を与えたことも否めないでしょう。こうした矛盾して見える言動には、彼なりのコンプレックスが背景としてあったためとも考えられるのです。
生誕200年を契機に、彼の実像に光が当てられ、ピアノ曲以外にもより多くの作品が演奏されることを願ってやみません。
福田 弥(1966年~)
慶応義塾大学文学研究科後期博士課程満期終了。音楽学(西洋音楽史学)専攻、フランツ・リスト研究。1995〜97年にハンガリー政府給費生(特別研究員)としてブダペシュトのリスト音楽院に留学。武蔵野音楽大学専任講師を経て、現在、慶応義塾大学文学部准教授。おもな著作は『「リスト」作曲家 人と作品シリーズ』(音楽之友社2005年)。