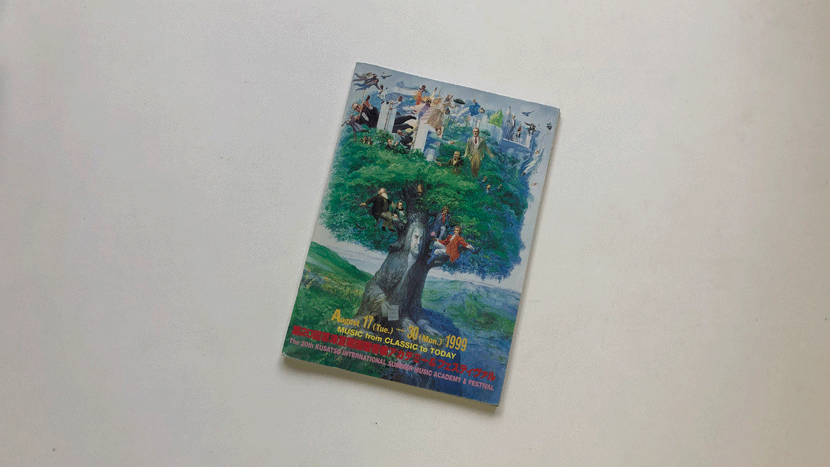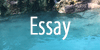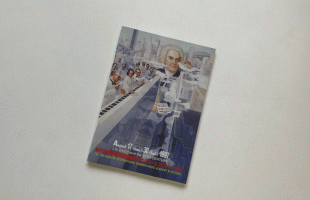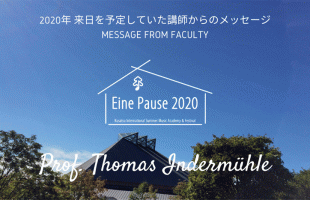文・佐野光司
第20回プログラムより(1999年発行)
今日の音楽生活のほとんどは18、19世紀の音楽で占められている。今日の演奏家の演奏する音楽も、私達、聴衆が享受する音楽も、そのほとんど―人によっては全て―が18、19世紀の音楽だろう。もっと具体的に言えばベートーヴェンを中心とした前後約100年、つまりヴィヴァルディ、バッハの後期バロック時代の音楽から、後期ロマン派の音楽か、せいぜいドビュッシー、ラヴェルらの印象主義の音楽までであろう。この印象主義の音楽スタイルが、今日一般に行き渡っている音楽の下限であり、境界のように思える。
もっともこう言い切ってしまうと、居心地の悪い音楽家達がいるのも確かだ。今日の作曲家である。今日の音楽史を営々と築いている彼等の存在を忘れる訳にはいかないだろう。彼等は18、19世紀の音楽中心の音楽生活の中で、創作の上でこれとどう対峙してきたのだろうか。ここで書く内容はここにある。
どんな文化も、その文化の持つ伝統と深く結びついている。20世紀の音楽も、その基本を18、19世紀の音楽に負っていることは云うまでもない。毎度「18、19世紀の音楽」と書くのも大変なので、その音楽をここでは「古典」としておこう。今世紀の作曲家にとって、規範とすべき「古典」とはまさしくこの時代の音楽であり、後期バロックより古い音楽を規範としている作曲家はほとんどいない。
ところで20世紀の作曲家でも、第2次大戦前と大戦後とでは、古典に対する態度が大きく異なっている。今世紀の前半の作曲家達の音楽は、古典の伝統を超克しようと試みながら、基本的には古典の発展・継承であったと言えるだろう。見かけ上では、ドビュッシーもシェーンベルクも自分の直前の音楽とは決定的に異なった音楽を作った。しかし彼等の脳裏には、常にヴァーグナーがあり、ベートーヴェンがあった。ドビュッシーがベートーヴェンについて「《田園交響曲》を聴くくらいなら、朝日の昇るのを見ていた方がずっとためになる」と批判したり、「ヴァーグナーは日の出と勘違いされた美しい落日であった」「ヴァーグナーの後につくというのでなく、ヴァーグナー以後を模索しなければならない」と述べた時、彼はベートーヴェンやヴァーグナーのドイツ・ロマン主義の呪縛から脱却出来たと確信したのではないのか。
確かにドビュッシーの音楽は、ドイツ・ロマン派に対して「フランス国民楽派」とも言いうる音楽を創った。だが、その根底はヴァーグナーによって徹底的に用いられた属7系の和音に、異なった意味を与えたものだ。シェーンベルクがドビュッシーの方法について「彼の和声法は、ヴァーグナーが指し示した道をさらに突き進めたものである」と評したことは、半分は正しい。ただしドビュッシーの真の新しさは、音楽的時間にあると言うべきだろう。
シェーンベルクはドイツ=オーストリーの文化圏にいたため、もっと深くその伝統に根ざしている。彼は『民族の音楽』(1931)という論文の中で、自分の音楽のオリジンについて、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ヴァーグナー、ブラームスらの名を挙げ、各々の作曲家からどのようなことを学んだかを具体的に記している。たとえばバッハを例にとると、「1)対位法的思考。つまり伴奏づけうる音形を作る技法。2)一つの動機から全てを創りだし、音形同士を関連づける技法。……」等といった具合に、各々の作曲家について3項目から5項目ぐらいその影響を列挙している。これはシェーンベルクが12音技法の完成後、10年ほど経ってから書いたものだが、なお、自らの音楽にある古典からの影響を、むしろ自信と誇りをもって語っている。
シェーンベルクが破壊した調性とは、主音を中心とした音の階級制のシステムであった。ショースキーによれば、調性とは、ルイ王朝下におけるバロック的身分制度に属したもので、このシステムは階級的文化の下での人間生活を現しており、これに対して12音技法は、この階級制度を破壊し、平等主義的な響きの世界を作ったという。
この考えは実は筆者も学生時代に友人達と討論したことのある考えだ。調性の確立は18世紀初頭であり、12音技法の考案は第1次大戦後なので、歴史的社会的情況を考えるとうまく当てはまる。ただその並行関係をそのまま結びつけるのはやや安易な観があるので、誰もが思いながら文章にしなかった、といったところだ。さすがにヨーロッパ人は思ったことは自信をもって書く。
ところでシェーンベルクは、12音技法によって新たな響きを獲得したが、その響きの新しさにも拘わらず、彼の音楽構成法は先に引用したように、基本的には古典の延長線上にあった。だがそれは一人シェーンベルクに限らず、ベルク、ヒンデミット、バルトーク等、両大戦間のほとんどの作曲家に当てはまる。K.H.ヴェルナーが「1950年頃までの作法は、基本的には古典・ロマン派の原理と同じである」と言ったのは正しい。彼等の音楽は、音響的な新しさと、形式的な古典性を特徴としている。
大きな変化は第2次大戦後に起こる。点描音楽と不確定性の音楽である。点描音楽はメシアンが《音価と強度のモード》(49)で始め、弟子のブーレーズが《ストルクチュールI》(52)で継いだ。ここでは音楽を構成する上でこれまで不可欠だったモティーフと認識しうるものが全て破壊された。シュトックハウゼンは《音価と強度のモード》を聴いた時「あたかも天空の星たちをみるかのような幻想的な音楽」と評している。そこでは個々の音は宇宙空間にある星のごとく、モティーフ的な関連なく散らばっていた。ベートーヴェンもヴァーグナーも存在しなかった。
ジョン・ケージを震源とする不確定性の音楽は、もっと大きな衝撃を与えた。点描音楽がまだ残していた12音への依存は、不確定性の音楽では否定され、従来の「音楽作品を構築する」という「創作」の概念そのものが否定された。それはアリストテレスが『詩学』の第7章で述べた起承転結を基本とする劇作法―ヨーロッパの芸術は、全てその延長線上にあったのだが―に対する決定的な否定であった。おそらく1950年代から60年代が、最も古典の伝統を強く否定した時代であろう。この時代はそうすることによって、自己の内に澱のように付着している古典の残滓を洗い落とそうとした。それが新しい音楽を生み出すエネルギーだったと言えなくもない。
しかし同時に、不確定性と古典的な「詩学・修辞学」とを結びつけた音楽が、新たな響き(トーン・クラスター)の装いをもって現れる。ベンデレツキの《広島の犠牲への哀歌》(61)、武満徹の《テクスチュアズ》(64)等にそれを見ることが出来よう。ここにはモティーフを中心とした伝統的な形式は存在しないが、一つのクライマックスに向かって進む、アリストテレス的な詩学が内在している。そしてさらにベリオの《シンフォニア》(67)を嚆矢とする古典音楽の引用が、現代と古典との関係にあらたなページを開いた。シュニトケが《ピアノ五重奏曲》(75)で始めたポリスタイリズム(多様式主義)は、ベリオの引用音楽の発展であるだけでなく、今日の音楽の基底を成していると言っても過言ではない。彼は自己の《合奏協奏曲》(78)について次のように語っている。
「この曲は3つの音楽の領域からなっています。その第1はバロック音楽的特徴と形式の見られる領域であり、第2は調性から開放された半音階と微小音程の領域で、最後の第3は陳腐な性格の卑俗な商業実用音楽の領域です。」シュニトケはこの異なった様式の対比を、古典が持っていた調性の対比に替わるものとして考えた。
引用音楽やポリスタイリズムは、古典を歴史的視座の中で捉えた。そこでは古典を超克すべきものとして、と云うよりはむしろ音楽的素材として対象化したと言えるだろう。ここが今世紀の前半と大きく異なる点である。今日の創作において、古典はドビュッシーやシェーンベルクのように超克すべき対象として内化しているのではない。「今」は、20世紀も含めて過去300年の音楽が音響的に対象化され、古典は「音楽の詩学」として音楽構成の在り方に内在していると云うべきだろう。
佐野光司(1937~)
日本の音楽学者、現代音楽研究の第一人者。スクリャービン研究で名高い音楽学者。桐朋学園大学名誉教授。この他、第21回の当音楽祭プログラム冊子に「「描かれない音への眼差し」も寄稿。