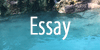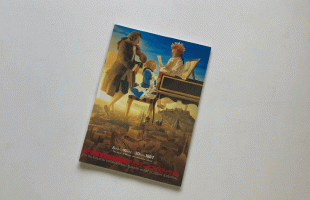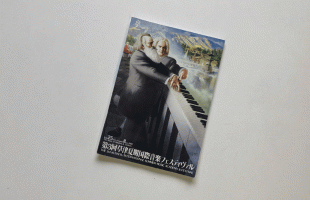文・三宅幸夫
第12回プログラムより(1991年発行)
普段なにげなく使っている言葉でも、改めて意味を問われると、答えに窮することがままあるものだ。さしづめ「ロマン主義」(あるいはロマン派の音楽)などは、そのよい例だろう。この言葉、とくに音楽関係者のあいだでは、すでに〈了解済み〉の言葉として用いられることが多い。「試験は、ロマン派から任意の一曲」といった具合で、ベートーヴェンやシェーンベルクの作品を選ぼうものなら、最初から常識を疑われるという寸法だ。しかも、同じ時代に同じ土地ウィーンで活躍していた他の作曲家、たとえばベートーヴェンに対するシューベルト、あるいはシェーンベルクに対するマーラーならば問題なしとするのだから、これも、かなりいい加減な〈了解済み〉ではなかろうか。
もちろん言葉には、意味が曖昧だからこそ使いやすいという面があることは承知している。だが、それにしても「ロマン主義」は音楽の分野だけでなく、19世紀ヨーロッパ文化総体を特徴づける第一級のキー・ワードだけに、このまま野放しに用いてよいわけはなかろう。そこで、まずは「ロマン主義」にまとわりついている様々な誤解・曲解をとくために、文学や美術にも触れながら、幾つかのテーゼを立ててみよう。
1.ロマン主義は時代概念ではない:音楽の分野では、シューベルトが『糸を紡ぐグレートヒェン』を作曲した1814年から、シェーンベルクが無調の世界に足を踏み入れた1907年までを、ひとまとめに「ロマン主義の時代」と呼ぶことが多い。しかし、これも二重の意味で忠実を裏切っている。たとえば、歌詞・音楽ともにすぐれてロマンティックなモーツァルトの歌曲『ラウラに寄せる夕べの想い』(1787)とR.シュトラウスの『最後の四つの歌』(1948)―両者は前述のロマン主義の時代を、はるかに逸脱しているではないか。また、160年余りの隔たりがあるにもかかわらず、この二つの作品に通じる親近性は否定すべくもないが、反対に、同じ時期に生まれた作品だからといって、こうした親近性がみられるとは限らない。たとえば、ベルリオーズの『幻想交響曲』とショパンの『練習曲集』、ワーグナーの『マイスタージンガー』とブラームスの『ドイツ・レクイエム』……これらの作品のあいだに、いったいどれだけ共通の分母がみつかるというのだろう。
それだけではない。文学や美術の分野では比較的早い時期に「リアリズム」へと移行してゆくが、19世紀後半の音楽にそれと対応する作品はないのか?という疑問も当然起きてくるだろう。ことほどさように、「ロマン主義」を時代懸念として捉えると、さまざまな面で破綻が生じてくるのである。
2.ロマン主義は様式概念ではない:このテーゼは、前述のテーゼと対を成すもので、もっともロマン主義の本質を鋭く突いている。ロマン主義に固有の様式がないということは、音楽の分野でも容易に実証できることだが、ここではむしろ美術を例にしたほうが分りやすいだろう。美術史家の有川治男氏は、次のように述べている。「ロマン主義に様式がないということですが、それは工芸を見ればすぐに分る。ロマン主義に工芸はありません。ルネサンスにせよバロックにせよ、一つの様式的特徴をもった美術は、必ず工芸の分野でも独特のものを持っています。そもそも工芸は用と形の組み合わせですからね」―これ以上に明快な解答もないだろう。
画家と同じように、作曲家もまた一つの様式に基づいて創作するのではなく、過去のさまざまな様式を借りて曲を書いていったのである。意外に思われるむきもあるだろうが、たとえばショパンの『24の前奏曲』は、バロック時代のフランス風序曲の様式まで借りた〈様式の仮装行列〉と呼ぶことができるし、みずから革命家を自認したワーグナーも、ルネサンスの旋法和声を借りて『マイスタージンガー』の1節を書いているのである。
3.ロマン主義は古典主義に対する対概念ではない:これは今年の音楽祭のテーマ「1830年―ロマン派音楽の胎動」とも関係してくる。従来の歴史家は、つねに古典主義とロマン主義のあいだに一線を画そうと努め、〈理性(古典主義)〉に対する〈感情(ロマン主義)〉といった図式で、両者を強引に対照づけてきたのである。だがしかし、対概念によって割り切ることは、歴史的事実を裏切り、ひいては歴史の流れを無理にせきとめることになりかねない。
一つだけ文学の分野から反証を挙げるならば、ゲーテがその良い例だろう。もし、この古典主義を代表する作家が書いた『ファウスト』を古典的というならば、古典主義そのものの意味が怪しくなろうというものだ。つまり、古典主義者と呼ばれている人間がきわめてロマン主義的な作品を書くこともあれば、その逆もまたありえたのである。それは一人の人間のなかだけにとどまるのではなく、文化全体にも及ぶ。たとえば、「古典主義」と「ロマン主義」のあいだで現実に起こった〈滑らかな移行〉も、従来の歴史観ではとうてい説明がつかない事実と言えよう。
また1830年をロマン主義の「胎動」とする解釈も、こうした従来の歴史観によるものである。ベートーヴェンの死によって古典派にケリがつき、ロマン派のベルリオーズが『幻想交響曲』をひっさげて登場し、パリではヴィクトル・ユーゴーの『エルナニ』が熱狂的な支持を受け……と現象面では、たしかに説明しやすい。だが、ロマン主義はすでに1790年代から胎動を始めていたとみるのが、最近の研究者の一致した見解である。その意味で、むしろ1830年はロマン主義が沸騰点に達した「爆発」と捉えるべきかもしれない。
これは、音楽からも充分に説明できることだ。機能和声法、拍節法、主題・動機の労作……等々の音楽語法は、古典主義とロマン主義双方に共通している。ただ、すでにベートーヴェンの音楽がそうであるように、古典派の音楽語法の「定型」を故意に裏返して用いたのがロマン派の音楽である。作曲家は聴き手がこの定型になじんでいることを前提として、自分がこの定型から意識的に離脱したときには、聴き手がその効果を充分に評価してくれることを期待していた。シューベルトが『白鳥の歌』の〈影法師〉を空虚な響きで開始したとき、彼は、古典的な三和音を期待する「耳」を前提としていたのである。
さて、以上三つのテーゼはいずれも「~ではない」という否定形だったから、ここで最後に「ロマン主義」の意味するところを、できるだけ、具体的に絞り込んでおこう。すでに述べたように、「ロマン主義」は固有の様式を持ったエポックを指す用語ではなく、一つの〈世界観〉として捉えるべきである。その際、前提となるのは「かつて遠い昔に、世界のすべてが調和を保っていた時代があった」という原初的イメージではないか。そしてこのイメージから出発して、ロマン主義は次の三つのトポスを生み出す。すなわち、第一に時間的(過去)にも空間的(異国)にも遠く離れたものへの〈憧憬〉。第二に、その理想境から引き裂かれた現在の〈苦悩〉。そして第三に、この苦悩にみちた現実からの〈救済〉の願望である。
この三つのトポスはロマン主義芸術の、どの分野にも、どの作品にも繰返し現れる。絵画でいえば、カスパール・ダーヴィト・フリードリヒに代表されるように、ゴシックふうの教会あるいは修道院の「廃墟」(遠い過去)のモティーフが繰り返し画面に現れるのがよい例だろう。また音楽に引き寄せるならば、メンデルスゾーンの作風は絵画におけるナザレ派のごとく、遠い過去の音楽に規範を求めて無垢の響きを再現しようとしたものと言えよう。そして、シューマンの『子供の情景』もそれまでの標題音楽のように、単に現実の子供の世界を描写したものではない。この小品集は〈苦悩〉にみちた現実から逃避した、汚れのない過去への〈憧憬〉であり、最後が「眠り」すなわち一時的な死=〈救済〉で終わっているのも極めて象徴的だ。
もちろん、こうした解釈にはつねに恣意的に傾く危険性があるから、ここでショパンを例として「トポスと音楽語法の関係」について具体例を示しておこう。
ロマン主義の作曲家の特徴は、まずもって形式面には現れない。なぜならば、彼らにとって音楽は形式ではなく、内容だったからである。古典派の作曲家ベートーヴェンは形式に対して攻撃的な態度を取ったが、ロマン派の作曲家ショパンは「ABA’」といった古典的形式を素直に取り入れる―この一見逆説的にみえる形式に対する態度こそ、形式は容器に過ぎず内容で勝負というロマン主義の傾向を端的に語っているのだ。
たとえば、ショパンの『スケルツォ第1番』の冒頭にフォルティッシモとスフォルツァートで鳴らされる二つの和音は、それだけでロマン主義のトポスを体現していると言えよう。この二つの和音はいずれも鋭い不協和音で、高音域にある第一の和音と低音域にある第二の和音のあいだには、音域的なつながりはまったくない。あたかも悲鳴のような二つの響きのなかに、引き裂かれた自己の〈苦悩〉を読み取ることは容易であろう。
あるいは『バラード第2番』の冒頭。6/8拍子のリズムにのってカンタービレの旋律が歌われるのがだが、問題は最初に(古典派の旋律法に従えば)2小節余分に旋律の開始音が反復され、そのあとに初めて旋律が動き出すことである。つまり、それによって旋律の入りも終りも不確かなものとなり、始まりも終りもない無限の効果が生まれてくるのだ。この曲はバラードだから、この冒頭部は過去への〈憧憬〉を体現したものであり、同時に―アドルノ流に、過去への追憶が未来への回路に通じているとすれば―〈救済〉の願望もそこに込められていると見ることができよう。ロマン主義音楽の特徴は、まさにこうした「細部」に現れてくるものなのである。
三宅幸夫(1946~2017)
音楽学者。慶應義塾大学名誉教授。専門はJ.S.バッハの作曲技法、およびワーグナーを中心とする19世紀ドイツ音楽研究。当音楽祭のプログラムには、他に第15回(1994年)「あれか、これか?―シューベルトのピアノ・ソナタをめぐって―」、第17回(1996年)『「反発」あるいは「補完」?―ワーグナーとブラームス―』の寄稿がある。