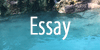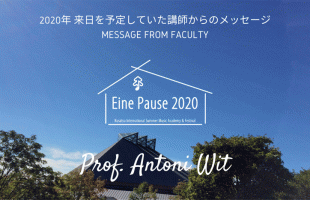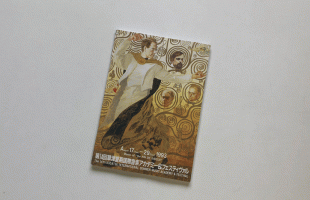文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:小宮正安
第32回プログラムより(2011年発行)
フランツ・リストが生を受けたライディグという町は、今日ではオーストリアの領土となっている。詳しく言うとオーストリアのブルゲンラント州に位置しており、この州は1921年に誕生した。だがリストが産声を上げた1811年10月22日当時、ライディングはハンガリーの領内にあり、しかもハンガリーはオーストリア帝国の一部に組み込まれていた。
1867年、オーストリア帝国の統治形態が変わり、新たにオーストリア=ハンガリー二重帝国が成立した。この新帝国では、オーストリア帝国とハンガリー王国が互いに独立した国家形態を保ちつつも、行政面においては部分的に共同統治をおこない、君主も二重の統治機能を担っていた。つまり時の皇帝フランツ・ヨーゼフは、オーストリア皇帝であると同時に、ハンガリー王となったのである。これぞ二重帝国と呼ばれる所以であり、わざわざオーストリア=ハンガリーと表記される所以なのだ。
なおオーストリア=ハンガリー二重帝国の誕生にあたり、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフとその后エリーザベトはハンガリー王ならびに王妃となるべく、オーフェン(現在のブダペスト)で戴冠式に出席した。時は1867年6月8日。式に際してはミサが挙行されたが、それにあたってミサ曲を作曲するよう要請を受けたのがリストである。というわけでこの時彼が作ったミサ曲には、「ハンガリー戴冠式ミサ曲」という副題が付けられた。
ただしリストがハンガリー人だったかといえば、けっしてそうではない。彼の両親はともに、ウィーンを取り囲むオーストリアの一地域、ニーダーエスタライヒの出身だからである。
父親であるアダム・リストはエーデルスタールという町に生まれ、その両親はゲオルクならびにバルバラ・リストという名前だった(この時の彼らの苗字は、ドイツ語風にListと綴られていた)。母親の旧姓はアンナ・ラーガーといい、ニーダーエスタライヒの中心地クレムスの出身。娘時代はウィーンで小間使いとして働いていた。いっぽう父親の方は長じてからは、故郷のエーデルスタールからさほど遠くないプレスブルク(現在はスロヴァキアの首都であるブラティスラヴァ、当時はハンガリーに属していた)で学業を修める。やがて1798年、ハンガリーの貴族エステルハージ侯に仕える官吏となり、政治、司法、経済の各分野で活躍した。そして最初の勤務地であるフォルヒテナウを振り出しに、アイゼンシュタット、そして1808年以降はライディングに住むようになった。これらの都市はいずれもハンガリーの領内であり、しかも当時のハンガリーはオーストリア帝国の一部だった。
なおライディングに腰を落ち着けたアダム・リストは、自分の苗字をハンガリー風にLisztと改めた。そして1810年アンナ・ラーガーと知り合い、1811年1月11日に結婚。同年10月22日に彼らの一人っ子として生まれたのがフランツ・リストである。
アダム・リストは音楽の才能にも恵まれており、多くの楽器を演奏することができた。時には、ヨゼフ・ハイドンやその後継者であるヨハン・ネポムク・フンメルが楽長を務めていたエステルハージ侯の宮廷楽団に、エキストラとして出演したほどである。
こうした事情もあり、アダム・リストは自分の息子フランツに音楽的才能があることを知るや否や、1822年に家族ぐるみでウィーンへと引越し、息子をカール・チェルニーやアントニオ・サリエリの下で学ばせることとなった。1824年になると今度はパリへ居を移し、さらなる音楽教育を息子が続けられるよう環境を整えた。フランツ・リストは父親の尽力によって神童として広く名を知られるようになり、父親とともに幾度となく演奏旅行をおこなった(イギリスにも3回渡っている)。いっぽう母親は1825年にオーストリアに戻り、最初は故郷のクレムスに、次いでグラーツに住んだ。そうこうしているうち、1827年8月28日に父親が死去。母親は再びパリへ戻り、1866年になるまで彼の地で生活を続けることとなる。
リストは1835年に愛人のマリー・ダグー侯爵夫人とともにジュネーヴに居を構えるも、1838年以降はヴィルトゥオーゾとして旅から旅への生活を送るようになり、1848年から61年にかけてようやくヴァイマルに落ち着いた。1861年から70年まではもっぱらローマを生活の中心とした。
演奏旅行の途上、リストはペスト(今日のブダペスト)や、他のハンガリーの都市でコンサートを開いた。だが彼とハンガリーの関係が、それ以上発展することもなかった。
例えばリストはハンガリー語を話せなかった。というのも彼は多民族国家オーストリア帝国の民であり、当時この帝国に存在する多くの民族と同様、もっぱら帝国の公用語たるドイツ語を話していたからである。
というわけで、リストはハンガリーよりもむしろオーストリア帝国への結びつきを折りに触れて示すこととなった。その典型こそ、1838年、時のオーストリア皇帝フェルディナントがコンバルディアならびにヴェネツィア王となった際、ミラノでの戴冠式に呼ばれた出来事だろう。しかもこの後彼は皇帝一家に客として招かれ、パドヴァに滞在すらしたのである。
というわけで、当時リストは「世界市民」と呼ばれていた。今風に言えば、オーストリアの旅券を所有したヨーロッパ人といえようか。さらに1859年10月30日には、時のオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフによってオーストリア貴族に叙せられた。といっても貴族になったからといって、実質的にさほどメリットがあるわけではなかったのだが。
リストのハンガリーに対する興味は、長い間単に音楽的なもの、しかも民俗音楽的な視点からのものにすぎなかった。ロマとその音楽について取り組み、ハンガリーの民族音楽、とりわけロマの音楽に影響されて数々のハンガリー狂詩曲を作ったり、ハンガリー行進曲を書いたりしたのはその頭な例である。
なお、外国からの圧制に対する革命音楽であったラコッツィ行進曲をリストがオーケストラ用とピアノ用に編曲したのは有名なはなしであり、これによって彼はハンガリー国内では自国と密接な関係にある作曲家と見なされるようになった。ただし当人としては、本作を通じてハンガリーの独立を訴えるつもりなど毛頭なく、単にハンガリーの伝統に影響された音楽を手がけたにすぎなかったのである。
こうした出来事に見られるように、リストがハンガリーの音楽を好んでいたという事実は、広い視点から捉えるべき問題なのだろう。たしかにハンガリー音楽に寄せる彼の嗜好はきわめて強いものがあったが、一方でフランス、ボヘミア、ポーランド、イタリアやスイス、果てはアフリカの音楽に至るまでその興味と嗜好が尽きることもなかった。つまりリストとしてみれば、自分にとって異質な音楽の全てに関心を抱き、それらを好んだのだった。
ただしハンガリーにおいて、リストに対する見方はまったく異なっていた。ハンガリーの地に生まれた世界的ピアニストにして作曲家、そしてハンガリーの音楽に興味を抱いていた人物として、彼は人々にとって誇るべき存在となったのである。
例えばペスト(今日のブダペスト)の国民劇場でリストが演奏会をおこなった時のこと。ハンガリーの貴族たちは、本来貴族にのみ帯刀を許されているサーベルを彼に対し特別に贈った。そしてこの象徴的な出来事により、リストは貴族と同等の人物と見なされるようになったのであった。
そうでなくてもリストは、ハンガリーの側から事あるごとに顕彰されることとなった。こうした動きに対し、彼の側も別段固辞する理由などなくとりあえず応じてはいたものの、それでもあくまで中立的な立場を貫いていた。
ようやくリストがハンガリー側からの働きかけに応えるようになったのは、1870年代になってからである。1871年、彼はハンガリー王国の頭問官に任命された。もちろんそれは名誉称号であったものの、4000グルデンの特別年金が支給されるというものだった。またその2年後、ブダペストに音楽院を作る決定がなされるが、その院長としてリストの名が挙がり、彼もまたそれを受諾した。同年、かつて神童時代のリストがペスト(現在のブダペスト)で初舞台を踏んでから50年経ったことを祝い、ブダペストでは大々的な祝典がおこなわれた。ちょうどこの時オーストリア皇帝夫妻もブダペストに滞在していたが、彼らはハンガリー王夫妻でもあるという立場から、リストをブダペストにあるみずからの居城へと招待した。
さらにハンガリーの音楽家や政治家、貴族たちは、国際的な音楽シーンにおいてリストをハンガリー人として売り出そうと画策した。結果、リスト自身も彼らの熱心な願いを受け容れ、1878年に開催されたパリ万博においてハンガリーの楽器を展示するための審査委員を務めたのである。
1881年、リスト自ら先導役をつとめてきたブダペスト音楽院の新校舎がついに完成、建物の中には彼専用の住まいも作られた。そしてこれ以来彼は亡くなるまで、年の始めの2・3ヶ月をブダペストで過ごすこととなる。なお夏の間(つまり1年のうちもっとも長い期間)は、ヴァイマルに滞在するのが常だった。それどころか1883年には、4月8日から翌84年の1月31日まで彼の地で過ごしたほどである。その他の期間については、ローマやウィーンに逗留したり、旅をおこなったりするのが常だった。
リストはウィーンにおいてもこの街の人間と見なされていたし、ヴァイマルにおいても同様だった。また別のいくつかの場所…特に伝記上重要とされるのは、ライン河上流域のラインタールに位置するノンネンヴェルトである……については、そこに定住しようと考えたことさえあった。ローマでは1865年に下級聖職者(僧侶の予備段階)に叙せられ、アッペと称するようになって以降、この街に非常に親しむこととなった。
ではハンガリーについてはどうかといえば、仕事の拠点にしようと考えたことこそなかったものの、リストはこの地での滞在を満喫し、ハンガリーが自分を大事にしてくれていることを如実に感じ取っていた。それどころか、ハンガリーの民族衣装を仕立てて嬉々としたり、ハンガリーの音楽家や組織を支援したり、晩年には自らのためにプダペストに作られた住まいを利用したりしたほどである。
1842年以来、リストはヴァイマルにおいて特任の宮廷楽長となった。これは名誉職的なポジションだったが、1848年になると宮廷楽長として現場で実際に活動することとなり、それは1861年まで続いた。さらに1869年以降、多方面に渡る活動や義務から逃れ一休みするための場所として、彼はこの街を毎年訪れるようになった。
ヴァイマルという街は、一方では文化の中心でありながら、もう一方ではこぢんまりとしており、何かと面倒臭い社交的義務からも自由だった。街の人々もリストが滞在してくれることを誇りに感じている一方、彼に対して何かを求めることなく、創作意欲が回復するようそっとしておいてくれた。このような環境は、年老いたリストにとってありがたく、他の場所では得がたいものだった。しかも、彼の娘のコジマがリヒャルト・ワーグナーと結婚後に住んだバイロイトから、ヴァイマルが程遠くない場所に位置しているということも重要であった。
ただし音楽界から完全に身を引いてしまうことなど、リストにはできなかった。1861年にヴァイマルの宮廷楽長を辞してからは一定のポストに就くことはなく、1846年以降公開の場にピアニストとして登場することもなかったにもかかわらず、である。そうした観点から見ると、音楽の中心地ウィーンは彼にとって特に重要な地であった。1838年、39年、そして46年にウィーンでおこなった演奏会は、リストのピアニスト人生にとってハイライトとなった。1856年にモーツァルト生誕100年の記念演奏会で指揮をおこなった際には、多くの物議が醸されるいっぽう、彼を偉大な指揮者と認識する人々も誕生したといえよう。
じっさい、まさしくそうした人物としてリストはウィーンを度々訪れた。年を追うごとにウィーン楽友協会との関係は密接になり、同協会における指導的役割も増した。楽友協会主催の音楽会では、後期の作品を自ら指揮したほどである。ベートーヴェン記念像の除幕式に際して招待を受けたことも象徴的な出来事ならば、1846年以来はじめてピアニストとして登場しベートーヴェンのピアノ協奏曲を演奏したことはさらに象徴的だった。
重要なのは、リストがウィーンでの生活全般の多くを、叔父のエドゥアルト・リスト博士に負っていたという点だろう(エドゥアルトはリストより6歳年下であったにもかかわらず叔父であり、1879年に亡くなった)。エドゥアルトは住まいの一部を、いつでもリストが使えるよう手配し、整えておいてくれた。経済や法律や組織といった諸事についても、エドゥアルトはリストを支援した。エドゥアルトのもとでリストは、ウィーンやヴァイマルの友人たちのもとにいる時のようにくつろぐことができた。つまりそこにいれば、彼は世界的な巨匠としてではなく、愛すべき一人の人間として扱ってもらえたのである。
リストがファンから度を越して「追っかけ」をされるような時、エドゥアルトはリストを置いて、そっとしておくことに力を注いだ。それどころか1度は、リストを逃亡させたほどである。この時リストはわざと人目につくよう、旅行馬車でエドゥアルトの家を出発した。ところが馬車はウィーンのすぐ郊外まで差し掛かると、再びリストを乗せたままウィーンへととって返した。こうして馬車の窓のカーテンをかたく閉ざしたまま、リストは夕方にはエドゥアルトの住まいに戻っていたのである。リストはもはやウィーンにいないと一般の人々が思っていたころ、エドゥアルトとリストは実は既に市中で顔を合わせていたというわけだ。
ピアニストとして活動していた若き日のリストはウィーンにおいて、国際レヴェルのピアノの名手たちと比較されることとなった。というのも当時この街ほど、ピアノの名手が活躍した場所もなかったからである。ショパン、クララ・ヴィーク、ジークムント・タールベルクといった具合に、綺羅星のような存在が並び立ち、ウィーンで名声を得ることはヨーロッパ中に轟く名声を得るための重要な足がかりだった。
また当時のウィーンは、ヨーロッパにおけるピアノ製造業の中心地だった。リストはコンラート・グラーフやヨハン・バプティスト・シュトライヒャと個人的関係を持ち、後にはかのイグナツならびにルートヴィヒ・ベーゼンドルファーとの付き合いを通じ、きわめて大きな影響と刺激を受けるようになる。
指揮活動をおこなったり、ワーグナーやブルックナーを中心とする新ドイツ楽派の一人に数えられるようになったりして以降、ウィーンはリストにとってますます神聖かつ重要な地点と化した。ブラームスを持ち上げる一方でワーグナーやブルックナーをこき下ろすような批評が巻き起こると、後者の評価をまっとうなものにすべくリストは一大キャンペーンをおこない、それはウィーンを超えて絶大な成果をもたらした。その一方で1882年には、ハンス・フォン・ビューローの出演するブラームスの演奏会を訪れ、大いに感銘を受けている。ウィーンにあっては、単なる流派や楽派の違いを超越したところに芸術家が存在していた……、そのもっとも美しい出来事の一つであるといえよう。
リストとウィーンとの結びつきということで言えば、彼がこの街で生涯にわたる重要な出版者を見つけたことも忘れてはならない。1824年、神童として鳴らしていた13歳のリストに、アントン・ディアベリが声をかけてきたのである。ディアベリは自らのところで出版している変奏曲の楽譜を充実させるべく、有名かつ優れた作曲家に対し自作のテーマによる変奏曲を書いてくれないかと打診を繰り返しており、リストにも白羽の矢が立ったのだった。ひょっとするとこの出来事こそ、リストがはじめて作曲家として認識された最初だったかもしれない。
その15年後、今度はトビアス・ハスリンガーが、リストがウィーンで編曲したラコッツィ行進曲を出版した。この行進曲はハンガリー革命の際に歌われた古いメロディに基づいており、それを公にすることは当局から禁じられていたのだが、ハスリンガーは検閲官を次のように説得して出版にこぎつけたのである。日く、リストの芸術はそうした否定的な政治的状況を忘れさせてくれるほどの力がある、というものだった。
その他にも、リストの作品を出版したウィーンの出版者については枚挙に暇がない。ウィーンの楽譜出版者は、作曲家リストにとって特別に重要な存在であり続けたのだった。
リストはハンガリーの側からは自国の音楽家と受け止められ、そのように喧伝されていたものの、それがウィーンで真に受けいれられることはまったくなかった。人々はリストに好意的であって、ウィーンこそ彼のルーツの源であり、華やかな特徴を最大限に発揮できる場所であることを知っていたのである。
じっさいウィーンで活躍した数々の作曲家を見るに、ロマの音楽に感激し、そこから霊感を受けたのはリスト一人ではない。それはウィーンの音楽的伝統であって、少なくともヨゼフ・ハイドンにまで遡ることのできるものだったのである。彼もまた、ハンガリーのあるいはロマのメロディに基づいて作曲をおこなったほどなのだから。
ウィーンではロマの楽団も活躍しており、大編成で演奏会をおこなったり、小編成で飲食店や野外のアトラクションに出演したりしていた。そして、リストも当然のようにウィーンでこうしたロマの音楽を体験し、それが彼の創作に大きな影響を及ぼしたのである。重要なのは、ロマの楽師の中でも優秀な人々はウィーンを目指したという点だ。というのもハンガリーではロマの音楽はあまりに日常的な存在であって、さして見向きもされなかったため、名声を得たり金を稼いだりしたければウィーンへ出て行く必要があったのである。
つまり相矛盾するかのようだが、ハンガリーのあるいはロマの音楽はハンガリー以外で有名になり、その重要拠点こそウィーンだった。こうした傾向はリストの世代にあっても、また彼よりも年下のヨハネス・ブラームスの世代にあっても同じであった。ブラームスも主にウィーンでロマの音楽のメロディに親しみ、それを自作のハンガリー舞曲へ採り入れたのである。
若き日のリストはウィーンにおいて、ベートーヴェンの弟子であり彼の信頼を一身に受けていたチェルニーからピアノを学び、フランツ・シューベルトを教えたことのあるサリエリから作曲を習った。それによって彼は、ウィーンの音楽的伝統のルーツをその根本に至るまで会得できた。
なおこの経験は、リストの人生にとって大きな意味を持つこととなった。彼がシューベルトの歌曲をピアノ独奏用に編曲したり、あるいは華やかな演奏会用作品(シューベルトのワルツ・カプリースに基づいて書かれた「ウィーンの夜会」)を作ったりしたことは、何よりの証拠である。たしかにリストはシューベルトの使徒として、彼の作品を世に広めることに成功した。と同時に演奏家としての彼は、ベートーヴェンの使徒でもあった。彼のピアノ演奏は全ヨーロッパを魅了し、模範的と評価されたわけだが、師がチェルニーでありさらにその師がベートーヴェンであったことを考えると、それはけっして不思議でも何でもないといえよう。
にもかかわらず、リストを指して典型的なオーストリアの作曲家とは言いがたい。ましてや、典型的なハンガリーの音楽家などとはとても言えない。たとえかの有名なハンガリー狂詩曲を作曲し、それらが実にハンガリー風に聞こえたとしても、やはり彼はハンガリーの作曲家ではないのだ。というよりもむしろ、例えば交響詩や、実験的かつ未来を先取りしたような後期の声楽曲、ピアノ曲、オルガン曲など、リストの作品には他にも重要なものがいくつもあり、しかもそれらはさほど一般的ではないときている。そしてこれらの作品に耳を傾けると、オーストリア的な伝統はおろか、ハンガリー的な影響など一切存在しないことが分かるのだ。
しかもこうした音楽を通じ、リストははじめて自らの目的を達成できたといえるかもしれない。師のチェルニー、しいていえばウィーンにルーツを持つヴィルトゥオーゾ的で派手なピアノ作品は、今も昔も既に充分すぎるほどの名声を得てきた。だがまさに、この伝統路線・ポピュラー路線を外れ、未知の領域に新たな一歩を踏み出した瞬間、リストはきわめて実験的で未来的な音楽にわが道を見出せたのである。言葉を変えれば、この新たな一歩のためにこそ、初期の伝統路線・ポピュラー路線が存在したともいえよう。逆に聴き手の側としても、ウィーンの伝統とハンガリーのメロディに心動かされていた時代のリストを知ることで、型破りで実験性に富み、未来音楽の様々な形態に惹かれていった後期のリストを理解し、正しく評価できるのではないか。
今日リストといえば、もっぱら超絶技巧のピアノ作品か、ハンガリーの民族音楽……というよりもハンガリーにいたロマの音楽……からインスピレーションを受けた作品によって有名である。だがそれらは、彼の創作のほんの一部でしかない。だからこそリスト・イヤーとなる2011年は、リストの全貌を知りうるまたとない機会なのである。