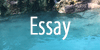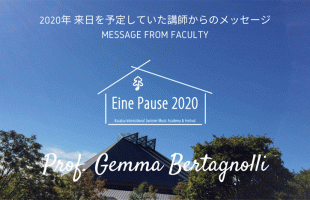文:オットー・ビーバ/日本語翻訳:武石みどり
第25回プログラムより(2004年発行)
音楽史の中で、バロックと古典派にかけての時代ほど刺激的で多様な時代はない。それは、ある様式から次の様式へのゆるやかな移行でも、一般的に認識可能な論理的発展でもなく、探求と実験の時代であった。
バロック音楽の語法の可能性が使い尽くされて時代の終焉が意識されたときから、新しいものの探求が始まった。これはすべての場所で同時に始まったのではなく、ある作曲家は早い時期から、他の作曲家はそれより遅く、またある所では集中的にさまざまな実験が行われる一方で、別の所では保守的な傾向が続くという具合にまちまちに進行した。
ヨーロッパで、作曲家たちが特に集中的に新しいものと取り組んだ拠点は三ヶ所である。前古典派様式が見事に花開いたドイツ選帝侯国の首都マンハイム(若きモーツァルトがマンハイムに旅行したのは、まさにその理由による)、そしてバロックと古典派の形式的・様式的なあらゆる実験が行われたウィーンとロンドンである。(ウィーンは、ヨーゼフ・ハイドンとミヒャエル・ハイドンの兄弟、そしてモーツァルトといった今日でも有名な作曲家たちが出現したという点で、ロンドンよりも一歩抜きん出ていた。)しかしまた、例えばベルリンとハンブルクで活動したカール・フィリップ・エマヌエル・バッハのように、上記の三都市とは離れたところで孤立して新しい道を切り開いた作曲家たちもいる。
では、バロックから古典派にかけて重要な様式の方向性とはどのようなものだったのであろうか?
第一に、バロックの要素を基本的に破ることなく、そこから新しい発展を求めた―言うならば、バロックという土台の上にバロック風でない家を建てようとした―作曲家たちがいた。これが、いわば後期バロック様式、あるいはバロック後派である。
第二に、バロックの殻を完全に打ち破り、まったく新しいことをしようとした作曲家たちもいる。前古典派と呼ばれる人たちである。彼らの問題点は、古典派の基礎を築いたものの、本当の古典派様式にまで到達する強さがなかったことである。彼らは古典派という山の頂上への道を知っており、それを指し示すことはできたが、自ら頂上に至ることはできなかった。カール・シュターミツ(マンハイム)とゲオルク・マティアス・モン(ウィーン)は、この方向性の作曲家として今日最も有名である。モーツァルトの初期の交響曲も同じ方向性を示しているが、しかし、モーツァルト自身は古典派の頂点に素早く簡単に到達した。だが、頂点を極めなかったとはいえ、これら前古典派の作曲家たちを過小評価すべきではない。アルノルト・シェーンベルクは、ゲオルク・マティアス・モン作曲のチェロ協奏曲に非常に魅了され、現代的な演奏習慣に合わせて編曲・出版したほどであった。
第三の方向性に属する人々は、自分たちが目標を見失った根本的な変革の時代、古い規則が効力を無くしたがまだ新しい規範が存在していない、あるいは存在しても認識できない時代にあることを感じていた。彼らは若く大胆な「革命家」であり、聴衆の期待など考えに入れず、むしろあえて聴衆にショックを与えた。有名な音楽学者H.C.ロビンズ・ランドンは約40年前に、こうした音楽の方向性を「シュトルム・ウント・ドラング(疾風怒涛)」と名づけることを提案した。ドイツ文学史では、文学の分野で前述の作曲家のような姿勢を示した詩人たちを、以前からそう呼んできたのである。そこでランドンは、ドイツ文学史の概念を音楽にも援用しようと考え、この40年の間にこの用語は定着した。音楽的な「シュトルム・ウント・ドラング(疾風怒涛)」様式の典型的な作品は、モーツァルトの交響曲ト短調KV183である。
第四に、これとは反対に非常に穏やかな傾向の人々も存在した。彼らは感情豊かで多感な時代の代表者である。バロック時代の厳格な作法や硬直した儀式性は、もはや日常生活には存在しない。多くの人々が、感情と感覚、欲望と気分、情緒と憧れに導かれて生活できることに喜びを感じていた。このことは、多くの作曲家の音楽にも表されている。若きハイドンが作曲したディヴェルティメントの緩徐楽章は、そのみごとな曲例である。
これら四つが、この時代に最も重要な方向性であった。もちろん、多くの作曲家においては複数の方向性が重なり合い、組み合わせられ、さらに個人的に変形もされている。これら四つの方向性は、新しく確立される古典派様式の発展にそれぞれ重要な役割を果たした。
これらの方向性が現れたのは1740年から1780年にかけて、すなわちヨハン・セバスティアン・バッハの作曲家となった4人の息子が活動していた時期のことである。
ヨハン・セバスティアン・バッハは二回結婚している。最初の結婚では、三人の息子が成人した。そのうちヨハン・ゴットフリート・ベルンハルト・バッハは、1739年に24歳で亡くなっている。彼は音楽的に高い才能に恵まれていたが、非常に落ち着きのない性格で、音楽的な職務に就いて働く決心がつかなかった。特に注目すべき作品は残していない。
ヨハン・セバスティアン・バッハの長男ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ(1710~1784年)もまた、音楽的な才能に恵まれていたものの落ち着きがなく、長い間職務に就くことを望まず、むしろ制約のない放浪的な生活様式を好んだ。この奇妙な性格の故に、オルガニストとしての職はいずれも長続きせず、1764年以降は定職に就かなかった。あちこちを放浪し、落ちぶれた天才として、自分の才能を本当に開花させることなく世を去った。彼の作曲様式は、その性格と同様に移り気である。その作品にはバロック後派、シュトルム・ウント・ドラング、および多感様式の傾向が、すべて芸術的に高い水準で混在している。その天才的な才能のゆえに父ヨハン・セバスティアン・バッハのお気に入りであったという言い伝えは、おそらく本当のことであろう。
ヨハン・セバスティアン・バッハのその次の息子は、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(1714~1788年)である。彼はベルリンの王室に勤め、1767年以降ハンブルクの教会の音楽監督となった。カール・フィリップ・エマヌエル・バッハは、シュトルム・ウント・ドラングの典型的な巨匠であるが、同時に多感様式の多くの特徴をも具えていた。特に鍵盤作品の作曲様式は新しく、非凡で未来志向的であった。ベルリンでもハンブルクでも、彼は人々に尊敬され、落ち着きと威厳に満ちた人物であった。彼が著した教科書「クラヴィーア奏法試論」は、19世紀の後半に至るまで用いられている。
ヨハン・セバスティアン・バッハの二回目の結婚では、二人の息子が成人した。二回目の結婚で得た最初の息子、ヨハン・クリストフ・フリードリッヒ・バッハは、ヨーゼフ・ハイドンと同じ1732年に生まれた。しかし、彼の音楽はハイドンほど先進的ではなかった。モーツァルトが生まれた年、1756年には、ハイドンと同じように侯爵家の楽長となった。しかし彼が勤めたのは北ドイツの小さな侯爵家で、芸術的影響力と財力の点でエステルハージ侯爵家には及ぶべくもなかった。バッハの息子たちの中で、彼は典型的な前古典派である。モーツァルトの死の4年後、1795年に亡くなった。
バッハの末息子ヨハン・クリスティアン・バッハ(1735~1782年)は、主にミラノで活動し、1762年以降ロンドンで活躍した。彼は、あたかも歌手がアリアを歌うかのように旋律がすべての音楽を支配している器楽曲の急速楽章、すなわち、いわゆる「歌うアレグロ」を発明した。そのようなアレグロ楽章は、モーツァルトの作品にも見出される。ヨハン・クリスティアン・バッハは、―頂点を極めなかったにせよ―前古典派の最盛期の作曲家の一人である。それに加えて、多感様式の傾向も少し見られる。若きヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、ヨハン・クリスティアン・バッハのさまざまな作品を自らの勉強のために編曲したが、それは同時に、彼がいかにこの作曲家を模範として高く評価していたかを公に示すものでもあった。
このように、ヨハン・セバスティアン・バッハの息子たちは皆、バロックと古典派の間の時期に重要かつ典型的であった四つの様式的方向性のうち、少なくともどれかを代表している。従って、今回の草津夏期国際音楽アカデミーでこの時代の代表としてバッハの四人の息子を紹介し、バロックと古典派―あるいはヨハン・セバスティアン・バッハに始まりルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェンに至るまでの、目標が定かでなく紆余曲折の多い発展―の間に位置する者として示すことには、大きな意味がある。
ヨハン・セバスティアン・バッハの故郷、および彼が活動した主な場所、すなわち中部・北部ドイツでは、その作品はすぐに忘れられてしまった。バッハの名前を覚えていた人はいたが、作品が演奏されることはなくなった。これに対して、オーストリアではバッハの作品が(少なくとも部分的に)演奏され続けた。オーストリアでは、新しいものに喜びを感じ新様式の試行錯誤で成果を得る一方で、伝統にも敬意が払われたからである。間違った進歩主義が主張される中で、人々は古いものを根本から無視したわけではなかった。特にヨハン・セバスティアン・バッハの作品は教育用・学習用に好んで用いられた。『平均律クラヴィーア曲集』のフーガは、モーツァルトを含む多くのウィーンの作曲家によって1780年代と1790年代に弦楽合奏用に編曲され、前奏や序奏を付けて演奏された。これらの編曲では、興味深いことに、バロック時代のフーガがまったく新しい様式の序奏と組み合わせられている。
ここでフーガについて一言。ウィーンの音楽の典型的な特徴は、フーガという形式が時代遅れになることがなかった、ということである。古典派の音楽においても、フーガは声楽曲や器楽曲に用いられた。バロック時代の遺物としてではなく、音楽的な表現手段として、また作曲家の能力の試金石として通用していた。ヨハン・セバスティアン・バッハの作品ほどフーガ作曲の勉強によい教材は無い。古典派のフーガは、もちろんバッハのフーガよりも和声的に複雑である。フーガの作曲が当たり前であったバロック時代とは違って、古典派ではフーガが特別な意味をもっていたため、時にはバロック時代のフーガよりも技巧に満ちたものが作られた。古典派においては、厳格な規則に従った通常のフーガはそれほど求められず、作曲上の規則を守る以上の表現が求められた。他の場所ではフーガへの関心が薄れてしまったのに対して、ウィーンでの要求は高かったことになる。その意味で、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの三人は、バッハの息子たちに優る興味深いフーガを書いている。そのことから、バロック音楽の典型的な形式であるフーガが、ウィーン古典派においても確固たる地位と重要性を占めていたことを確認できる。フーガが最も頻繁に見られるのは、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、およびウィーンの同時代の作曲家たちの、オラトリオ、ミサ曲、室内楽作品であった。
これらの三大巨匠がヨハン・セバスティアン・バッハについて研究していたことは、よく知られている。モーツァルトはすでに子供の頃、ザルツブルクでバッハの作品を知った。ハイドンはウィーンで、ベートーヴェンは生誕地ボンで少々、次にウィーンで集中的にバッハを勉強した。ベートーヴェンがバッハの作品を勉強するために書き写した手稿譜は、現在も大部分がウィーン楽友協会資料室に残されている。ハイドンとモーツァルトの友人であり、ベートーヴェンの先生であったヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーは、バッハの『音楽の捧げ物』を研究し、『ロ短調ミサ曲』のクルチフィクスに見られる作曲技法上のアイデアを自身のミサ曲に応用した。ハイドンはその楽譜蔵書の中に『ロ短調ミサ曲』全曲のスコアを所蔵しており、また1800年頃にはオーストリア皇帝フランツの楽譜蔵書の中に『ヨハネ受難曲』のスコアがあったことが記録されている。約16年後、ウィーンでこの作品の初演が行われた。ベートーヴェンも『ヨハネ受難曲』に取り組んだ。彼がバッハを研究していたことを知って、初めて『ミサ・ソレムニス』の細部の意味が明らかとなる。
1791年、モーツァルトが大聖堂の楽長という新しい地位の獲得を目指して(これは、彼の突然の死により実現しなかった)、新たにバロックの模範を研究し始めた。ミサ曲ではフーガが不可欠とされているように、新しい職に就いて教会音楽を作曲する際、バロックの作品が模範として役立つからである。『魔笛』のような新しい様式の作品においてさえ、バロック時代のコラール旋律やフーガ的な部分(すでに序曲に見られる)、厳格な規則に従った書法が見られる。新しい様式を求めつつバロックの伝統を守ることは、モーツァルトにとっては相反することではなかったのである。
もちろん、モーツァルトが1789年にベルリンへ旅行した際、ヨハン・セバスティアン・バッハに思いを寄せ、その活動の場を訪ねるためにライプツィッヒに立ち寄ったことも、忘れてはならない。バッハがカントルを務めていたトーマス教会を1789年4月22日に訪ね、そこでバッハが生前に弾いたオルガンを弾き、バッハの弟子ヨハン・フリードリッヒ・ドーレスからバッハの人柄と作品について話を聞いた。ライプツィッヒでは、当時すでにバッハの作品は演奏されていなかった。モーツァルトはカンタータ『主に向かって新しい歌を歌え』の筆写スコアをウィーンに持ち帰り、その楽譜に、オーケストラ用に編曲したいという希望をメモ書きしている。このスコアは、今日ウィーン楽友協会資料室に保管されている。残念ながら、モーツァルトは計画していたオーケストラ編曲を実行することができなかった。
ベルリンでは、フェリックス・メンデルスゾーン=バルトルディがヨハン・セバスティアン・バッハを再発見した。だが、ウィーンではバッハを再発見する必要はなかった。バッハの作品が演奏され続けていたからである。そのジャンルは、教会音楽や鍵盤曲、オルガン曲ばかりでなく、室内楽にも及んでいたため、そこから直接ハイドンの弦楽四重奏曲のフーガ楽章やベートーヴェン後期の弦楽四重奏曲へとつながっていった。これらのフーガ楽章は、回顧的なもの、ひからびた学問的なものを感じさせることが多い。しかし実際には、非常に活発な伝統を示す生きた証拠なのである。
ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの時代、ウィーンでヨハン・セバスティアン・バッハに取り組んでいたのは作曲家たちだけではない。当時あまり出版譜の出ていなかった有名なバッハ作品の楽譜を収集している人たちもいた。ヨーゼフ・ハイドン作曲のオラトリオ『天地創造』と『四季』の歌詞を作ったゴットフリート・ファン・スヴィーテンは、そのようなバッハ・コレクター、あるいはバッハ信奉者の一人と言われている。事実、モーツァルトはスヴィーテンの家を何度も訪れ、そこでバッハの作品をたくさん演奏したと、手紙に書き残した。だが、スヴィーテンはバッハ信奉者というより、むしろもっと新しい音楽に興味を抱いていた。若い頃には、個人的な知り合いであったカール・フィリップ・エマヌエル・バッハに熱中し、また後にはベートーヴェンの交響曲第一番の献呈を受けている。これは、その作曲様式があまりに新機軸であるため、聴衆にショックを与えたといわれる曲である。
ヨハン・セバスティアン・バッハの作品のうち、古典派時代にウィーンの出版社から初版が出された作品は少なくない。こうした出版譜により、バッハの作品はどんどん各地に広まった。バッハ作品の出版に最も貢献した有名な出版者といえば、ベートーヴェンの弟子カール・ツェルニーであろう。ツェルニー自身の鍵盤作品は新しいギャラント様式であった。しかし同時に彼は、バッハのような古い基礎的な作曲法とバッハの作品を知ってこそ、そのような新しい様式の作品を書くことが許されることを強調している。彼自身がその条件を満たしていたことは、彼の最初のクラヴィーア・ソナタのフーガ楽章によって証明されている。
これに関連して、1824年以降ウィーンの宮廷オルガニストを務め、フランツ・シューベルトやアントン・ブルックナーを指導した人物、ジーモン・ゼヒター(1788~1867年)についても指摘しておかねばならない。彼は若い頃にベートーヴェンを知り自分の作品を献呈した。ゼヒターは対位法の教師として有名であった。対位法の作曲技法を通して、彼はバロックの伝統を高い水準で19世紀後半にまで保ち、古い規則と新しい和声のアイデアとを結びつけた。若きブラームスも、バロック時代の模範に基づくゼヒターの音楽理論教科書を用いた一人である。やや若い同時代人としてベートーヴェンからも高く評価されたゼヒターは、古典派の中で育ち、バロックとロマン派、さらには後期ロマン派を結ぶ役割を果たした。注目すべきことに、彼はまた、モーツァルトの『ジュピター交響曲』最終楽章のフガート部分の分析を最初に記述した人物でもある。バロック時代のフーガの技法と古典派のソナタ形式楽章について彼が説明したことは、今日に至るまで通用している。
古典派の作曲家たちはバロック時代の様式を排除し、自分たちで見出した古典様式へと置き替えていった。このような過程にありながらバロックの伝統が完全に否定されることがなかったのは、ウィーンでのみ可能な現象であった。まったく異なる文脈ではあるが、聖書には「すべてのものを識別して、良いものを守り(なさい)」という言葉がある。いうならば、ウィーン古典派の音楽家たちはこれを実行したことになる。彼らはバッハを最も有名で重要な先達と認め、それを忘れることなく守ったため、バッハを再発見する必要もなかった。彼らはフーガのようなバロックの形式を新しい生命で満たし、さらに展開し変化させた。彼らは古いものを軽蔑し、せせら笑って脇に押しやるのではなく、尊敬の念をもって乗り越えることによって、初めて後世に残る価値ある新しい作品を生み出すことができると知っていたのである。ウィーンでは、バロックと古典派の間の試行錯誤と新しい発展の時期が特に多彩で刺激的であったために、人々は性急に結論を出すことなく、新しい方向性を熱心に探求した。その結果、古いものの価値が慎重に試され、古い様式の細部が変形されて新しい様式へと組み入れられたのである。
この様子は、ウィーンという街の姿にも似ている。ウィーンでは18世紀の建物は比較的少なく、多くは19世紀の建物である。19世紀の建物は特徴的な新様式で、見た目に近代的である。しかし、バロック時代の建物と19世紀の建物、さらには19世紀のネオ・バロック様式の建物が、調和しながら隣同士に並んでいるのである。そして、今日ウィーンの街を訪れる人々は、あえて一つ一つの建物に様式と時代の境界線を引こうとはしない。このように新旧両様式の建物が入り混じっている様子を目にして楽しむのである。