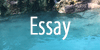文:井阪 紘
ウィグモアホールでの再会の後は、1982年にしばしばチューリヒ郊外ツミコンの自宅を訪れたり、フランクフルトのアルテ・オーパーでの彼女のマスタークラスを見たりと、ともかく私は彼女に会いに行った。それは1983年の秋に、日本でシュヴァルツコップによる草津の秋期特別マスタークラスを計画していたためで、私にとっては初めて彼女とする仕事であり、日本でこのプロジェクトをぜひとも成功させたかった。マスタークラスは、10月15日大阪のザ・シンフォニーホールを皮切りに、17日に東京の練馬文化センター、そして21日から4日間、草津の天狗山レストハウスという都合6日間で、草津では2時間半の公開講座を朝夕2回、都合10回というハードなスケジュール。それをシュヴァルツコップは精力的にこなした。

1983年10月15日大阪ザ・シンフォニーホールにて
オーディションは確か来日したその夜に行なうはずが、彼女が風邪気味だったかで予定を変更したために、急遽会場を音楽の友ホールから新宿の村松楽器に移して行なった。応募者だけで120名以上いたと記憶している。それほどに、当時もシュヴァルツコップの名前は音楽学生にも一般の音楽ファンにも鮮烈で、憧れの人であった。中にはオーディションで30秒も歌わせてもらえなくても、会って話をしただけで満足だといって帰った人もいた。多数の応募者の中から、彼女は8人の生徒を選んだ。
選ばれた受講生の中には、すでに現役で活躍していた秋山恵美子や岩淵嘉瑩といった人もいたが、当時東京藝術大学の大学院生だった小濱妙美さんには、その後シュヴァルツコップを追いかけてドイツに移り住み、ツミコンの自宅で週末にレッスンを受けるようになるほどの運命的な出会いとなったようだ。
もうひとつ、音楽の友ホールで計画していた彼女の「ヴォルフ歌曲について」と題した講演会では、ご主人のウォルター・レッグが若い頃に作った「フーゴ・ヴォルフ協会」による1932 年の録音等からEMIで7枚のLPに収められたレコードがあるから、それを用意するようにと来日してから言われた。そのLPは日本ではついに発売されなかったもので、苦労してやっと東芝EMIに頼んで手元に取り寄せた。そして、肝心の講演予定日を彼女は14日から19日に変更したいと言い出し、その調整をするのは大変な作業であったが、何せ言い出したら聞かないから、これも「はい!」とふたつ返事で従った。
おもしろかったのは、この講演会で彼女はほとんど自分が歌ったレコードは使わなかったこと。自分の師であるマリア・イヴォーギュンやジョン・マコーマック、エリザベート・シューマンなどの録音を聴かせて、詩の中にある言葉のイメージと表現を、過去の歌手がどのように実現させてきたかを語った。
草津の4日間では、白井光子さんが風邪で声が出なくなってコンサートをキャンセル。でも、NHKがこの4日間をテレビに収録して年末に放送したのがよい記念となった。
当時、マスタークラスを主催した財団にお金がなかったため、草津までの道のりを、私の親友でこの音楽祭のピアノ調律師だった小林禄幸氏の車にシュヴァルツコップと同乗して移動した。その車中で彼女とは終始英語でいろいろ話したのだが、いつも私が話すと「LとRの発音が悪い!」と直される。気をつけて話をすると「今のRの発音はよかったわ」と言って、リンツのスイス製チョコレートをご褒美にくれた。ともかくその時は、ご主人レッグのこと、ジェラルド・ムーアのフェアウェルコンサートのことなど、いろいろなことを話してくれた。

実はこの頃、私はカセットデッキのメーカーとして一時代を画した中道電気の社長、中道悦郎氏と親しく、彼が亡くなった後、E.ナカミチ財団の音楽事業の遂行を任されていたので、2年後の85年にはこの財団の主催で再び日本でシュヴァルツコップのマスタークラスをやろうと計画し、彼女本人の了承も得ていた。だが、その85年の初めに彼女は腰を悪くして、ドクターストップで長い時間飛行機に乗れないと言って来た。
次回の1985年は、大阪のザ・シンフォニーホールと草津、それに私が84年からつくば国際音楽祭のプロデューサーをしていた関係で、つくばノバホールでマスタークラスをと目論んでいたが、このプランは幻となり、代わりにビクトリア・デ・ロス・アンヘレスがこのプロジェクトを86年に引き受けてくれた。
そんなことがあったが、私はその1985年の12月9日、シュヴァルツコップの70歳の誕生日にベルリンのホテル・ケンピンスキーで彼女と会うことができた。「ごく一部の親しい人だけが集まってワインを飲んだりおしゃべりをするだけだけど、いらっしゃい」と言われて、その日の夕方5時頃に彼女の部屋を訪ねた。7時頃には彼女の招いた友人たちが揃い、部屋にはキャンドルが灯され、皆でさまざまな話をした。途中、カラヤンも後で来るからねと彼女が話していたら、テレビのニュースでカラヤンが出てきて、皆で談話をしながら見ることとなった。が、その話の内容が悪かった。カラヤンはテレビで自分の映像プロダクションの自慢話をし始めた。「私は遂に自分の理想の《ばらの騎士》のプロダクションをやっと完成した。侯爵夫人はアンナ=トモワ・シントウで。1983年、1984年にザルツブルクで制作したものだ」と。
一瞬、部屋の中は凍りついたようになった。シュヴァルツコップは直ぐにテレビを消すように私に命じた。
長い沈黙。誰もが言葉を失った。全員がしばらく言葉を発せない、というハプニングになった。
70歳の誕生パーティ以来、私は久しく彼女と会う機会がなくなり、またもとのクリスマス・カードと誕生日12月8日に電報を打つだけの「親子関係」に戻ってしまった。
2001年9月26日、ウィーンのカラヤン・センターで、BMGから新たに発売される1960年の《ばらの騎士》のDVDについての記者会見があると、オットー・エーデルマンからウィーン在住のピアニスト細木朝子さんを通じて案内が来た。その日はちょうど録音の仕事がない日だったので、昼間から会見に出かけてみた。ところが、神の引合せだったのだろうか、思いもかけないことに、その席にシュヴァルツコップが!
記者会見が一通り終って、DVDにサインをもらう列の最後に、昔と同じように私も同様に並んだ。やっと順番が来てサインをもらうべく買ったばかりのDVDを出して話をすることができた。「ヒロシはウィーンで仕事をしていると知っていたから、ひょっとして会えるかなあ、と思っていたよ」と話してくれた。そしてカメラを向け、写真をとってもいいかとたずねたら、昔なら絶対にOKをくれなかった写真嫌いの彼女が、「こんな年寄りでよければ、どうぞ!」と許可をくれた。それが私に対する「母親」の最後の贈り物だった。
20世紀最大のソプラノ歌手といっても過言ではない。名花エリザベート・シュヴァルツコップは、最後にお住まいになっていたオーストリアの自宅で2006 年8月3日亡くなった。
その報に接した瞬間、私には音楽の道における母親のような存在だった彼女と一緒に過ごした時間や、仕事をしたさまざまな思い出が、走馬灯のように蘇ってきた。前年の2005年12月8日、「90歳のお誕生日おめでとう!」と電報を出した時、「いつ亡くなられても仕方がないから覚悟しておかなくては」と思ったが、それがついに現実のものとなったのだった。
*「人生を変えたリート~シュヴァルツコップを偲んで」(『レコード芸術』2006年11月号を一部加筆して掲載)