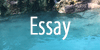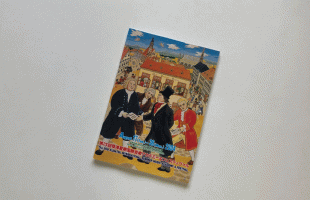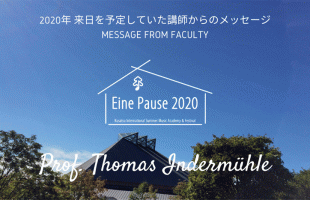文・樋口隆一
第18回プログラムより(1997年8月発行)
現代ロシアの作曲家アルフレート・シュニトケが《クアジ・ウナ・ソナタ》という不思議な題名の作品を書いている。本来はヴァイオリンとピアノのための作品らしいが、私の持っているCDは、1987年に作曲者自身が室内オーケストラ用に編曲したものだ。イタリア語の題名は、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ「月光」の「ソナタ・クアジ・ウナ・ファンタジア」をもじったのだろうが、訳すと「ソナタのように」ということになる。どこかふざけたところのある音楽だから、作曲家本人は「ソナタもどき」くらいの意味で言っているのだろう。
何がふざけているかといえば、それはもう最初からおかしい。いきなりピアノがト短調の和音をガーンと叩いたかと思うと、4秒ぐらい沈黙があり、こんどはヴァイオリンがおよそ非音楽的な雑音をグシャッとやり、また10秒ほどの沈黙がある。それからもト短調の和音と無調、クラスターが、ストラヴィンスキーのパロディーまで交えながらほとんど妥協なく交錯する。ところがそんなナンセンス(無意味)な世界に、突然きわめて意味深い情報が飛び込んでくるので、聴き手はハッとする。ヴァイオリンが心を込めて弾くのはB-A-C-Hの動機ではないか。その突然の瞑想的境地は、ヴァイオリンの暴力的なパッセージに妨げられながら、さまざまに展開されてゆく。そこから先はシュニトケの独壇場。いわゆる<多様式>の万華鏡が始まる。それは彼がマーラーやストラヴィンスキーの影響のうちに編み出した刺激に富んだ音楽である。
B-A-C-Hの動機といえば思い出すのが、シェーンベルクの《管弦楽のための変奏曲》作品31(1928)である。12音技法による最初の大規模な管弦楽曲として名高いこの傑作では、すでに序奏の部分からトロンボーンがかすかに吹き鳴らすこの動機が印象的だが、この複雑な音の構造物の中にしばしば見え隠れして、最後のフィナーレにおいて決定的な意味を与えられる。まさにそれはこの難解な作品の中で12音技法の本格的な応用に成功したシェーンベルクの勝利の宣言であり、そのことを可能としてくれたバッハという先達に対する深い感謝の表現でもある。
シェーンベルクにかぎらず、新ウィーン楽派の作曲家はバッハに強い関心を抱いていた。アントン・ウェーベルンの場合、バッハの《音楽の捧げ物》の6声のリチェルカーレ(フーガ)を大管弦楽のために編曲した《リチェルカータ》(1935)という作品がある。ウェーベルンはそこで、8小節からなる主題を7つの動機からなるものと分析し、それらをトロンボーン、ホルン、トランペットに交互に演奏させることによって、個々の意味を鮮明に浮き上がらせるように工夫している。これがいわゆる<音色旋律>と呼ばれるものである。ウェーベルンの編曲においては、楽器法だけでなく、例えば弦楽器の弓遣いの微細な変化による意味付け、すなわちアーティキュレーションも精緻を極めている。これが何を意味しているかといえば、本来声楽的な形式であったフーガを、器楽的な原理である小さな動機の集積として見直すことにより、より深い理解を可能とすることをめざしているのだとも考えられる。ひとつの有機体を、全体としてとらえると同時に、個々の細胞の集積としてとらえる考え方ということもできよう。
シェーンベルクは1928年に、バッハのオルガンのための《前奏曲とフーガ変ホ長調》BWV552を大オーケストラのために編曲しているが、その2年後の1930年に友人の指揮者フリッツ・シュティードリーに宛てた手紙の中で、彼の一連のバッハ編曲の根拠を説明しているのは興味深い。その一部を紹介しておこう。「今日の音楽の把握法は、水平と同様に垂直の関係における<動機的な>進行を明らかにすることを要求します。つまり私たちは、自明の前提である対位法的構造のうちに存する効果への信頼だけでは満足せず、これらの対位法を動機的な連関として知覚することを欲するのです。ホモフォニーはわれわれに、これらの連関をひとつの上声部において追うことを教えました。メンデルスゾーン、ヴァーグナー、ブラームスの<多声的ホモフォニー>という中間段階は、より多くの声部を追うことをわれわれに教えました。今日、わたしたちの耳と理解力は、これらの基準をバッハに応用しないでは満足しないでしょう。協和音のみによって見事に進行する声部から生じる<快い>効果だけでは私たちはもはや満足しません。私たちが必要とするのは、見通しを得るための明瞭性なのです。これらはみな、フレージングなしには不可能です。しかしながらフレージングは、パトスの時代が行ったように、<情動を強調するために>用いてはなりません。そうではなく、フレージングは、1.重さの関係を線の中に正しく配分し、2.動機労作を明らかにしたりぼかしたりし、3.各声部が全声部とすべての響き(明瞭さ)にたいして、格互に強弱関係を顧慮すべきなのです」。もしここでいうフレージングという言葉を適宜アーティキュレーションという言葉に置き換え、しかも著者の名を伏せて掲載したら、アーノンクールが古楽の演奏について語っている言葉かと錯覚する読者も少なくあるまい。
バッハの音楽の持つ意味論的ないしは象徴的な力に注目した作曲家にアルバン・ベルクがいる。彼が最後に完成した作品である《ヴァイオリン協奏曲》において、バッハのコラールが重要な意味を持っていることは良く知られている。カンタータ第60番《おお永遠よ、汝恐ろしき言葉》BWV60の最終曲をなす死のコラール「いまや足れり」が、第2楽章後半のアダージョで独奏ヴァイオリンによって引用され、それに木管のアンサンブルが応答するあたりから、この協奏曲は鎮魂の調べを奏で始めるのだ。ベルクはこの作品を「あるひとりの天使の思い出のために」書いたのであった。その天使とは、小児麻痺の後遺症で19歳の花の命を散らしたマノン・グロビウスのことである。ベルクはまたこの作品において、マノンの命日に由来する数<22>や、ベルク自身の運命数<23>、さらには、最後の恋人ハンナ・フックスを示す数<10>などを、作曲の際の小節数の割り出しに使っている。こうした数の象徴的用法も、バッハから学んだものに他ならない。
西洋音楽史を俯瞰すると、バッハという作曲家は中世以来のポリフォニー音楽の集大成を行った人物と考えてよい。ところが1750年に世を去ると、彼の音楽は一般には忘れられた。モーツァルトやベートーヴェンもバッハを高く評価していたが、1829年にメンデルスゾーンが《マタイ受難曲》を復活上演したあたりから、バッハはロマン派の音楽家たちの<導きの星>となる。古い音楽伝統を学ぼうとした彼らの目には、かつてその集大成を行ったバッハが、まさにその伝統の具現者と映ったのである。
20世紀、それも第1次世界大戦を経た後で、ストラヴィンスキーやヒンデミットのような新古典主義者と、彼らに異議を唱えたシェーンベルクに代表される新ウィーン楽派の双方が、それぞれの意味においてバッハに理想を求めたのも興味深い事実だが、その根底にはやはり19世紀以来のバッハ崇拝の伝統があったことは否めない。つねに新しい芸術を求めてやまないヨーロッパの芸術が、しかもなお意識せざるを得ない伝統の存在。20世紀の作曲家にとっても、バッハこそはまさにその伝統の結晶にほかならないのである。
樋口隆一(1946〜)
専門領域はバッハとシェーンベルクを中心とする西洋音楽史。音楽学研究、指揮、音楽評論と、幅広く活躍している。『新バッハ全集』I/34の校訂でテュービンゲン大学哲学博士。明治学院大学名誉教授。国際音楽学会前副会長。日本アルバンベルク協会常任理事。DAAD友の会会長。第3回京都音楽賞評論研究部門賞、第2回辻荘一賞受賞。『バッハ』(新潮文庫)、『バッハ・カンタータ研究』(音楽之友社)など著書多数。2002年3月オーストリア学術芸術功労十字章が授与された。当音楽祭には第13回「バロックからクラシックへ?」、第40回「バッハが生きた時代」等、長きに渡り寄稿している。ウィーン楽友協会のオットー・ビーバ博士との親交も深い。